RFPとは?目的・構成・作成ポイントまで徹底解説!

ITプロジェクトやシステム導入を成功に導くためには、適切なパートナーの選定が不可欠です。そのための「道しるべ」として多くの企業で利用されているのが、RFP(提案依頼書)です。
しかし、RFPは単に依頼内容をまとめた文書ではなく、プロジェクトの方向性を示し、双方の期待値を明確にするための戦略的なツールでもあります。
ここでは「RFPとは何か」という基本的な概念から、その作成において押さえておくべき重要なポイントを解説します。企業の目的やニーズを適切に伝えることで、プロジェクトの成功を引き寄せるRFPの作成方法を、一つ一つの要素に沿って考えていきましょう。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談する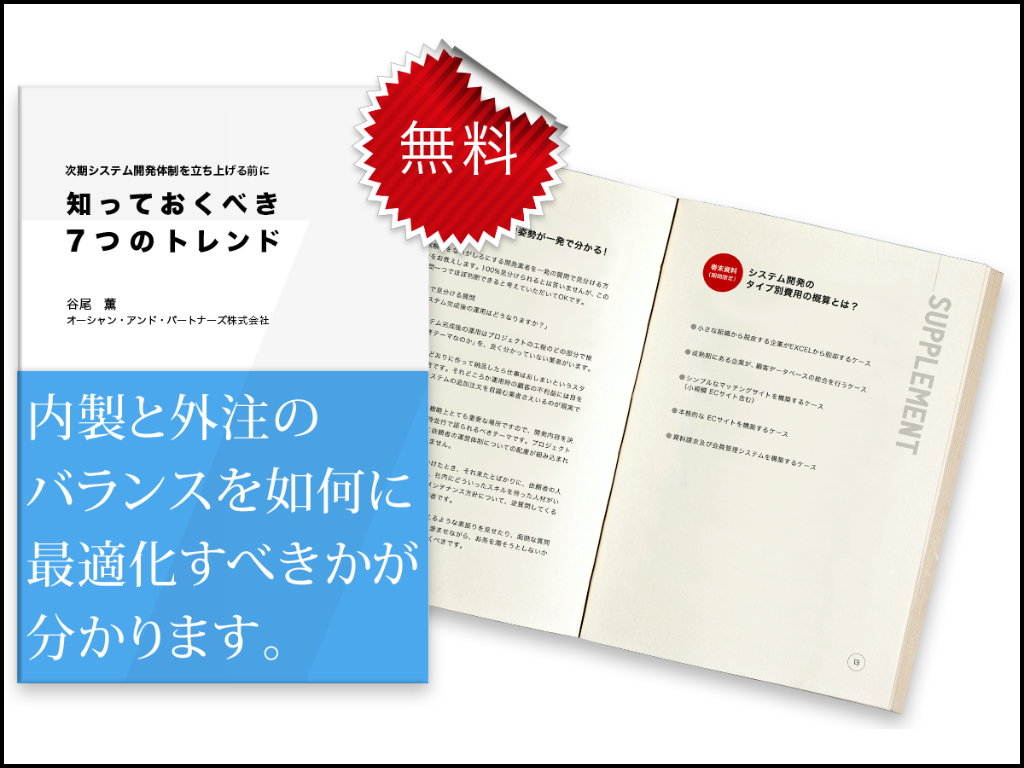
目次
RFPとは?基本概念を解説!

まずはRFPとはどんなものなのか、理解を深めておくことが重要です。似た言葉であるRFIと混同されることも多いため、違いはもちろんREPの正しい意義や目的などを知っておく必要があるでしょう。
はじめに、RFPに関する基本的な概念の部分について解説していきます。
RFP(提案依頼書)とは
RFP(Request for Proposal)、つまり提案依頼書とは、企業が新しいシステムの構築やサービスの導入を検討する際に、外部のベンダーやサービス提供者に対して具体的な提案を求めるための重要なドキュメントです。
しかし、RFPは単なる書類ではありません。それは、プロジェクトの方向性を定め、必要なリソースを効率的に確保し、プロジェクトの成否を左右する「羅針盤」のような役割を果たします。
RFPとRFIの違い
RFPとRFIは混同されることがありますが、目的が異なります。RFIは情報収集が主目的で、複数のベンダーからサービス内容や能力の情報を集める段階です。
対してRFPは、情報を基に具体的な提案を依頼し、最終的な選定につなげる段階を指します。
RFPには、プロジェクトの背景、目的、スコープ、要件、納期、予算、評価基準など、ベンダーが提案を行う上で必要な情報を、詳細に記載します。明確で具体的なRFPを作成することで、ベンダーからの提案内容の質を高め、最適な提案を受けやすくなるのです。
このように、RFPには具体的な要件や評価基準が含まれるため、ベンダーはその内容に基づいて提案書を作成することとなります。あくまで参考情報の収集であり、契約や発注を前提とするものでは無いという点にも留意すべきでしょう。
どう言った目的でRFPを作成するのか?

RFPを作成する目的は、単にベンダーへ提案依頼をすることだけではありません。むしろ、発注側の組織が自らの課題や要件を整理し、社内で共通認識を持つためのプロセスとしての意味合いが大きいと言えます。
複数の候補先から客観的に比較できるような提案を得るためにも、RFPの存在は欠かせません。ここでは、具体的にどのような目的でRFPが作成されるのかを詳しく見ていきます。
社内要件の整理と共有
RFP作成の大きな目的の一つは、社内に点在する要件を整理して一つの文書に落とし込み、関係者全員で共有することです。
企業内の各部門はそれぞれ異なる期待や要望を持っており、プロジェクトに対する視点がばらばらになることが少なくありません。そのままベンダーに依頼を出してしまうと、後から「この機能はいらなかった」「想定していた仕様と違った」といった齟齬が生じやすくなってしまいます。
RFPを作成する過程で社内の意見を調整すれば、必要な機能と不要な機能を取捨選択し、最終的なゴールを明確化できます。結果として、社内の合意形成が進み、ベンダーに対しても一貫性のある情報を提供できるのです。こうした要件整理は、短期的な発注の正確性だけでなく、長期的なシステム運用の安定性にも直結する重要なステップです。
ベンダーから最適な提案を引き出す
RFPは、ベンダーから質の高い提案を引き出すための手段でもあります。発注側が要件や背景を明確に示すほど、ベンダーは具体的かつ実現可能性の高い解決策を提案しやすくなります。
例えば「コスト削減を重視している」「将来的に拡張性を持たせたい」といった条件を明記しておけば、ベンダーはその方針に沿った提案を組み立てられるようになるでしょう。
また、複数社から提案を受ける際も、共通の評価基準があれば比較が容易になり、単純な価格競争に終わらない選定が可能です。
RFPを通じてベンダーの持つノウハウを引き出すことで、発注者にとって最適なパートナー選びに繋がります。これこそがRFPを導入する大きな価値のひとつと言えるでしょう。
透明性と公平性の確保
もう一つの重要な目的は、選定プロセスにおける透明性と公平性を担保することです。もし依頼を口頭や非公式なやり取りに頼ってしまうと、特定のベンダーが優遇されているように見えたり、不公平感からトラブルが発生するリスクがあります。
RFPを文書として作成し、全てのベンダーに同じ条件を提示すれば、公正な提案依頼が可能になります。これにより、評価基準も明確化され、発注側は納得度の高い意思決定を下せるのです。
特に公共案件や大規模プロジェクトでは、調達過程の透明性は信頼性に直結します。RFPを活用することで、企業は「公平で公正なベンダー選定を行った」と内外に示すことができるでしょう。
RFPのメリット・デメリットを解説!
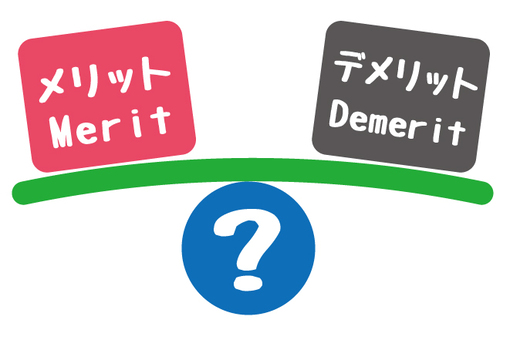
RFP(提案依頼書)は、ベンダー選定をスムーズかつ公正に進めるための有効な手段ですが、同時にメリットとデメリットの両方を持ち合わせています。
会社にとって効率化などのメリットを与える一方で、RFPが負担やリスクになる場合もあるということです。ここからは、RFPを作成・運用する際のメリットとデメリットについて、具体的に解説していきます。
メリット
ここまでご説明してきた内容を踏まえ、RFPを導入する最大のメリットは、発注側のニーズを正確にベンダーへ伝えられることです。要件や背景を明確にしたうえで文書化することで、ベンダーは曖昧さのない具体的な提案を出しやすくなるというわけです。
複数ベンダーから提案を受け取ることで、比較検討の幅も広がります。価格だけでなく、サービス品質や導入後のサポート体制、拡張性や将来性といった観点も加味して評価できるため、より最適なパートナー選びが可能になります。
さらに、調達プロセスの透明性や公平性も確保できるメリットもあるでしょう。全てのベンダーに同じ条件を提示するため、不公平な競争を防ぐことができ、企業の信頼性を高める効果も期待できるのです。
「社内要件の整理」「複数ベンダー間の公平な比較」「透明性の確保」という3つの大きなメリットを発注側にもたらし、結果的に成功率の高いプロジェクトを実現できるのです。
デメリット
一方で、RFPには注意すべきデメリットも存在します。まず大きな課題は「作成の手間とコスト」です。
詳細な要件を整理し、社内調整を行ったうえで文書化するには多大な時間と労力が必要です。場合によっては専門知識を持つ担当者をアサインする必要があり、準備段階で負担が増大するケースもあります。
要件定義が不十分なままRFPを作成してしまうと、ベンダー側が誤った前提で提案を行うリスクがあります。その結果、見積りや提案内容が現実と乖離し、後々の修正や再調整で余計なコストや時間が発生してしまう恐れもあるのです。
さらに、RFPは内容を詳細に記載するがゆえに、柔軟性を欠くという面もあります。要件を固めすぎると、ベンダーの独自性や創造的な提案を引き出しにくくなり、本来ならもっと良い解決策があったのに見逃してしまうケースも考えられるでしょう。
このようにRFPには「作成にかかるコストと工数」「要件定義の難しさ」「柔軟性の欠如」という弱点があり、正しく活用するには注意が必要です。メリットを享受するためには、これらのデメリットを十分に理解した上で運用せざるを得ません。
効果的なRFPの構成要素は?

RFPを構成する要素は多岐にわたりますが、特に重要な要素を以下に示します。
背景情報と目的の共有
RFPの冒頭では、プロジェクトの背景と目的を明確にし、なぜこのプロジェクトが必要なのかを示します。ベンダーが目的を理解することで、より効果的な提案が期待できます。
具体的な要件定義
機能要件と非機能要件の両方を具体的に記載します。機能要件にはシステムが「何をすべきか」を、非機能要件には「どのように」動作するべきかを示します。詳細な要件があることで、ベンダーの理解が深まり、提供されるソリューションの精度も高まります。
予算とスケジュールの提示
予算とスケジュールを明確にすることで、現実的な提案が受けやすくなります。企業としての期待と、ベンダーとしての実現可能性を事前に調整できる重要な要素です。
評価基準と選定プロセス
提案をどのような基準で評価するのかを明示することで、ベンダー側もそれに合わせて提案内容を調整しやすくなり、フェアな競争が可能になります。
成功するためのRFP作成のポイントとは?

成功するRFPは、現場の具体的なニーズと経営層の視点がしっかりと反映されているものです。現場の担当者は日々の業務を通じて実際の課題を把握しており、その意見を反映させることは非常に重要です。
同時に、経営者が「なぜこのプロジェクトを進めるのか」という大きな方向性を示すことで、RFPが戦略的な文書となります。この二つの視点の融合が、後の運用面でも役立つRFPの作成につながります。
RFP作成におけるリスク管理と柔軟性の確保

どのプロジェクトにも不確定要素やリスクが存在しますが、RFP作成段階からこれらのリスクを想定し、対策を講じておくことが重要です。
たとえば、プロジェクトの変更が発生した場合の柔軟な対応や、進行に伴う予算調整の必要性などについて、ベンダーがどのように対応できるかを事前に明示することで、スムーズなプロジェクト推進が可能となります。
作成プロセスで見落としがちなポイント
多くの企業が見落としがちなのが、RFP作成の初期段階で予算感を固めておくことです。具体的な予算が決まっていないと、ベンダー側も費用の見積もりが難しく、結果的に安価な選択が高くついてしまうことがあります。また、曖昧な表現や不足している要件は、後のトラブルの原因となるため、初期段階での細部への配慮が求められます。
RFPの作成に困ったならオーシャン・アンド・パートナーズへ!

RFPは、プロジェクトやサービス導入を成功させるための重要な文書です。明確な要件を整理し、複数のベンダーから最適な提案を受けることで、プロジェクトの成果を最大化できます。しかし、作成には時間や専門知識が必要なため、初めての方や複雑なプロジェクトでは作成が難しい場合もあるでしょう。
そんな時は、オーシャン・アンド・パートナーズのサポートを受けることで、要件整理からRFP作成、ベンダー選定まで一貫して支援できます。専門家のアドバイスを活用することで、効率を向上させながら正確にRFPを作成し、プロジェクトの成功確率を高められるでしょう。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
この記事を書いた人について

-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社 代表取締役
協同組合シー・ソフトウェア(全省庁統一資格Aランク)代表理事
富士通、日本オラクル、フューチャーアーキテクト、独立系ベンチャーを経てオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社を設立。2010年中小企業基盤整備機構「創業・ベンチャーフォーラム」にてチャレンジ事例100に選出。
最新記事一覧
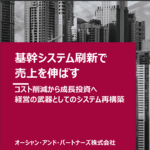 経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか?
経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか? 経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは
経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは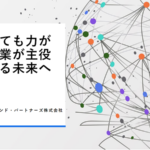 経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録
経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録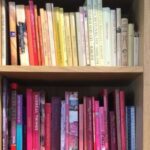 RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―
RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―










