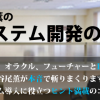基幹システムの導入の価格相場とは?失敗しないためのポイントを徹底解説!

基幹システムの導入を検討している企業にとって、「いったいどれくらいの価格になるのか?」という疑問は非常に大きなものです。
クラウド型とオンプレミス型の違い、さらにはスクラッチ開発との価格差、コストを抑えるための工夫など、価格に関する情報は複雑です。
この記事では、基幹システムの導入にかかる価格相場や構成要素を徹底解説し、貴社に最適な導入形態を選ぶためのヒントを提供します。
あくまで金額は目安ですので、参考にしてください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
目次
基幹システムとは?

企業活動に欠かせない販売管理、在庫管理、会計、人事といった業務を統合的に支えるのが「基幹システム」です。
これらの機能を連携させることで、業務効率を向上させ、意思決定を迅速化することが可能になります。近年では、クラウド技術の進展により、従来のオンプレミス型に加え、クラウド型基幹システムの導入も広がっています。
中堅・中小企業においても、業務の複雑化や人手不足の影響から、基幹システムの導入ニーズは年々高まっています。ただし、費用や運用の負荷、導入スピードなどにおいて最適な選択肢は企業ごとに異なります。そのため、価格だけでなく、自社の業務やリソースに合った導入形態を見極めることが重要です。
本記事では、導入形態ごとの費用相場を比較しながら、価格の内訳や注意点を詳しく解説していきます。
基幹システムの導入タイプと価格相場

基幹システムの導入形態にはクラウド型、オンプレミス型、スクラッチ開発があり、それぞれ価格や導入スピード、保守体制、拡張性や運用負荷が大きく変わるため、向いている企業も異なります。
そのため、早い段階で自社に合った導入形態を見極めることが大切です。
これら3つの導入タイプについて、価格の目安や導入傾向をわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
あくまで金額は目安ですので、参考にしてください。
クラウド型
クラウド型基幹システムは、インターネット経由で提供されるサービスを利用する形式です。初期費用を抑えられる点が特徴で、月額利用料(サブスクリプション)を支払うことでサービスを利用します。
価格設定の考え方として、中小企業向けのプランであれば初期費用は比較的抑えめに設定されており、月額利用料も段階的な料金体系となっていることが一般的です。具体的な金額は企業規模や必要機能によって大きく変動するため、複数社から見積もりを取得して比較検討することが重要になります。
クラウド型は導入までのスピードが早く、運用や保守もベンダーに任せられるため、ITリソースが限られた企業に向いています。一方で、カスタマイズの自由度は低めであり、自社独自の業務プロセスがある場合には制限となることもあります。
また、利用人数や機能によって料金が段階的に上がるため、スケーラビリティとコストのバランスを慎重に見極めることが必要です。
オンプレミス型
オンプレミス型とは、自社サーバーにソフトウェアをインストールして運用する形式です。カスタマイズ性が高く、社内システムとの統合やデータ管理を柔軟に行えるのが大きなメリットです。しかしながら、その分初期費用が高額になる傾向があります。
価格の考え方として、オンプレミス型では初期投資が大きな比重を占める構造となっています。サーバー購入費、ソフトウェアライセンス料、導入作業費などが一括で発生するため、資金調達やキャッシュフローへの影響を慎重に検討する必要があります。カスタマイズの範囲によっては開発費用が大幅に増加する場合もあるため、要件定義の段階で必要な機能を明確にしておくことが重要です。
導入には数カ月から1年以上かかることもあり、IT部門のリソースも多く求められます。セキュリティやデータの自社保管に強いこだわりがある企業や、既存の業務システムと密に連携したいケースには向いていますが、初期コストと保守運用の手間は留意すべき点になります。
スクラッチ開発
スクラッチ開発とは、ゼロから自社専用の基幹システムを開発する形式です。業務に完全にフィットする設計が可能で、拡張性も非常に高いですが、一方で一般的に高額になることが多いです。
価格の考え方として、スクラッチ開発では開発工数が価格に直結するため、要件の複雑さや開発期間によって費用が大きく変動します。システムの規模感としては、小規模なものから大企業向けの大規模システムまで幅広く、それに応じて投資額も変わってきます。重要なのは、開発前の要件定義と仕様策定を丁寧に行い、後から追加開発が発生しないよう計画することです。
導入までに1年から2年を要することもあり、短期間での導入は難しい傾向です。また、運用後の改修や保守にも専用のリソースが必要となるため、長期的な運用体制の整備が欠かせません。このため、大手企業や特殊業務を行う企業であれば投資に見合うメリットがありますが、中小企業にはハードルが高い選択肢といえるでしょう。
基幹システムの価格はどう決まる?

基幹システムの導入費用は、単に「製品を購入するだけ」の金額では済みません。実際には、要件定義や初期設定、開発・カスタマイズ、導入後の保守・運用など、前後のプロセスに多くのコストが関わってきます。
そのため、見積書に記載された数字だけを見て判断するのは危険です。費用の価格の内訳を正しく理解することで、自社に合った無理のない投資判断ができるようになります。
以下では、基幹システムにかかる主な費用構成について詳しく解説します。
①ライセンス費用
ライセンス費用は、ソフトウェアを利用するための基本的な費用です。
クラウド型であれば月額制が多く、利用ユーザー数や選択する機能によって価格が変動します。一般的な相場として、基本ライセンス費用が月額10万円〜100万円、ユーザーごとのライセンス費用が1ユーザーあたり月額1,000円〜1万円程度となっています。
一方、オンプレミス型では、買い切り型のライセンスが主流で、導入時に数百万円〜数千万円の費用が発生します。クラウド型は利用期間中ずっと支払いが続くのに対し、オンプレミス型は初期にまとまった費用が必要ですが、その後の継続的なライセンス料はかかりません。
契約時には、ライセンス形態ごとのコスト発生タイミングや総額を長期的な視点で確認し、支払い計画を立てることが重要です。
②導入・初期設定費用
導入・初期設定費用は、要件定義やシステム設計、初期設定、テスト、教育などの工程にかかるコストです。
先ほどお伝えしたクラウド型、オンプレミス型、スクラッチ開発の費用は、システムの規模やカスタマイズの度合いによって大きく変動します。特にオンプレミス型やスクラッチ開発では、独自要件やカスタマイズ対応が多くなるため、初期費用が高額になる傾向があります。
導入後のトラブルを防ぐためにも、この初期工程の質は非常に重要です。必要に応じてPoC(概念実証)を活用し、要件や仕様の妥当性を事前に確認することも検討しましょう。
③開発・カスタマイズ費用
業務に合わせたシステムの調整が必要になる場合、カスタマイズ費用が発生します。テンプレート型のクラウドサービスでは制限があるものの、オンプレミス型やスクラッチ開発では、かなり柔軟な設計が可能です。
相場としては、1機能あたり数十万円〜数百万円となり、全体では1,000万円を超えることもあります。開発内容によっては外部ベンダーとの綿密な調整が求められるため、スケジュールにも余裕を持つことが大切です。
④保守・運用コスト
保守・運用コストは、システム導入後も継続的に発生する費用です。
クラウド型の場合は、これらのコストが月額利用料に含まれていることが多く、障害対応やシステムアップデート、法改正への対応などもサービス範囲内で提供されます。
一方、オンプレミス型では別途保守契約が必要となります。システムの規模や保守範囲によっては、年間数十万円台で収まる場合もあれば、委託範囲が広い場合は300万円を超えることもあります。
自社内で運用を行う場合には、IT担当者の人件費も合わせて考慮するようにしましょう。
クラウド型とオンプレミス型の基幹システムの価格を比較

導入形態の選択は、価格面においても大きな違いをもたらします。
ここでは、クラウド型とオンプレミス型の費用・価格の構造を具体的に比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
あくまで金額は目安ですので、参考にしてください。
初期費用の違い
基幹システムの導入において、初期費用の差は導入方法によって大きく異なります。
以下の表は、クラウド型とオンプレミス型の初期費用に関する主な違いをまとめたものです。
| 比較項目 |
クラウド型 |
オンプレミス型 |
| 初期費用 | オンプレミスと比較して相対的に費用が 低いケースが多い(場合によっては 数100万円以内に収まるケースも) | 初期見積が低価格でも最終的には1,000万円以上 |
| サーバー構築 |
不要(ベンダー側で用意) |
自社で購入・構築が必要 |
| ソフトウェア設定 |
ベンダーが初期設定を実施 |
自社またはSIerによる導入作業が必要 |
| 導入までの期間 | 数週間~数ヵ月 | 最低半年〜数年 |
クラウド型の最大のメリットは、初期コストを大幅に抑えられる点にあります。多くのサービスで初期費用が100万円以内に収まることが多く、予算に限りのある中小企業でも比較的導入しやすいのが特徴です。
一方、オンプレミス型では、自社サーバーの構築や環境設定に大きな投資が必要となります。初期見積もりが低価格であっても、最終的には1,000万円以上の費用がかかるケースが多く、一般的には数千万円から億円単位の投資規模となります。このようにまとまった費用がかかるため、慎重な予算計画と長期的な運用視点が欠かせません。
そのため、初期投資をできるだけ抑えたい企業にとっては、クラウド型がより現実的で導入しやすい選択肢といえるでしょう。
月額・年間コストの違い
クラウド型とオンプレミス型では、導入後にかかる継続的にかかる費用や価格にも大きな差があります。
以下の表は、月額料金・保守費・サーバー維持費などの違いをまとめたものです。
|
比較項目 |
クラウド型 |
オンプレミス型 |
|
月額コストの目安 |
数万円~10万円程度 |
なし(買い切りが中心) |
|
年間保守費用 |
月額に含まれることが多い |
数十万~300万円程度 |
|
サーバー維持費 |
不要(ベンダーが管理) |
発生(電気代・運用管理費) |
|
その他のコスト |
オプション機能・ユーザー数によって増加 |
人件費・システム更新費が発生 |
|
資金繰りへの影響 |
支払いが分散されるため安定しやすい |
初期費用+維持費で管理が難しい場合も |
|
コスト面の特徴 |
継続コストは予測しやすく、管理しやすい |
中長期で見るとコストがかさみやすい傾向 |
クラウド型は、毎月の利用料という形で費用が発生しますが、支払いが定期的に分散されるため資金繰りの安定にもつながります。
一方で、オンプレミス型は保守費用や人件費などが後から重くのしかかる場合もあり、導入前に全体のランニングコストを試算しておくことが不可欠です。
導入後の運用負荷の違い
基幹システムは、導入して終わりではありません。むしろ導入後の運用こそが、日々の業務に大きく影響を及ぼします。クラウド型とオンプレミス型では、運用・保守にかかる労力や必要なリソースが大きく異なります。
導入後の運用負荷の違いを比較した表が、以下のとおりです。
|
比較項目 |
クラウド型 |
オンプレミス型 |
|
運用・保守の主体 |
ベンダーが担当 |
自社または外部委託 |
|
ソフトウェアの更新 |
自動で適用される |
自社で実施(手動更新) |
|
セキュリティ対応 |
自動アップデートにより対応 |
パッチ適用・監視を自社で管理 |
|
サーバー管理 |
不要(クラウド上に設置) |
必要(監視・点検が必要) |
|
IT人材への依存度 |
低い |
高い(社内に専任担当者が必要) |
|
日常業務への影響 |
ほぼなし |
担当者の業務負荷が増大する場合あり |
クラウド型は、運用・保守の多くをベンダーに任せることができるため、IT担当者が少ない企業でも無理なく運用が可能です。ソフトウェアのアップデートやセキュリティ対応も自動で行われることが多く、システムの安全性を高く保ちやすい点も大きなメリットです。
一方、オンプレミス型では、サーバーの監視や障害対応、ソフトウェアの更新などを自社で対応する必要があります。そのため、社内に専門知識を持つ担当者が求められ、場合によっては外部業者への委託や保守契約が不可欠となります。
このように、IT部門への負担を軽減し、安定した運用体制を築きたい企業にとっては、クラウド型がより適した選択肢といえるでしょう。
基幹システムの価格を抑えるための3つのポイントを徹底解説!

基幹システムの導入は、多くの企業にとって大きな投資ですが、ポイントを押さえればコストを無理なく抑えることも可能です。
そこで、ここでは、価格を抑えるために意識すべき3つのポイントをわかりやすく紹介します。
不要な費用を避け、無理のない形で納得のいく導入をするためにも、ぜひこれらのポイントを抑えておきましょう。
①必要な機能を明確にする
システム導入時にありがちなのが、「あれもこれも」と機能を盛り込みすぎてしまい、結果として費用が膨らむケースです。そこで重要なのが、業務に本当に必要な機能をあらかじめ明確にしておくことです。
業務フローを洗い出し、各部門で必要な機能をリスト化した上で優先順位をつけることで、不要な開発や過剰なライセンス契約を防ぐことができます。また、最小限の構成で導入し、段階的に拡張するスタイルもコスト抑制に効果的です。
②IT導入補助金などを活用する
中小企業がITツールを導入する際には、「IT導入補助金」などの国の支援制度を活用することで、大きな費用削減が可能になります。IT導入補助金を利用すれば、対象経費の最大3分の2、条件によっては最大4分の3まで補助してもらうことができます(補助額の上限は最大450万円)。
申請には所定のタイミングや要件があるため、IT導入支援事業者(ベンダー)と相談しながらスケジュールを調整することが重要です。専用の申請フォーマットや相談窓口も用意されているため、情報収集を早めに行い、制度を効果的に活用することでスムーズな申請が可能になります。IT導入補助金について、詳しくは中小企業庁の資料をご確認ください。
③信頼できるベンダーを選定する
価格だけに目を奪われてベンダーを選んでしまうと、後々トラブルや追加費用が発生するリスクがあります。価格だけでなく、過去の導入実績やサポート体制、提案力なども含めて総合的に判断しましょう。
また、提案内容の根拠や費用の内訳が明確であるかも重要なチェックポイントです。価格が安くても、運用後に必要な保守費や追加開発費が別途かかる場合もあるため、初回の見積もり時に「総コスト」の観点で比較すると良いでしょう。
基幹システム導入で失敗しないためのポイントも紹介!

「コストが安いから…」「有名なベンダーだから…」そんな理由だけで基幹システムを選んでしまうと、導入後に想定外のトラブルや追加費用に悩まされることになりかねません。
基幹システムは企業の業務を支える「中枢」であり、導入は一度きりではなく長期的な視点が求められます。
ここでは、価格だけにとらわれず、自社に本当に合ったシステムを見極めるために押さえておきたい重要なポイントを詳しく解説します。導入後に後悔しないための“目利き力”を身につけましょう。
相見積もりを取る
複数のベンダーから見積もりを取得することで、適正な価格かどうかを判断できます。
機能内容、保守費、カスタマイズ範囲などを統一した上で見積依頼を行うことが重要です。条件を揃えることで、単純比較がしやすくなり、不要なオプションの有無なども確認できます。
また、ベンダーごとの対応スピードや説明の丁寧さから、信頼性の高いパートナーを見極めるヒントにもなります。
費用対効果(ROI)を考慮する
導入費用が高額に見えても、それにより業務効率や売上が大幅に改善するならば、投資価値は高いといえます。
たとえば、年間500時間の作業削減が実現できれば、それに相当する人件費やミス削減効果を金額で算出し、ROI(投資対効果)を可視化することが重要です。
このROIを可視化するには、簡易的なExcel試算表を作成するのが有効です。基本的には、以下のような項目を入力して計算します。
【ROI試算の基本構成(Excelで作成可能)】
|
項目 |
内容 |
例 |
|
初期費用 |
システム導入にかかる費用 |
400万円 |
|
年間運用費 |
月額費用や保守費用など |
120万円 |
|
年間効果(コスト削減額) |
作業削減・人件費削減などの金額換算 |
300万円 |
|
年間効果(売上増加分) |
システム導入により見込める増収 |
200万円 |
|
ROI算出式 |
(効果合計 − 総コスト) ÷ 総コスト × 100 |
⇒ 33% など |
このように、ROI=(得られる効果-かかるコスト)÷コスト × 100 という計算式で、投資に対する効果を数値として把握できます。
判断材料のひとつとして、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
導入後のサポート体制を確認する
さらに、最低限備わっていてほしいサポート体制についても、事前に確認しておくことをおすすめします。
まず、障害時の緊急対応窓口があるかどうか、そして24時間対応が可能かを確認しましょう。基幹システムは業務の中核を担うため、営業時間外でのトラブルにも対応してもらえるかは重要なポイントです。
次に、ソフトウェアの定期アップデート提供について確認が必要です。特に法改正や税制変更への対応は、企業運営に直結する重要な要素となります。また、リモートまたは訪問による技術サポートが受けられるかも、問題解決の迅速性に大きく影響します。
さらに、サポート対応のSLA(サービスレベル合意)が明記されているかどうかも重要です。どの程度の時間内に対応してもらえるのか、保守契約の範囲内で何回まで問い合わせができるのか、時間制限はあるのかといった点を事前に把握しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
最後に、将来的なバージョンアップや機能追加への対応条件も確認しておきましょう。システムは継続的に改善されていくものですから、どのような条件で新機能を利用できるのかを理解しておくことが大切です。
基幹システムならオーシャン・アンド・パートナーズに相談!

基幹システムの導入には多くの選択肢があり、価格も導入形態によって大きく異なります。初期費用や運用コストだけでなく、導入後のサポート体制や自社の業務との相性までを含めて総合的に判断することが、失敗しないためのカギです。「とりあえず導入する」ではなく、「将来を見据えて最適な選択をする」という視点をもつことで、基幹システムは貴社の成長を支える心強い基盤となるはずです。
オーシャン・アンド・パートナーズでは、中堅・中小企業様向けにクラウド型・オンプレミス型の最適な導入支援を行っています。これまでに豊富な導入実績があり、大手IT企業出身の専門コンサルタントによる的確なアドバイスを提供しています。既存システムの調査や業務整理、基幹システムの再構築をはじめ、新規Webサービス導入、業務効率化ツール開発まで幅広く対応可能です。また、導入前後を含めた総合的なサポートも充実しており、安心してお任せいただけます。
費用や価格がどれくらいかかるのか分からない、何から始めればいいか不安という方も、まずはお気軽にご相談してみてはいかがでしょうか?
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
この記事を書いた人について
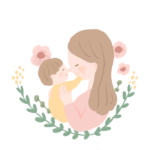
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。