IT投資で“甘えるな”と言わせない──責任者が通す稟議の切り口
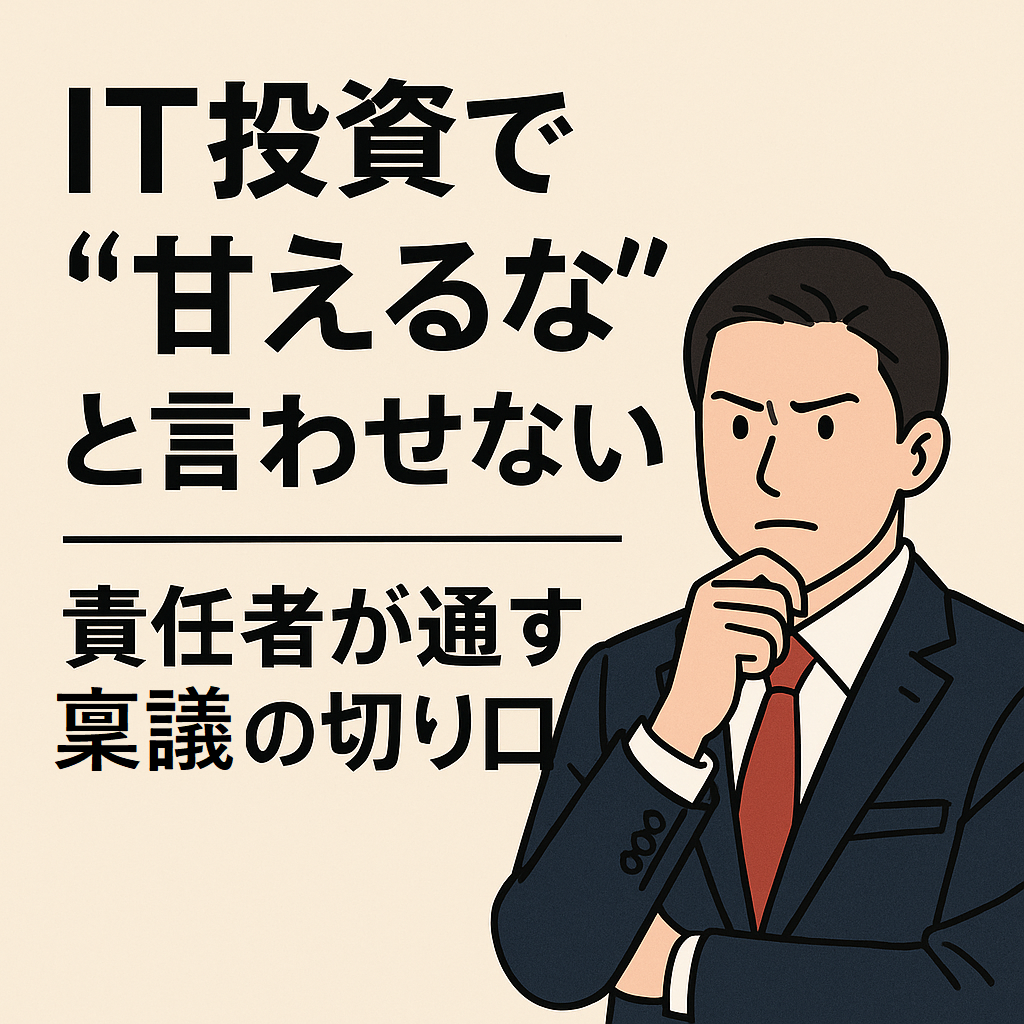
経費精算クラウド、請求書管理システム、勤怠管理ツール、営業支援SFA──。
業務を効率化し、生産性を高めることは誰の目にも明らかなのに、なぜIT投資の稟議は通りにくいのでしょうか。
背景には、経営層特有の発想があります。
「給料を払っているのだから、その中で頑張るべきだ」──。
そうした“心の声”が、実は多くの決裁を止めているのです。
本稿では、この“甘えるな”という心の声をどう読み解き、どう「納得」に変えるのか。
具体的な事例を交えながら、責任者が経営層を動かすための稟議の切り口を探っていきます。
目次
なぜIT投資の稟議は通りにくいのか
稟議を上げてもなかなか承認されない。そんな経験をしたことのある事業部門の責任者は多いのではないでしょうか。特にクラウドサービスやOA機器の更新といったIT関連の投資は、「今じゃなくてもいいだろう」「費用対効果が分からない」と言われ、後回しにされたり見送られたりするケースが目立ちます。
もしご自身の会社でIT投資の決裁が渋い傾向にあると感じるなら、その経営者の頭の中には、きっとこんな“心の声”が潜んでいるはずです。
「甘えるな。」
もちろん、会議の場でそう言い放つわけではありません。しかし「給料を払っているのだから、その中で頑張るべきだ」という価値観は、実際に多くの経営層の根底にあります。
ここで大切なのは、従業員の生産性や合理性の向上は、経営者が給料を支払うと決めた時点で、すでに期待値に含まれているということです。経営者から見れば「給料を渡しているのだから、社員はその中で最大限の成果を出してくれるはずだ」と考えるのが自然です。
だからこそ、社員から「効率化のためにクラウドを導入したい」「合理化のためにOA機器を更新したい」といった要望が出てきたとき、経営者にはこう映ってしまうことがあります。
「それはすでに給料の中に含まれている努力ではないか。ここでさらに経費をかけるのは二重払いになるのでは?」
つまり経営者が“甘えるな”と感じる背景には、重複した支払いを避けたいという合理性と同時に、「これだけ給料を払っているのだから、しっかり働いてほしい」という強い想いがあります。従業員を大切に思っているからこそ、簡単には追加支出に首を縦に振らないのです。
この経営者特有の感覚を理解しないまま稟議を上げれば、「甘えるな」という心の声に阻まれてしまいます。だからこそ、責任者には「その心理を受け止めたうえで、どう解消するか」という視点が求められるのです。
経営層の心理を理解する
経営層が大切にするのは「目に見える資産」です。
-
社屋や工場といった建物
-
従業員数
-
設備や車両
こうしたものは、誰の目にも「会社の規模」や「経営者の手腕」を象徴するものです。だからこそ投資しやすく、承認も通りやすいのです。
一方で、ITや仕組みへの投資はどうでしょうか。
システムやクラウドサービスは、導入しても外からは見えません。社員が便利になったとしても、それは経営層の目に直接映るわけではないのです。
そのため、「なくても仕事は回っているのだから、まだ我慢できるのではないか」という判断になりやすい。つまり、経営層にとってIT投資は「見えない支出=優先度の低いコスト」に見えてしまうのです。
「甘えるな」という心の声の正体
経営層は本当に「社員が楽をすること」を嫌がっているのでしょうか。
──実はそうではありません。
その正体は「効果が見えない支出」に対する不安です。
投資をしても成果が証明できなければ、ただコストを増やしただけになる。そうしたリスクを嫌うあまり、防御的に「甘えるな」という心の声が生まれるのです。
つまり「甘えるな」とは、怠けを咎める言葉ではなく、成果が分からないことへの恐れの表れなのです。
責任者の役割は、この“不安”を数字やストーリーで解消してあげることにあります。
視点の転換①:支出ではなくリスク回避
ケース1:経費精算クラウド
従来は紙やExcelで処理を行い、1件につき10〜15分かかっていたとします。これをクラウド化すれば、処理は数分で済みます。年間で数百時間単位の削減になるのは容易に想像できるでしょう。
この時間削減は単なる効率化にとどまりません。
-
その時間を使って新しい提案書を作れる
-
顧客対応のスピードを上げられる
-
ミスが減り、社員が疲弊しなくなる
つまり、削減できた時間は新たな生産性を生み出す余地に直結します。
さらに、人材採用に力を入れている企業であれば、こう説明できます。
「このクラウド導入は、新たに社員を1人採用したのと同じ効果を持ちます」と。
稟議では「導入コストが○円です」と書くのではなく、「導入しないことで失われ続けるリスクが○時間、○円規模で発生しています」と伝えるのがポイントです。
視点の転換②:“見えない”を“見える化”する
ケース2:請求書管理システム
導入前は、月末になると経理部門が残業を重ね、請求ミスも発生していました。
導入後は、処理時間が3分の1になり、さらにエラーもゼロに。ダッシュボードで進捗を可視化できるようになり、経営層に「どれだけ改善したか」を即座に報告できるようになったのです。
IT投資の最大の弱点は「効果が目に見えにくい」ことです。
だからこそ、稟議においては「時間削減」「残業代換算」「エラー削減率」といった数値に落とし込む必要があります。
未来の効果を“見える化”できれば、経営層の「甘えるな」という心の声を「なるほど、これは投資に値する」と納得に変えることができます。
視点の転換③:給料を活かすための投資
ケース3:高速複合機・高性能PC
導入前は、印刷待ちや処理の遅さで、社員1人あたり毎月数時間が無駄になっていました。
導入後は待ち時間がほぼゼロになり、その分の時間は成果を生む仕事に充てられるようになったのです。
ここで強調すべきは、「社員を甘やかす投資」ではないということ。
本質は、「給料を払っているのなら、その給料が成果に直結するように環境を整える投資」だという点です。
稟議の言い換えとしては、
「社員を楽にさせる支出」ではなく「給料の価値を最大化する投資」。
この表現に変えることで、経営層の心の声を真正面から解消できます。
視点の転換④:勤怠管理クラウドは「見えない残業」を削る
ケース4:勤怠管理クラウド
勤怠管理はどの企業でも必須の業務ですが、手作業で行われているケースはいまだに多くあります。
-
Before:タイムカードやExcelで集計 → 担当者が数日かけて入力・修正
-
After:クラウド化により打刻データが即時集計 → 集計時間は数時間に短縮
これにより、経理・総務の負担が軽減されるだけでなく、サービス残業や不正打刻といった「見えない残業」も抑止できます。
削減できた時間は新しい付加価値業務に回せますし、労務リスクの低減は経営にとっても極めて重要です。
ここでも「人材採用と同等の効果」「リスク回避としての保険効果」を示せば、稟議は格段に通りやすくなります。
視点の転換⑤:営業支援ツールは「売上に直結する投資」
ケース5:SFA/CRM
営業活動は属人化しやすく、情報共有が不十分になりがちです。営業支援ツール(SFA/CRM)は、これを仕組み化し、組織全体で売上を積み上げる力を生み出します。
-
Before:各営業担当がExcelやメールで情報を管理 → 共有漏れや属人化で機会損失
-
After:顧客データや進捗が一元化 → 引き継ぎがスムーズ、提案スピードも向上
ここで重要なのは、時間削減効果だけではなく、**「売上に直結するストーリー」**を描けることです。
「情報共有により受注率が○%改善」「提案件数が月間○件増加」など、経営層がもっとも注目する“売上への寄与”を明示すれば、「甘えるな」という声は消えます。
営業支援ツールは、単なる効率化ではなく、企業成長のドライバーとなる投資として位置づけるべきです。
責任者に求められる“言い換え力”
ここまで見てきた通り、経営層は「甘えるな」という心の声を持っています。
その背景にあるのは「効果が見えない不安」です。
責任者に必要なのは、この不安を“別の言葉”に置き換える力です。
-
Before: 「便利になるからクラウドを導入したい」
-
After: 「クラウド導入で年間○時間削減。残業代換算で○万円削減、さらに新規提案の時間が創出される」
この“言い換え力”こそ、稟議を通すための最大の武器です。
まとめ:稟議は未来を動かす提案
もし経営層の頭の中に「甘えるな」という心の声があるのなら、それは社員を責める言葉ではなく、「効果が見えない不安」の裏返しです。
責任者が取るべきアプローチは明確です。
-
リスク回避の視点で語る
-
見える化で安心感を与える
-
給料の価値を最大化する投資だと位置づける
-
売上成長や人材採用と同等の効果を伝える
IT投資は“甘え”ではなく“未来を守る必然”。
稟議は単なる承認依頼ではなく、経営層の意識を変える提案にできるのです。
そして、それを実現できるのは、稟議を上げる責任者であるあなたです。
この記事を書いた人について

-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社 代表取締役
協同組合シー・ソフトウェア(全省庁統一資格Aランク)代表理事
富士通、日本オラクル、フューチャーアーキテクト、独立系ベンチャーを経てオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社を設立。2010年中小企業基盤整備機構「創業・ベンチャーフォーラム」にてチャレンジ事例100に選出。
最新記事一覧
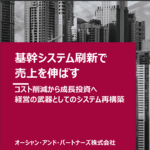 経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか?
経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか? 経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは
経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは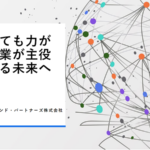 経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録
経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録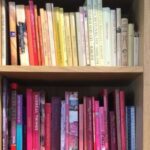 RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―
RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―










