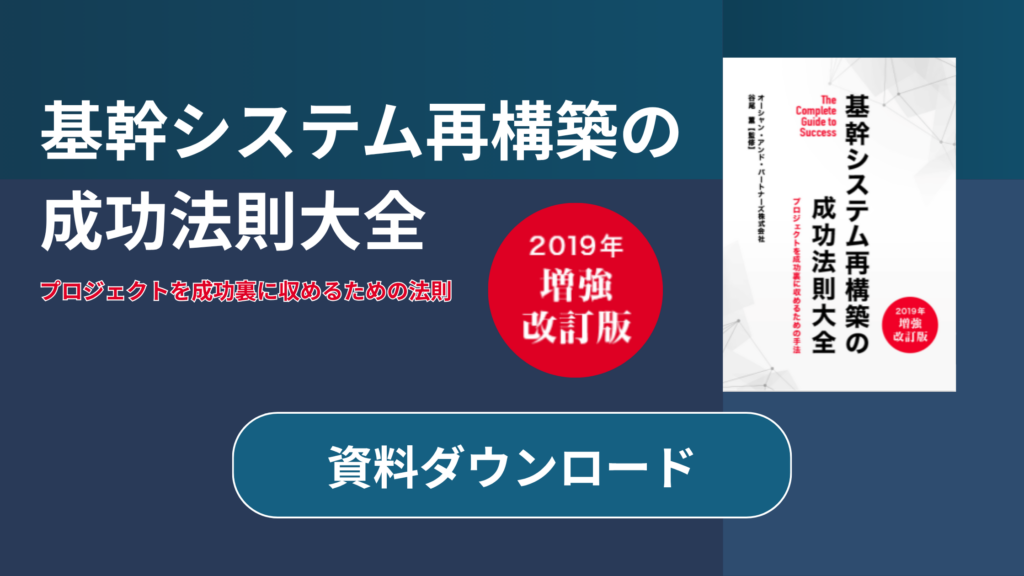基幹システム再構築の際の進め方とは?進め方と注意点まで徹底解説!

企業が長年使ってきた基幹システムは、時代の変化とともに老朽化し、業務効率や柔軟性の面で課題が出てきます。システムの再構築は単なるリニューアルではなく、企業の事業戦略や将来の成長を左右する重要なプロジェクトです。
本記事では、基幹システム再構築の適切なタイミングから、具体的な進め方、そして注意すべきポイントまでを徹底的に解説します。自社のシステム刷新を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談する目次
基幹システムとは何か?
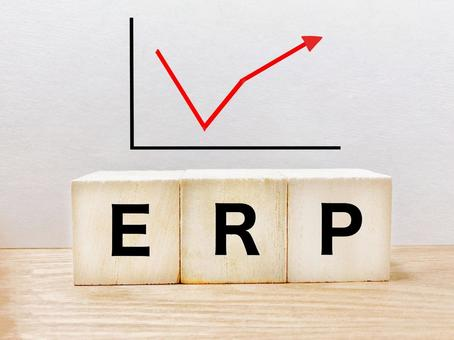
基幹システムは企業の活動を根底から支える“神経網”ともいえる存在です。財務、販売、人事など、日々の意思決定や情報伝達の中枢となり、社内外のさまざまなデータがこの仕組みを通じて流れます。
かつては一体型の大規模システムが主流でしたが、今では各社の業務特性や成長段階に応じ、複数のシステムが連動し合う形態も一般的です。たとえば、サプライチェーン全体をリアルタイムで管理したり、ECや営業チャネルの多様化へフレキシブルに対応したりなど、「つながる基盤」が企業運営に不可欠となっています。
つまり、基幹システムは“業務を効率化する道具”ではなく、“組織の変化を後押しするプラットフォーム”と捉え直す必要があるのです。
基幹システム再構築が必要となる背景を解説!

企業が基幹システムの刷新に踏み切る背景は、単なるシステム老朽化だけではありません。近年は市場環境やビジネスモデルの急激な変化、サイバーリスクへの対応要求など、外的・内的圧力が複雑に絡み合っています。
たとえば、既存システムが新たなサービスや部門横断の業務に十分対応できない、電子帳簿法やインボイス制度など法規制変更へ追随できない、といった声が多くなっています。また、レガシーシステムのブラックボックス化や属人化は、事業継続の脆弱性を高めており、これを機に全体を再設計し直す企業も増加中です。
「とりあえず継続」では将来の成長が見込めない今、基幹システムの再構築は“守り”のためだけではなく、“攻め”の戦略投資として位置付けられています。
基幹システムの再構築のタイミングはいつなのか?

システム再構築を行う最適なタイミングは、単に「古くなったから」ではなく、事業環境や社内の業務フローに変化が起きたときです。たとえば、業務のデジタル化が進む中で既存システムが新しいツールや外部サービスと連携できない、あるいはデータ活用が難しいといった課題が発生した場合が挙げられます。
基幹システムの保守費用が年々増加している場合や、システムを扱える人材が減少している場合も再構築のサインです。特に、ベンダーサポートが終了したシステムを使い続けることは、セキュリティ面で大きなリスクとなります。
事業の拡大や新規サービスの立ち上げなどでシステム要件が大きく変化した際も、再構築を検討するタイミングといえるでしょう。「業務」「コスト」「人材」「技術基盤」といった観点で不具合や制約が目立ち始めたときが、最も適切な見直し時期です。
基幹システムを再構築の進め方を順に解説!

システム再構築は段階的に進めることが成功の鍵です。ここでは、全体の流れを5つのステップに分け、それぞれのポイントを解説します。
現在の課題把握から運用・保守まで、一つひとつの工程を丁寧に進めることが、失敗を防ぐ最短ルートになります。
①現在の基幹システムの把握
再構築の第一歩は、今あるシステムの現状を正確に把握することです。長年運用してきた基幹システムは、担当者の入れ替わりや業務拡大により、仕様が不明確になっているケースも少なくありません。まずはどの部署で、どの機能を、どのように利用しているのかを洗い出し、業務フローやデータの流れを図式化します。
次に、現場担当者へのヒアリングを通して「業務が煩雑」「手作業が多い」「情報共有が遅い」などの課題を具体的に整理します。さらに、システム障害の発生履歴、保守コスト、運用体制などもチェックし、問題点を明確化しておくことが大切です。
他のシステムとの連携状況や、既存データの品質もこの段階で確認しておきましょう。特に古いシステムではデータ形式が統一されていないことが多く、再構築時の移行リスクにつながりかねません。
こうした現状を正確に把握することで、次の工程である目的設定や方式選定をスムーズに進めることができます。基幹システム再構築の成功は、この“現状把握”の精度にかかっているといっても過言ではないのです。
②何のための再構築なのかを理解する
現状分析が終わったら、次に「なぜ再構築するのか」を明確にする段階に進みます。目的があいまいなままプロジェクトを始めてしまうと、方向性が定まらず、最終的に「費用ばかりかかった」という事態になりかねません。
目的は「業務効率化」「コスト削減」「経営データの可視化」「セキュリティ強化」など、企業によって異なります。属人化をなくして全社で統一した業務プロセスを作りたい、あるいはリアルタイムにデータを分析して意思決定を早めたいなど、経営課題と直結する目的を設定することが重要です。
経営層と現場担当者、IT部門の三者で目的を共有し、再構築の意義を全員が理解している状態を作ることも欠かせません。この共有ができていないと、後の工程で「現場のニーズに合っていない」「開発が進まない」などのトラブルにつながります。
システム再構築は単なるリプレイスではなく、会社の将来を見据えた経営改革でもあります。そのため、目的を言語化し、達成すべきゴールを明確に定めておくことが成功の第一条件です。
③再構築の方法を決める
目的を明確にしたら、次は再構築の方法を選定します。方法としては、「フルスクラッチ開発」「パッケージ導入」「クラウド移行」「ハイブリッド構成」などが代表的です。
フルスクラッチ開発は、自社の業務に完全に合わせた自由な設計ができる一方、開発期間とコストが大きくなります。
パッケージ導入は導入スピードが速くコストを抑えられますが、自社の業務をシステムに合わせる必要があり、柔軟性が低いというデメリットもあります。
クラウド移行は柔軟性と拡張性が高く、初期費用を抑えつつ最新技術を取り入れられる点が魅力です。既存システムの一部を残しつつ段階的に刷新する「ハイブリッド構成」は、リスクを抑えながら新旧システムの共存を図れる方法です。
選定時は、コスト・拡張性・運用負荷・セキュリティ・将来性などの観点から総合的に判断しましょう。社内にIT知識が不足している場合は、外部の専門パートナーに相談し、長期的な視点での設計支援を受けるのも有効です。
④開発・移行をする
設計方針と方式が決まったら、いよいよ開発とデータ移行のフェーズに入ります。この段階では、プロジェクトマネジメントが特に重要です。進捗や課題を可視化し、定期的なレビューを実施することで、仕様変更や遅延を最小限に抑えることができます。
開発中は、単に機能を作るだけでなく、ユーザーが実際に業務で使いやすいかを意識した設計が求められます。操作性やレスポンス速度、エラーハンドリングの方法なども確認しましょう。
データ移行も慎重に行う必要があり、旧システムのデータを正確に新システムへ反映するために、移行前の整備、バックアップ、テストを徹底し、移行後のデータ検証も必ず実施します。
ユーザー部門によるテストや受け入れ検証を行うことで、業務上の抜けや不具合を事前に発見できます。システム開発は「作ること」よりも「使える状態にすること」がゴールであり、開発・移行段階での丁寧な確認作業が必要不可欠なのです。
⑤保守・運用をする
システムをリリースしたら、運用と保守のフェーズに入ります。新システムは導入して終わりではなく、継続的な改善と安定稼働が求められます。まず、日常運用を安定させるために、ユーザーからの問い合わせや不具合に迅速に対応できる体制を整えましょう。運用担当者の教育やマニュアル整備も欠かせません。
リリース後には、ユーザーフィードバックや業務の変化に応じて機能追加や修正を行うことも必須です。システム監視やセキュリティチェックを定期的に実施し、障害やリスクを未然に防ぐ取り組みが求められます。
基幹システム再構築はここからが本番とも言えます。初期の開発や移行だけで満足せず、運用・保守を通じて継続的に改善していく姿勢が、長期的な効果を生むポイントです。
基幹システム再構築のアプローチと選択肢のカギとは?

再構築プロジェクトは、一律の解がなく、自社の業務特性やITビジョンに合った手法を取ることが不可欠です。最初に取り組むべきは、現状の仕組みを分解し、“どこに柔軟性や拡張性が必要か”を徹底的に棚卸しすることです。
比較検討したい選択肢には次のようなものがあります。
オンプレミス vs. クラウド
オンプレミス運用は自社の管理下に置くことで高度なカスタマイズやセキュリティを実現できますが、コストや技術者確保が長期的な課題となります。
一方で、クラウド型は拠点ごとの機動的な展開や、ITインフラの運用負担軽減、災害時のレジリエンス向上が強みです。ただし、自社要件とのギャップやデータ主権の考慮が必要不可欠です。
パッケージ vs. スクラッチ開発
パッケージ型ソリューションは“業界標準”に沿った運用を迅速に立ち上げられる反面、自社特有の業務慣習や強みに100%沿うことが難しい場合があります。
これに対し、スクラッチ開発は高い柔軟性を持ちますが、仕様確定に時間と工数がかかるため、フェーズ分割やプロトタイプ開発を経て段階的に導入する実践例が主流となりつつあります。
現状維持ではなく、新たな挑戦を後押しする

基幹システム再構築の最大の狙いは、“企業の新しい可能性”を解き放つことにあります。複数部署や拠点を横断するデータ活用、変わりゆく市場や顧客接点への即応力、働く人々の生産性を最大化するための業務プロセス刷新――これらが、再構築によって実現できる新たな価値です。
今求められるのは「現状維持ではなく、新たな挑戦を後押しする設計思想」です。たとえばAIやIoTといった新技術との連携を見据え、小さな改善の積み重ねでは得られない企業変革のエンジンとして、基幹システムを再定義する時代が訪れています。
基幹システムを再構築を進める際の注意点とは?

ここまでお話ししてきたように、基幹システム再構築は単なる入れ替えではなく、業務プロセスや意思決定、組織運用に大きな影響を及ぼす経営プロジェクトです。開始前に押さえておくべき注意点を明確にしておかなければ、コスト超過やスケジュール破綻、現場混乱に発展しかねません。
具体的には「ゴールの明確化」「導入効果が出るまでの時間」「開発パートナーの選定」の三点を中心に、リスクと対応策を事前に設計しておくことが重要です。
再構築のゴールを明確にする
まず第一に、プロジェクトの「到達点」を誰が見ても分かる形で定義することが必須です。
単に「新しくする」「使いやすくする」といった曖昧な目標では、要件定義や優先順位付けがぶれてしまい、結果として不要な機能や過剰なカスタマイズにコストを割く羽目になってしまいます。
具体的には、改善対象の業務を部門別に列挙し、業務プロセスのどの手順を何%短縮するのか、どのKPI(例:月次決算日数、受注→請求のリードタイム、在庫回転率など)を何日または何%で改善するのかを数値で定めます。
また経営層、現場責任者、IT部門、外部ベンダーの四者でゴールを文書化してサインオフを取り、ゴール達成のための最小限要件(MVP)と拡張要件を明確に分けておくことで、要件変更やスコープ拡大が要求された場合でも判断基準がブレず、優先度に沿った意思決定が可能になります。
加えて、プロジェクト初期に想定されるリスク(データ移行での欠損、既存業務の停止時間、利用者の習熟遅延など)を洗い出し、それぞれの許容値と対策をゴールに紐づけておくと、途中で軌道修正が必要になった際の対応がスムーズになるでしょう。
メリットを感じるまで時間がかかる
新しい基幹システムを導入した直後は、業務フローの変更や操作方法の習熟の影響で、一時的に業務負荷が増えることが少なくありません。システム導入の効果を短期的に評価するのは難しく、中長期的な視点でメリットを確認することが大前提となります。
例えば「月次決算の短縮」を目的にする場合、導入後1ヶ月のデータではなく、3〜6ヶ月の実績で比較するなど現実的な評価期間を設ける必要があります。
加えて教育計画(トレーニング回数、OJTの担当者、Q&Aリソース)やサポート体制(初動対応のSLA、運用ヘルプデスクの稼働時間)を導入前に用意し、ユーザーが新システムに慣れるまでの運用支援を厚くすることが望ましいです。
メリットが見えるまでの遅延を説明するコミュニケーションプランも重要で、経営層や現場に対して「いつ」「どの指標で」「どの程度の改善を期待しているのか」を定期的に報告し、短期的なマイナスを乗り切るための心理的な準備をしておきましょう。
合わない開発会社がある
開発会社の選定はプロジェクト成功に直結します。自社業務への理解が浅い、提案力やサポート力が不足している、コミュニケーションが取りにくい会社を選ぶと、開発遅延や完成後の使いにくいシステムにつながる可能性があります。
採点基準としては、
- 同業界での導入実績と成功事例
- 要件定義〜運用までの一貫した支援体制(ドキュメント・テスト・移行支援)
- 初期対応力と常時サポートのSLA
- 担当チームとのコミュニケーションのしやすさ
- 追加開発や長期運用時のコスト見積りの透明性、
の5点を重視します。
これに加え、RFPやPoCで実務に近いテストを実施し、実際のデータや処理でパフォーマンスと手順を確認することも忘れないようにしましょう。契約条項では、要件未達成時のペナルティ、成果物の受け入れ基準、保守範囲の明確化を入れておくとトラブル防止になります。
相性が悪いパートナーは初期に見切りをつけ、代替策を早期に検討する判断力も必要です。結果的に、適切なベンダー選びがプロジェクトの成功率を大きく左右すると考えても良いでしょう。
基幹システム再構築の進め方がわからないならオーシャン・アンド・パートナーズへ

基幹システム再構築は、企業にとって大きな変革の機会です。それは単なるコストや業務効率化の問題ではなく、新しい価値を創造し、競争力を高める挑戦です。
「基幹システム再構築を通じて、企業が持つポテンシャルを最大限に引き出す」――この視点を持つことで、プロジェクトは確実に未来へのステップとなるでしょう。
オーシャン・アンド・パートナーズは、基幹システム再構築や業務改善に豊富な実績を持ち、業務分析、システム設計、導入、運用までワンストップでサポート。企業ごとの課題に最適なソリューションを提供します。
再構築プロジェクトの計画立案や外部パートナー選定に悩む企業様にも安心して任せていただけるよう、長期的な視点でシステムを最適化する戦略的な提案が可能です。基幹システム再構築を円滑に進め、業務効率や経営判断力を高めたいのであれば、信頼できるパートナーとしてオーシャン・アンド・パートナーズをぜひご活用ください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談するこの記事を書いた人について
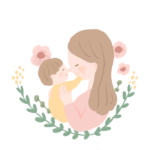
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。