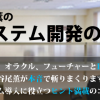システム開発の失敗事例5選!原因と対策、成功に導くパートナー選びのポイントを解説!

「システム開発案件の8割が失敗する」という実態をご存じでしょうか。
一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の「企業IT動向調査報告書2023」によれば、500人月以上のプロジェクトにおいて、想定通りの工期をが順守されたプロジェクトの割合はたった14.1%だとされています。
そもそもシステムとして完成に至らなかったケースのほか、システムとしては完成したものの業務として使えないケース、一部の業務としては使えるがデータとしてつながりが成り立っていないケースなど、ひとくちに失敗と言ってもさまざまな状況が起こりえます。
実は、うまくいかないケースにはある理由と共通点があるのです。
本記事では、よくあるシステム開発の失敗要因を5つのケースに分けて紹介しながら、それぞれの原因と対策を解説します。
さらに、開発を成功へ導くためのポイントや、信頼できる開発パートナーの選び方についても詳しく説明していきます。これからシステム開発を検討している方や、過去にトラブルを経験した方は、ぜひ最後までご覧ください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談する目次
システム開発のよくある失敗の原因5選を解説!

システム開発が失敗に終わる背景には多くの場合、「要件定義の甘さ」や「スケジュールの見誤り」といった初期段階でのミスが後を引き、後半で大きな影響を及ぼします。また、担当者間の認識違いや、技術面での判断ミスも見逃せません。
ここでは、特に発生頻度の高い5つの失敗原因についてご紹介します。実際の事例も交えつつ詳しく見ていきましょう。
①要件定義不足
システム開発で最も多い失敗が「要件定義の不足」です。例えば医療関連のシステム開発では、「既存システムとの連携仕様」や「業務フローの実態」を十分に把握しないまま開発を進めてしまい、その結果、完成後に想定していなかった不具合が発生し、追加改修と再テストが必要になりました。納期もコストも大幅に超過し、現場の運用にも混乱が生じたといいます。
もう一つの事例は、ECサイト構築プロジェクトです。要件定義の段階で「ユーザーがどのように商品を検索・購入するか」という動線を明確に設計しなかったため、完成後に「ユーザーが目的の商品を探しにくい」「カート機能が使いづらい」といった問題が多数発生しました。結果としてUIを全面的に作り直すことになり、開発期間が当初の1.5倍に延びたといいます。
これらの事例に共通するのは、「利用者視点での設計不足」と「業務理解の浅さ」です。要件定義では、現場の声や運用シナリオを丁寧に吸い上げ、業務上の課題を正確に反映させることが欠かせません。開発前に関係者が共通認識を持ち、目的と成果物のイメージを一致させることが、システム開発を成功に導く第一歩なのです。
②開発遅延
当然ながら、開発に遅延が発生すればそれは間違いなく失敗としてカウントされます。
海外の大規模空港における手荷物管理システムの開発が、典型的な失敗例として挙げられます。開発途中で複数の仕様変更が発生し、さらに各ベンダー間の調整が難航したことで、最終的に16か月の遅延が生じ、プロジェクトの遅れが空港の開業時期にも影響し、膨大な損失につながりました。
もう一つは、行政機関の情報管理システムでの事例です。当初は1年での完成を予定していましたが、途中で要件の追加や改修が繰り返され、結果的に4年もの遅延を引き起こしました。進捗管理が不十分で、開発の遅れを早期に把握できなかったことも問題を深刻化させた原因とされています。
このような開発遅延を防ぐには、スケジュール管理とリスク対策の徹底が必要です。開発開始前に明確なマイルストーンを設定し、進捗状況を定期的に可視化することで、問題を早期に発見・修正できます。また、要件変更が発生した際には影響範囲を即座に見積もり、チーム全体で再スケジュールを共有することが重要です。柔軟かつ透明性の高い管理体制が、納期遵守への鍵となります。
③技術選定ミス
システム開発では「どの技術を使うか」の判断が成功と失敗を分けます。
事例の一つに、大手メーカーの基幹システム刷新プロジェクトがあります。新技術の採用を急ぎすぎた結果、開発メンバーのスキルが追いつかず、コード品質が低下してしまいました。運用開始後にバグが多発し、結局、既存の技術基盤に戻すという二度手間となってしまったのです。
もう一つの例は、中規模企業の販売管理システム開発です。コスト削減のためにオープンソースのフレームワークを採用しましたが、対応できるエンジニアが少なく、トラブル発生時に解決まで時間がかかってしまいました。サポート体制が整っていない技術を選んだことで、保守性が著しく低下し、結果として運用コストが増加したといいます。
このような失敗を防ぐには、開発チームの技術力や運用体制に合った技術を選ぶことが大切です。採用を検討している技術についてはPoC(概念実証)を実施し、性能や安定性を確認したうえで判断するのが理想的です。将来的な拡張性やメンテナンス性を見据え、保守・サポートが受けやすい技術を選定することも、成功への重要なポイントです。
④予算オーバー
予算オーバーは、システム開発で最も現実的な失敗要因の一つです。
例えば、官公庁の大規模データベース構築プロジェクトの事例が挙げられます。当初の見積もりでリスクを十分に織り込まなかったため、追加機能やテスト工程の拡大によって費用が大幅に増加しました。最終的に総コストが当初予定の2倍以上に膨らみ、予算不足から一部機能が削減される結果になったそうです。
もう一つは、スタートアップ企業の業務支援システム開発の事例です。開発途中で新しいアイデアが次々と出され、仕様変更を繰り返したことで費用が急増しました。当初は数百万円規模だった予算が、最終的には1,000万円を超えるまで膨れ上がり、資金繰りが悪化してプロジェクトが一時中断したという事例があります。
予算オーバーを防ぐには、まず「要件の優先度付け」を明確にすることが重要です。初期段階で“必須機能”と“後から追加可能な機能”を分けることで、費用をコントロールしやすくなるでしょう。また、見積もり時には開発費だけでなく、テスト・運用・保守まで含めたトータルコストを算出することが不可欠です。進捗ごとにコストを可視化し、定期的に見直すことで、予算超過を早期に防止できます。
⑤コミュニケーション不足
システム開発では、開発チームと発注側の間に生じる「コミュニケーション不足」が深刻な失敗につながることがあります。
事例として、行政系システムの刷新プロジェクトがあります。開発ベンダーと担当部署の間に情報共有の仕組みが整っていなかったことが原因となりました。会議記録や仕様変更の履歴が共有されず、設計と実装の内容にズレが発生。最終的に納品後のシステムが現場業務に適合せず、再開発が必要になったようです。
大手金融機関の顧客管理システム開発でも、同様の失敗が起きました。発注元の要望を担当営業が正確に開発チームへ伝えられず、機能設計に齟齬が発生。完成後のテスト段階で初めてその違いが明らかになり、修正作業に多大な時間とコストがかかったといいます。
こうした事例を防ぐには、定期的なミーティングとドキュメントによる情報共有が不可欠です。進捗報告や課題管理を一元化し、誰が見ても最新情報を把握できる状態を保つことで、誤解や抜け漏れを防げます。オンラインでのやり取りが増えた今こそ、チャットツールやタスク管理システムを活用し、チーム全体で透明性の高いコミュニケーションを継続することが成功への近道です。
システム開発を失敗させないための対策とは?

システム開発の失敗を防ぐには、単にスケジュールや予算を管理するだけでは不十分です。プロジェクトの目的を明確に定め、開発全体の方向性を共有すること、早期に問題を発見して修正する体制を整えること、そして人的・時間的リソースを適切に配分し、コミュニケーションを円滑に行うことが不可欠です。
システム開発の実際の現場に基づいて、失敗を防ぐための具体的な対策を詳しく解説します。
プロジェクトの方向性を明確にする
システム開発では、まずプロジェクトの方向性を明確にすることが非常に重要です。目標や目的が曖昧だと、開発チームも発注側も進むべき方向がぶれてしまい、不要な作業や仕様変更が増える原因になります。具体的には、プロジェクト開始前に「システムで何を達成したいのか」「どの業務課題を解決したいのか」を関係者全員で共有することが欠かせません。
要件の優先度を整理し、必須機能と追加機能を明確に区別することも大切です。開発中に変更や追加が発生しても、優先度に応じて柔軟に対応でき、スケジュールや予算への影響を最小化できます。
方向性や目的を文書化し、プロジェクトチーム全員が確認できる状態を作ることで、認識のズレや誤解を防ぎ、全員が同じゴールに向かって動けるようになるのです。方向性の明確化は、開発の迷走や手戻り作業を防ぎ、効率的かつ高品質なシステム構築の基盤となるでしょう。
エラーとバグを早期発見、修正する
システム開発では、エラーやバグを早期に発見し修正する体制を整えることが非常に重要です。初期段階での小さな問題を放置すると、後工程で大規模なトラブルに発展し、修正コストや開発期間が大幅に増加する可能性があります。特に大規模プロジェクトでは、仕様変更や追加開発が重なるとバグの影響が複雑化し、修正が困難になるケースもあります。
対策としては、単体テストや結合テストを計画的に実施し、テスト結果をチーム全員で共有することが有効です。テスト自動化やバグ管理ツールの活用により、エラーの追跡や修正状況を可視化することで問題を早期に把握できるほか、定期的にコードレビューを行い、開発者間で相互チェックを実施することで、潜在的な問題を未然に防ぐことが可能です。
こうした体制を整えることで、バグや不具合による手戻り作業を最小化し、品質と納期を確保することができます。エラーの早期発見と修正は、システム開発成功のための最も基本的な対策の一つです。
リソース配分を無駄にしない
システム開発では、人的リソース・時間的リソース・物的リソースの3つを適切に管理することが成功の鍵です。これらをバランスよく配分することで、開発効率を高め、遅延やコスト超過を防ぐことができます。
- 人的リソース
- 時間的リソース
- 物的リソース
人的リソースは、プロジェクトに関わるメンバーの人数やスキル、役割分担を指すものです。適切な配置と専門性の活用により、作業効率が向上し、品質の高い成果物を生み出せるほか、チーム内の情報共有や進捗管理を徹底することで、手戻りや過重負荷を防げます。
時間的リソースは、スケジュールや各工程の作業時間を指します。現実的な納期を設定し、マイルストーンや進捗管理を行うことで、遅延のリスクを最小化できるでしょう。
物的リソースは、開発に必要なハードウェアやソフトウェア、開発環境などを指すものです。適切な設備やツールを準備することで作業効率が向上し、障害やトラブルを未然に防げるでしょう。
これらのリソースをバランス良く管理することで、無駄なリソース消費を避け、システム開発をスムーズに進行させることができます。日々の徹底した管理で、予期せぬトラブルや遅延をできるだけ防いでいきましょう。
積極的にコミュニケーションを取る
システム開発で失敗を防ぐためには、チーム内および発注側とのコミュニケーションを積極的に行うことが不可欠です。事例の中では、開発ベンダーと担当部署間で情報共有が不十分だったため、仕様や要望の認識にズレが生じ、完成後のシステムが現場の業務に適合しないという問題が発生していました。
別の事例では、開発チーム内での情報伝達が不十分だったことにより、担当者の交代時に仕様意図が正確に引き継がれず、開発の遅れと品質低下が生じていました。特に大規模プロジェクトでは、関係者が多くなるため、情報の抜け漏れや誤解が起きやすく、コミュニケーション不足は深刻なリスクとなります。
対策としては、定期的な進捗確認会議やドキュメント化、チャットツールやタスク管理システムの活用が有効です。進捗状況や課題を全員で共有することで、認識のズレを早期に発見し、すぐに修正できます。疑問点や改善案を気軽に相談できる環境を整えることも、チーム全体の協力体制を強化する上で必要不可欠です。
積極的なコミュニケーションを維持することで、情報の透明性を高め、誤解や手戻りを防ぎ、プロジェクト全体の効率と品質を向上させることができます。これは、失敗しないシステム開発における最も基本的でありながら重要な対策の一つです。
システム開発の現場で起こっていることを紹介!

システム開発の現場では、発注者と開発者の間にしばしば「認識のズレ」が生じています。多くの発注担当者は、システムが実際にどう動くのかを具体的にイメージするのが難しく、結果として「とにかく使いやすくしてほしい」「他社のような便利な機能も加えたい」といった曖昧な要望を重ねてしまう傾向があります。
しかし、あらゆる要望を詰め込むことは現実的ではなく、優先順位をつけずに開発が進むと、肝心の業務フローに合わないシステムが完成してしまうリスクが高まります。
情報システムは「目に見えない成果物」であるため、建築とは違い、出来上がりを途中で確認することが難しいのが特徴です。そのため、思い描いていた仕上がりと実際の動作が異なり、「こんなはずではなかった」という結果に陥るケースが後を絶ちません。
本来、システム開発における要望は、最初の段階で丁寧に整理し、企業の目的や課題に照らして本当に必要な機能を絞り込む必要があります。重要なのは、“言われたものを作る”のではなく、“なぜそれが必要なのか”を一緒に考えてくれる存在がいることなのです。
ギャップを乗り越えるために、相談すべき相手が備える条件とは?
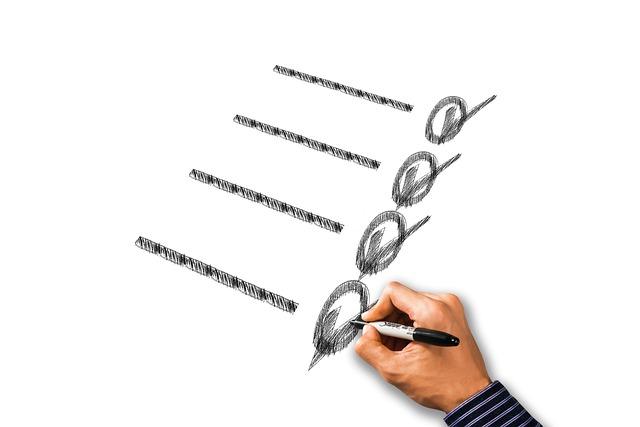
発注者と開発者の考えのギャップを埋めるには、「共に考え、真意を読み取ってくれるパートナー」を見つけることが不可欠です。単に発注内容を受け入れるベンダーではなく、対話を通じて目的を明確化してくれる存在が理想です。そのためには、相談相手に次のような資質が求められます。
まず重要なのは、理解力と洞察力のあるパートナーです。発注者の言葉の裏にある意図を読み取り、業務の背景から真の課題を把握できる力を持っている必要があります。あなたの組織の動きや文化まで掘り下げ、表面的な要望ではなく「何を実現したいのか」を引き出してくれる存在です。
次に、情報収集力と関係構築力です。プロジェクトを円滑に進めるためには、依頼者本人だけでなく、他部署の実務担当者や意思決定者とも関係を築き、全体の業務構造を把握できる体制が欠かせません。パートナーが社内に入り込み、現場の声を可視化する役割を果たせば、組織全体の合意形成をスムーズに進められます。
さらに欠かせないのが、質問力です。良いパートナーは指示を待つのではなく、疑問点を投げかけ、本質を探る会話をリードします。発注者が考えを言葉にする過程で、自らの整理が進み、潜在的なニーズが見えてくることも多いものです。質問を通して思考を引き出し、共に最適解を導けるパートナーこそ、信頼すべき相談相手と言えるでしょう。
優れた開発パートナーは、“使えるシステム”を作るだけでなく、発注者の思考を整理し、プロジェクトの方向性を一緒に形づくる伴走者です。そのような協働関係を築くことこそ、システム開発成功の第一歩です。
システム開発に失敗したくないならオーシャン・アンド・パートナーズへ

本来システム開発というのは、合理化や省力化のみを達成するものではなく、新しい価値を生み出すものです。組織をどうしたいから、どんなシステムをつくって、実際に何をやるのか。良いパートナーと巡りあわせて、あなたの意思が明確にできれば、システム開発は成功します。
あなたの組織が、ユーザの喜びの声に包まれ、健やかに売上を伸ばす。そのような状態が実現することでしょう。そしてリーダーであるあなたには、拍手と賞賛という見返りがあることでしょう。
オーシャン・アンド・パートナーズでは、企業のシステム戦略に関する総合的な支援を実施しています。基幹システムの再構築や業務プロセスのデジタル化、ITベンダー選定支援など、企業の課題に応じた最適なソリューションを提供しています。
「お客様が本当に実現したいこと」を起点に、組織・業務・仕組み・テクノロジーを横断的に捉え、計画から導入、運用後の改善まで一貫して伴走。柔軟な技術選定と設計手法により、業務効率化と事業成長を両立できる体制を構築します。ぜひ公式サイトより詳細をご覧ください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談するこの記事を書いた人について
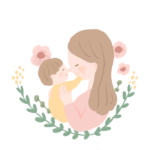
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。