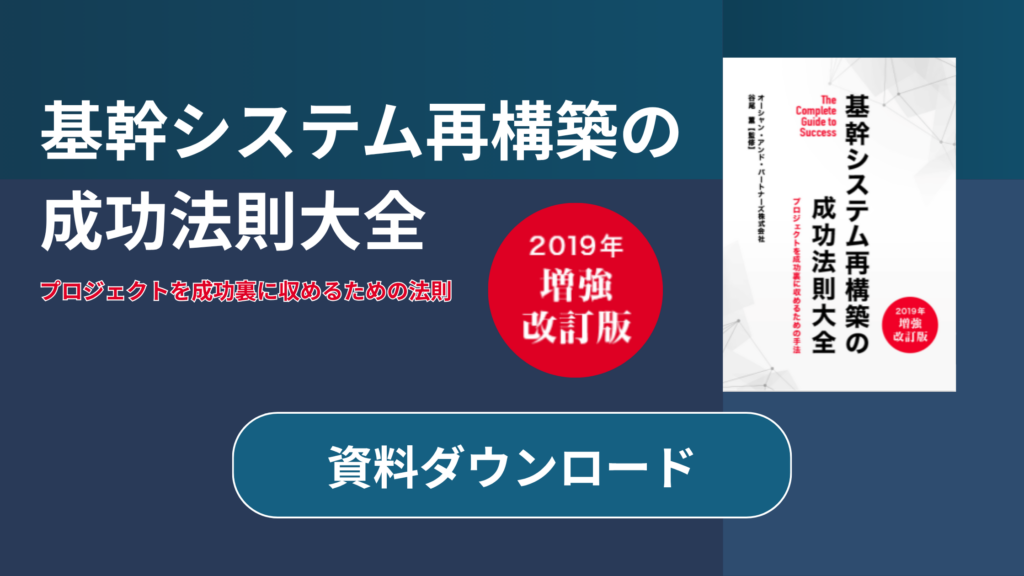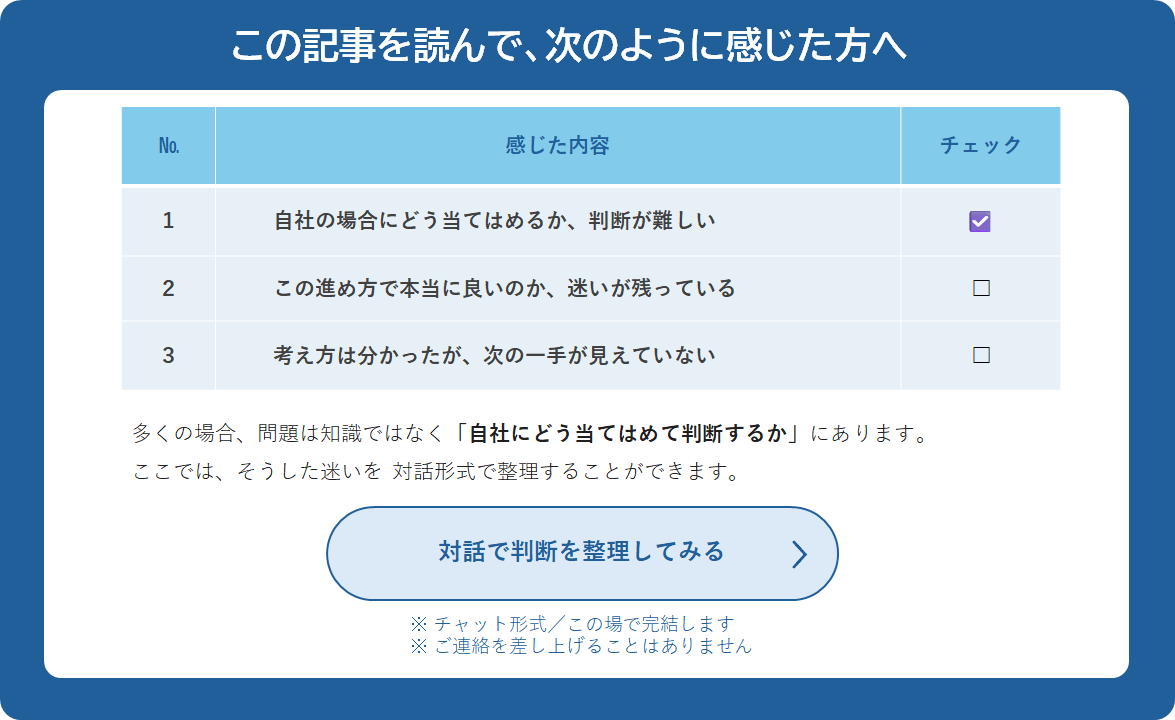システム内製化の失敗原因とは?陥りやすい9つのパターンと成功事例を徹底解説!

デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の波が企業を覆う中、システム開発を外部ベンダーに依存せず自社で行う「システム内製化」への関心が高まっています。外注コストの削減、スピーディな開発サイクル、自社ノウハウの蓄積など、内製化には多くのメリットが期待できます。
しかし、実際には計画通りに進まず、想定以上の時間と費用を浪費し、最終的にプロジェクトが頓挫してしまうケースも少なくありません。「やらない方がマシだった」という結末を迎えないために、失敗の原因を事前に知っておくことは極めて重要です。
本記事では、システム内製化が失敗する根本的な理由と、陥りやすい9つの典型的なパターンを詳しく解説します。さらに、実際に内製化に成功した企業の事例も紹介し、成功へのヒントをお届けします。
システム内製化が失敗する理由とは?

システム内製化を検討する企業が増えている背景には、外部委託によるコストと柔軟性の課題があります。しかし、内製化への移行は思った以上に困難を伴います。プロジェクトを開始したものの、期待した成果が得られず途中で挫折してしまう企業が後を絶ちませんが、なぜこのような事態が起きるのでしょうか。
ここでは、システム内製化が失敗に至る代表的な4つの理由を掘り下げて解説します。
コスト削減以外が見えていない
システム内製化を検討する多くの企業が真っ先に挙げる理由が「外注コストの削減」です。確かに、外部ベンダーへの継続的な支払いを削減できれば、長期的には大きなコスト削減効果が期待できるでしょう。しかし、コスト削減だけを目的にプロジェクトを進めると、内製化の本質的な価値を見失ってしまいかねません。
内製化には初期投資として、開発環境の構築費用、エンジニアの採用や育成コスト、既存システムからの移行費用など、相当な支出が必要です。これらの費用を考慮せずに表面的なコスト削減効果だけを追い求めると、予算が不足したり、十分なリソースを確保できなかったりして、プロジェクトが立ち行かなくなります。
ある企業では、年間数千万円の外注費を削減する目的でCRMシステムの内製化に着手しましたが、開発体制の構築や人材育成に想定外の費用がかかり、結局は外注時よりも高コストになってしまったケースがありました。
経営層がコスト削減以外のメリットを理解していないと、プロジェクトへの十分な予算配分や継続的な支援が得られず、開発チームが孤立して士気が低下し、優秀な人材が離職するという悪循環に陥ります。内製化を成功させるには、コスト削減だけでなく、事業成長への貢献やノウハウ蓄積といった中長期的な視点を持つことが不可欠です。
内製化すべき部分を決めていない
「すべてのシステムを内製化すればうまくいく」という漠然とした方針のまま進めてしまうのは、失敗への近道です。企業が扱うシステムは、基幹システムから周辺ツール、顧客向けアプリケーションまで多岐にわたります。これらすべてを一度に内製化しようとすると、リソースが分散し、優先順位が不明確になり、結果としてどれも中途半端に終わってしまう危険性が高まります。
内製化すべき領域と外部に委託すべき領域を明確に線引きすることが、プロジェクト成功の第一歩です。頻繁に仕様変更が発生し、迅速な対応が求められるシステムや、自社の競争優位性に直結するシステムは内製化に適していますが、給与計算や会計といった標準化されたパッケージシステムが豊富に存在する領域や、高度な専門知識が必要で自社にノウハウがない領域は外部に委託した方が効率的でしょう。
内製化する範囲を慎重に選定し、段階的に進めることがリスクを最小化するための重要な戦略となります。自社の業務特性やリソース状況を冷静に分析し、何を内製化すべきか明確な判断基準を持つことが成功への鍵です。
エンジニアに情報共有をさせていない
システム内製化においては、開発チーム内での知識共有と情報の透明性が極めて重要です。しかし、多くの企業で見落とされがちなのが、エンジニア間での適切な情報共有の仕組みです。特定のエンジニアだけが重要な情報や技術的知見を保持している状態、いわゆる「属人化」が進むと、その人物が退職したり異動したりした際に、プロジェクト全体が停滞してしまうリスクがあります。
情報共有が不足する原因としては、ドキュメント整備を軽視する文化、個人のタスクに追われて共有の時間が取れない状況、あるいは情報を共有するための適切なツールやプラットフォームが整備されていないことが挙げられます。特に、通常業務と並行して内製化プロジェクトを進める体制では、メンバーが日々の業務に忙殺され、ドキュメント作成やナレッジ共有が後回しになりがちです。
定期的なコードレビューや技術勉強会の開催、設計書やマニュアルの整備、チャットツールやドキュメント管理システムを活用した情報の一元管理など、組織的な情報共有の仕組みを構築することが不可欠です。情報がオープンに流通する文化を育てることで、チーム全体の技術力が底上げされ、プロジェクトの継続性と安定性が確保されるでしょう。
元の委託先からの引き継ぎが不十分
外部ベンダーに委託していたシステムを内製化する場合、最も重要なプロセスの一つが「引き継ぎ」です。しかし、この引き継ぎが不十分であることが原因で、内製化後にシステムの仕様が分からず、トラブル対応ができない、改修が進まないといった問題が頻発します。
外部ベンダーとの契約終了時には、システムのソースコード、設計書、運用マニュアル、過去のトラブル対応履歴など、あらゆる情報の提供を受ける必要がありますが、契約の終了を急いだり、ベンダー側が情報開示に消極的だったりすると、十分なドキュメントや知識が移転されないまま内製化がスタートしてしまうのです。
その結果、システムの内部構造が不明瞭なままとなり、障害が発生した際の原因究明に時間がかかったり、機能追加の際に既存コードとの整合性が取れなかったりする事態が生じます。
契約段階から引き継ぎ事項を明確にし、十分な引き継ぎ期間を確保すること、そして元の委託先との良好な関係を維持し、協力的な引き継ぎを実現することが求められます。可能であれば、移行期間中は元ベンダーのエンジニアにアドバイザーとして残ってもらい、自社チームへの知識移転をサポートしてもらうのも効果的な方法です。
システムの内製化で失敗に陥りやすいパターンを紹介!

システム内製化には様々な落とし穴が存在します。多くの企業が同じような失敗を繰り返しており、その失敗パターンには明確な共通点があります。事前にこれらの典型的な失敗パターンを知っておくことで、自社のプロジェクトにおいて同じ轍を踏むリスクを大幅に減らせるのです。
ここでは、内製化プロジェクトで特に陥りやすい9つの具体的な失敗パターンを紹介します。それぞれのパターンについて、なぜ失敗に至るのか、どのような状況で発生しやすいのかまでも詳しく解説します。
①コミュニケーションが不十分
システム内製化プロジェクトにおいて、最も頻繁に指摘される失敗要因の一つが「コミュニケーション不足」です。開発チーム内、あるいはチームと経営層や他部署との間で適切な情報共有が行われないと、プロジェクトの目標や期待値にズレが生じ、結果として誰も望んでいないシステムが出来上がってしまうリスクがあります。
具体的には、プロジェクトの開始時に関係者全員が集まって目標を明確に共有する場が設けられていなかったり、開発の進捗状況が定期的に報告されず、問題が発覚したときには既に手遅れになっていたりするケースが該当します。
技術者と非技術者の間で専門用語や前提知識のギャップがあるにもかかわらず、それを埋める努力がなされないと、要件の認識齟齬が発生します。営業部門が「顧客情報を簡単に検索できる機能」を求めていても、開発チームがその「簡単」の定義を正確に理解していなければ、期待とは異なる機能が実装されてしまうといったものです。
コミュニケーション不足を防ぐためには、定期的な進捗報告会の開催、誰もがアクセスできるプロジェクト管理ツールの導入、技術的な内容を分かりやすく説明する工夫などが有効です。また、開発初期段階でプロトタイプを作成し、関係者からフィードバックを得ることで、認識のズレを早期に発見・修正することができるでしょう。
②柔軟性に欠けている
ビジネス環境は常に変化しており、システム開発の途中で要件が変わることは珍しくありません。しかし、一度決めた計画に固執し、変化に対応できない硬直的なプロジェクト運営は、内製化を失敗に導きかねません。
初期段階で完璧な要件定義をしようとするあまり、要件定義に膨大な時間をかけ、実際の開発がなかなか始まらないケースがあります。開発が始まった後に市場環境の変化や経営方針の転換によって新たな要件が追加される場合でも、「計画になかった」という理由でそれを拒否してしまうと、完成したシステムがビジネスの実態に合わなくなってしまうのです。
アジャイル開発手法のように、短いサイクルで機能をリリースし、フィードバックを受けながら改善を重ねるアプローチが有効であるほか、要件の優先順位を明確にし、変化があった場合にどの要件を調整できるかをあらかじめ検討しておくことも重要です。
③内製化の目的を見失う
内製化すること自体が目的化してしまい、本来達成すべきビジネス上の目標を忘れてしまうパターンです。「DX推進の一環だから」「経営層からの指示だから」といった漠然とした理由だけでプロジェクトを開始すると、途中で方向性を見失い、何のためにシステムを作っているのか分からなくなります。
「業務効率を20%向上させる」「顧客満足度を向上させる」「年間コストを1000万円削減する」といった具体的で測定可能な目標が設定されていないと、完成したシステムの効果を評価することもできません。目的が不明確だと、開発の優先順位が決められず、機能の取捨選択ができなくなります。
内製化の目的を見失わないためには、プロジェクト開始時に具体的な目標を設定し、それを文書化して全メンバーで共有することが不可欠です。また、定期的に目標を振り返り、現在の開発内容がその目標達成に本当に貢献しているかを確認する機会を設けることも不可欠です。
④難易度の高い部分から始める
内製化の経験が浅い段階で、いきなり難易度の高いシステムや複雑な機能から着手してしまうのは、失敗の典型的なパターンです。技術的な挑戦は重要ですが、チームが十分な経験を積んでいない状態で高難度のプロジェクトに取り組むと、予想以上に時間がかかり、品質も担保できず、メンバーの疲弊とモチベーション低下を招きます。
初めての内製化プロジェクトで基幹システムの全面刷新に挑戦したり、最新の技術スタックを試したりするのは、リスクが高すぎます。まずは比較的シンプルで、失敗しても事業への影響が小さい領域から始め、成功体験を積み重ねることがポイントです。
ある金融機関では、内製化の第一歩として、顧客向けの複雑な投資シミュレーションシステムの開発に着手しました。しかし、チームメンバーは金融商品の知識も開発経験も不足しており、プロジェクトは大幅に遅延し、結局外部ベンダーに救援を依頼する事態になりました。スモールスタートの原則を守り、段階的にスキルを高めていくことが、内製化を成功に導く賢明な戦略と言えるでしょう。
⑤人材のレベルが見合っていない
システム内製化には、一定レベル以上の技術力を持つエンジニアが不可欠です。しかし、必要なスキルや経験を持たない人材だけでプロジェクトを進めようとすると、開発が滞ったり、品質の低いシステムが出来上がったりするリスクが高まります。
多くの企業では、既存の社員の中から「ITに詳しそうな人」を集めてプロジェクトチームを編成しがちですが、システム開発の経験がない、あるいは古い技術しか知らない人材だけでは、現代的なシステムを構築することは困難です。
エンジニアのスキルレベルがプロジェクトの要求レベルに達していない場合、学習しながら開発を進めることになり、予定よりも大幅に時間がかかります。技術的な判断ミスによってセキュリティホールが生まれたり、保守性の低いコードが量産されたりする危険性もあるでしょう。
人材不足を解決するには、外部から経験豊富なエンジニアを採用する、あるいは社内人材に対して計画的な研修や実践的なトレーニングを提供することが必要です。すべてを自社だけで完結させようとせず、難易度の高い部分については経験豊富な外部パートナーの支援を受けながら、徐々に自社の技術力を高めていくハイブリッドな方法も一つの手段です。
⑥ベンダー任せになる
内製化を決めたにもかかわらず、実際の開発の多くを外部ベンダーに依存してしまい、結局は従来の外注体制とほとんど変わらない状態になってしまうパターンです。これは、自社にノウハウが蓄積されず、内製化の本来の目的を達成できない典型的な失敗です。
内製化の初期段階では、外部の専門家の支援を受けることは有効ですが、その支援を受けている間に自社のエンジニアが技術を学び取り、徐々に自立していくプロセスも大切になります。しかし、ベンダーに丸投げしてしまい、自社のエンジニアが受け身の姿勢のままでは、プロジェクトが終わっても何も残りません。
ベンダー任せを避けるためには、外部支援を受ける際も自社エンジニアを主体的に関与させ、ペアプログラミングやコードレビューを通じて技術移転を図るようにしましょう。また、契約時にナレッジ移転やトレーニングを明確に盛り込み、ベンダーに技術移転の責任を持たせることも効果的です。
⑦属人化している
特定の個人だけがシステムの詳細を理解しており、その人がいないと開発も保守も進まない状態を「属人化」と呼びます。属人化が進むと、その人物が退職や異動、病欠などでプロジェクトから離れた際に、業務が完全にストップしてしまうなど重大なリスクが発生しかねません。
属人化は、情報共有の仕組みが整っていない、ドキュメント作成が軽視されている、あるいは特定のエンジニアが自分の地位を守るために意図的に情報を囲い込むといった要因で発生します。また、緊急時に対応できる人がその人しかいないという状況は、その人に過度な負担をかけ、燃え尽き症候群やストレスによる離職を招きます。
属人化を防ぐためには、複数人でのコードレビュー、ペアプログラミング、ローテーション制の導入、詳細なドキュメント作成などが有効です。また、経営層も属人化のリスクを理解し、特定の人物への過度な依存を避けるようチーム体制を整える必要があります。
⑧経営層に理解されていない
システム内製化は開発チームだけで完結するものではなく、全社的な取り組みとして経営層のコミットメントが不可欠です。しかし、経営層がシステム内製化の意義や必要性を十分に理解していないと、適切な予算配分や人員確保ができず、プロジェクトは早々に行き詰まります。
経営層の理解不足は、「内製化すればコストが下がるはず」「エンジニアを雇えばすぐにできるだろう」といった楽観的な思い込みとして現れることが多く、現実の困難や必要なリソースが過小評価されます。その結果、プロジェクトが予算オーバーや期間延長を申請しても承認されず、開発チームは制約の中で無理を強いられ、品質が犠牲になったり、メンバーの疲弊にもつながるでしょう。
経営層の理解を得るためには、技術的な詳細だけでなく、ビジネス上のメリットや投資対効果を分かりやすく説明することが重要です。また、定期的に経営層への報告会を開催し、進捗や課題を共有することで、継続的な支援を引き出すことができます。
⑨内製化後の体制がない
システムは作って終わりではありません。運用開始後も、バグ修正、機能追加、セキュリティ対応など、継続的なメンテナンスが必要です。しかし、内製化後の運用保守体制を考えずにプロジェクトを進めてしまうと、システムが完成した途端に誰も面倒を見なくなり、放置されてしまいます。
多くの企業では、プロジェクト期間中は専任チームを組んで開発に注力しますが、リリース後はメンバーが元の部署に戻ったり、新しいプロジェクトに移ったりして、運用担当者が不在になるケースがあります。運用担当者が配置されたとしても、開発経験のない人材が担当すると、軽微な修正すらできず、結局は外部ベンダーに依頼する羽目になってしまうでしょう。
内製化後の体制を整えるには、プロジェクト計画の段階から運用フェーズを見据え、運用担当者の選定、マニュアルの整備、運用ルールの策定などを行うことが重要です。また、運用担当者が開発チームと密に連携できる体制を作り、必要に応じて迅速に改修できる仕組みを整えることで、システムを長期的に活用し続けることができます。
システムの内製化に成功した事例とは?

ここまで内製化の失敗パターンを詳しく見てきましたが、一方で適切な戦略と体制のもとでシステム内製化を成功させている企業も数多く存在します。成功事例から学ぶことは、失敗パターンを知ることと同じくらい重要です。
ここでは、オーシャン・アンド・パートナーズ社が支援した3つの具体的な成功事例を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
信用保証情報を扱う基幹システムの刷新
国土交通省の指定保証機関として、分譲マンションの手付金保証事業においてシェア50%超を誇る企業のケースです。
この企業は、2011年にオフィスコンピュータから刷新したシステムを利用していましたが、柔軟性に欠けており、市場の変化や顧客ニーズへの対応が遅れるという課題を抱えていました。ビジネス環境が急速に変化する中で、競争力を維持するためには、より柔軟で拡張性の高いシステムが必要不可欠でした。
このプロジェクトにおけるミッションは、現状調査と課題の明確化を通じて「理想的かつ実現可能なシステムの姿」を定義すること、そして同社に最適な技術やサービスを選定し、システムアーキテクチャを策定すること、さらには新システムを組織に定着させることでした。
そこで、既存業務および現行システムの徹底的な調査から着手し、要件定義、システムアーキテクチャ設計、クラウド構成設計、RFP作成、ベンダ選定、そして開発工程のマネジメントまで、プロジェクト全体を包括的にサポート。
特筆すべきアプローチとして、顧客企業のチームメンバーとのブレインストーミングを徹底的に重視し、経営層へのプレゼンテーションも積極的に実施しました。技術を分かりやすく説明することでブラックボックスを排除し、経営層の理解とコミットメントを引き出すことに成功したのです。
その結果、業務の流れと情報の入出力および遷移構造の親和性が向上し、生産性が大幅に高まっただけでなく、取引先となるディベロッパーや販売会社向けのサービスも提供できるようになり、さらなるシェア拡大のきっかけとなりました。
システムの柔軟性と適切なセキュリティを確保しながら、コストを削減することにも成功し、内製化の理想的な成果を達成したのです。
>詳しい事例内容についてはこちら
信用保証情報を扱う基幹システムの刷新
金融機関向け教育サービス、基幹システム刷新
金融機関向けに図書・刊行誌の出版、通信講座、セミナー、銀行業務検定試験などの事業を営む企業の事例です。この企業では、システムの老朽化に伴い、時代の流れと顧客のニーズに対応できなくなってきたという課題がありました。従来のシステムでは情報を集約する機能がなく、ユーザー利便性が低いことも問題でした。
このプロジェクトのミッションは、上記のサービスを司る基幹業務を全面的にリニューアルすること、そしてテキストや書籍を送付する外部企業のシステムとのデータ連携を効率的に実現させることでした。支援会社としての役割は、既存業務および現行システムの調査、要件定義、システムアーキテクチャ設計、クラウド構成設計、システム設計開発、そしてWebデザインまで、幅広い範囲に及びました。
アプローチの核心は、顧客企業の組織や業務習慣を徹底的に理解することにありました。取引先や利用者のニーズを的確に把握し、企業戦略と一致するように全体をデザインすることで、単なるシステム刷新ではなく、ビジネス変革を実現しました。
オンプレミス環境からクラウドに移行することで、柔軟性を確保しながら維持コストを下げることにも成功しています。
プロジェクトの成果として、新システムを組織にフィットする形で導入することに成功し、取引先やユーザーへのサービスレベルが向上したことで収益にも直結しました。システムの柔軟性と適切なセキュリティを確保しながらコストを削減できたことも大きな成果です。
>詳しい事例内容についてはこちら
金融機関向け教育サービス、基幹システム刷新
コールセンターCTI/CRMシステム構築
保険相談や生活情報比較サービスを営む企業において、コールセンター業務による消費者とのコミュニケーションを創造的にしたいというニーズから始まったプロジェクトです。この企業は全国300店舗を展開し、コールセンターを大阪、北海道、タイで運営しており、大規模なオペレーションを効率的に管理するシステムが求められていました。
プロジェクトのミッションは、アウトバウンド、インバウンド、センター現場管理、成約管理という全体の仕組みを設計すること、オペレーター側画面の情報レイアウトを最適に設計すること、そしてサイトデザインやプログラムまで一貫して提供することでした。そこで、サービス設計、オープンソース調査、システムアーキテクチャ設計、システム設計開発、Webデザインという幅広い役割を担いました。
このプロジェクトの最大の特徴は、オープンソースのIP-PBXを活用したことです。具体的には、ソフトウェアIP-PBXとしてAsteriskを採用し、Asteriskを徹底的に調査して最大限かつ効率的に活かすように実装しました。従来、企業向けの構内電話交換機能は高価なPBX機器でしか実現できませんでしたが、この事例では安価なPCサーバーで同等の機能を実現することに成功したのです。
この事例が示すのは、必ずしも高額な商用製品を選ぶ必要はなく、オープンソースソフトウェアを適切に選定し、深く理解して活用することで、コストパフォーマンスの高いシステムを構築できるということです。技術選定においては流行や既成概念にとらわれず、顧客のニーズと予算に最適な解を追求する姿勢が重要であることが分かる事例でもあるでしょう。
>詳しい事例内容についてはこちら
コールセンターCTI/CRMシステム構築
ここから先は、自社の状況に当てはめて考えてみてください
この記事を書いた人について
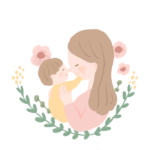
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。