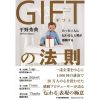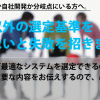DXの内製化は自社でできる?進め方から課題・成功事例まで徹底ガイド

DXの推進は今や企業の競争力を左右する重要な要素となっています。特に外部に頼り過ぎず、自社でDXを内製化する動きが急速に拡大しています。自社内でDXを進めることで、市場の変化に素早く対応できるようになり、コストの削減も期待できます。
また、業務の改善や新しいサービスの開発を自分たちのペースで加速させられるのも大きな魅力です。
この記事では、経営者や情報システム部門の責任者、そして現場でDX推進に取り組む方々に向けて、内製化の意義から具体的な取り組み方、発生しやすい課題、そして成功事例までをわかりやすく解説していきます。
これから内製化を目指す方にとって役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談する目次
なぜDXを内製化するのが重要なのかを解説!

DXを内製化することは、単にシステムを作るだけでなく、企業文化や組織体制の変革、そして社員のスキル向上にもつながります。
デジタル化は一過性の取り組みではなく、常に変化に対応し続ける必要があります。だからこそ、内製化によって自社の柔軟性と迅速な対応力を高めることが欠かせません。
まずはDXの内製化が重要な理由について、詳しく解説していきます。
企業文化を変化させるため
DXの内製化は、単なる技術導入にとどまらず、企業文化や働き方に大きな変革をもたらします。
社員がデジタル技術を積極的に使いこなすようになると、仕事に対する意識や取り組みが深まり、自発的に課題を見つけて改善策を考える姿勢が育ちます。こうした環境では、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する風土が形成され、組織全体の柔軟性や創造力が向上します。
また、部門間の情報共有や協力が進むことで、一体感のあるチームワークが生まれやすく、業務の効率化や意思決定の迅速化にもつながります。
こうした文化の変化は、企業が市場の変動に素早く対応し、持続的に成長するための強力な土台となります。DXの本質は技術だけでなく、「人と組織、企業文化」の変革にこそあると言えるでしょう。
市場の変化に対応するため
現代のビジネス環境は刻々と変化し、顧客のニーズも多様化しています。これにスピーディーに対応することが企業の生き残りに欠かせません。
しかし、外部に委託してシステム開発や運用を行う場合、変更のたびに時間がかかるため、ビジネスのスピードに追いつけないリスクが高まってしまいます。
一方、DXを内製化すれば、自社の状況やニーズに即した柔軟な対応が可能になります。市場の動向に合わせてシステムの改修や新機能の追加を速やかに行えるため、競合他社に先んじることができます。
DXの内製化は、変化に強い組織づくりを可能にし、企業競争力の維持・強化に直結する重要な戦略なのです。
社内のDXリテラシーの向上させる
DXの内製化が勧められる理由には、社員一人ひとりのデジタルスキルや知識の取得による組織全体のDXリテラシーの向上もあります。社員は自分の仕事の課題を把握し、適切なデジタルツールや手法を自ら選び実践できるようになるのです。
DXリテラシーが高まれば、ムダや非効率な業務の見直しや改善を迅速に行えるようになり、業務の効率化やコスト削減を叶えることができます。
また、ITに関する知識が社員間で共有されることで、部署や役職を超えた円滑なコミュニケーションや協力が実現し、組織としての意思決定もスピーディになるでしょう。
このように、DXリテラシー向上は、単なるスキルアップにとどまらず、組織文化の底上げや競争力強化に直結します。社員が主体的にデジタル技術を使いこなせる環境を作ることが、持続的なDX推進と企業の未来を切り拓くための重要なポイントとなるのです。
DXを内製化するメリットとは?

DXの内製化は、企業にメンテナンスを現場で迅速に行えるようになったり、コスト削減ができたりといったメリットをもたらします。また、知識やノウハウの蓄積によって外部への依存が減り対応のスピードが大幅に向上するため、長期的に見てプラスになることが多いのです。
こういったDX内製化のメリットや強みについて、ここで詳しく見ていきましょう。
メンテナンスを現場で行える
DXの内製化が進むと、システムを日々使っている現場担当者が不具合の対応や改善要望に迅速に対応できるようになります。
外部ベンダーに依頼する場合は、契約内容の確認や調整、納期調整など複雑な手続きが必要で、即時の対応が難しいケースが多いです。これに対し、内製化していれば、小さな修正や調整も即座に実施できるため、業務への影響を最小限に抑えることが可能です。
現場で対応できるということは、実態を最もよく把握している担当者が直接システムを改良するということになります。そのため、より業務に即した使いやすいシステムへと進化しやすくなるのです。
このように、DXの内製化はスピーディで柔軟なメンテナンスを可能とし、ビジネスの変化や現場ニーズに素早く対応できる強みを持っているのです。
コストが削減できる
DXを外部に委託すると、開発費や保守費用が継続的にかかり、年間で大きなコスト負担になることがあります。特に、プロジェクトごとに発生する調整や交渉の手間もコストとして積み重なります。一方で、DXを内製化すれば、一度体制が整うことで長期的に費用を大幅に抑えることが可能です。
また、DXの内製化により開発のスピードが上がることも重要です。スピーディーな業務改善や新サービス開発ができるようになるため、コスト効率も向上させることができるのです。さらに、DXの内製化はシステムの変更やトラブル対応も迅速にできるようになるため、業務停止や遅延のリスクを減らせる点も経済的なメリットと言えます。
これらの要素が組み合わさることで、内製化は単なる費用削減にとどまらず、企業の競争力強化にも貢献する重要な戦略となるのです。
知識や技術が蓄積される
DXを内製化する最大のメリットの一つは、システムに関わる知識や技術が社内に蓄積されることです。外部委託に頼ると、技術やノウハウは外部ベンダーに留まりやすく、自社内では十分に蓄積されません。そのため、継続的な改善や新しいプロジェクトへの応用が難しくなります。
一方、DXを内製化していれば、社員が設計や開発、運用のプロセスに深く関わるため、業務知識とITスキルの両方が着実に向上します。こうした知識の蓄積は、自社の独自課題を的確に理解し、柔軟かつ迅速に解決できる技術者の増加につながり、DX推進のスピードアップに直結します。
また、蓄積したノウハウは他の部門や新たなプロジェクトに共有・展開しやすくなるのもポイントです。これにより、組織全体の技術力と競争力を底上げすることができるでしょう。技術者の育成や社内教育も進むため、離職リスクを低減することにも役立ちます。
初期の人材育成や環境整備には投資が必要ですが、長期的に見ればDXの内製化は外注費用や手間を減らして、効率的な運用と持続可能な成長をするための強力な武器となるのです。
DXを内製化するための進め方を徹底解説!

上記のように多くのメリットがあるDXの内製化ですが、一方で企業にとって大きな変革を伴うプロジェクトともいえます。
ここではどのようにDXの内製化を進めていけば良いのか、ステップごとにまとめて解説していきます。組織全体の理解や協力を得ながら計画的に進めていきましょう。
社内で内製化の合意を得る
まず最初に欠かせないのは、経営層から現場まで幅広く内製化の意義と目的を共有し、社内での合意形成を図ることです。DXの内製化は既存の業務フローや働き方に変化をもたらすため、抵抗感が生じやすい傾向にあります。
こうした不安や懸念を減らすには、成し遂げたいビジョンや内製化によるメリットをわかりやすく伝えることが重要です。経営層が率先してメッセージを発信し、理解促進のための説明会やワークショップ開催、意見交換の場を設けることが有効です。内製化推進チームを結成するのも効果的です。各部署の代表を巻き込みながら組織全体で取り組む体制を整えていきましょう。
現在外注している内容の把握
DXの内製化を進める前の準備段階で最も重要なのは、現在どの業務やシステム開発を外部に委託しているのかを正確に把握することです。この把握は、全体的なコストや作業工程の見える化につながり、どこに無駄や改善ポイントがあるかを明確にします。
具体的には、各アウトソーシング先が担当している業務範囲や委託費用、契約条件などを詳しく調査します。その上で、どの部分を社内に取り込み内製化できるかを検討することで、最も効果的な内製化計画を立てられます。
また、業務フローやシステム全体の現状をリストアップし、重複や非効率な部分を洗い出すためにフローチャートやプロセスマップを作成することも有効です。これによって、優先順位をつけて内製化を段階的に実施し、効率的にDXを進める土台が整います。
現場担当者へのヒアリングなどを通じて実務上の課題やニーズを取り込むことで、経営層だけでなく現場の理解と協力も得やすくなるでしょう。
内製化の目的を明確化する
DXの内製化を成功させるためには、まず社内で目的と目標をはっきりさせることが欠かせません。目的は単に「外注費の削減」だけでなく、「特定業務の迅速な改善」「顧客体験の向上」「業務効率化」など、多面的な視点で設定することが重要です。明確な目的があれば、関係者全員が同じ方向に向かって取り組みやすくなります。
さらに、目的に基づいてどの業務を内製化するのか、その対象範囲を定めることで、必要なリソースやスケジュールも具体的に決めやすくなります。こうした計画的な設定は、無理のない現実的な内製化の進行を可能にし、成功の確率を高めます。目的や目標を共有し、進捗や成果を定期的に確認すれば、関係者間のコミュニケーションや協力関係も強化され、プロジェクトを円滑に推進できるでしょう。
設計書を作成する
DXの内製化の実作業に進む前に、システムや業務プロセスの設計書を詳細に作成することが非常に重要です。設計書はシステムの構成や機能要件を明文化したもので、内製担当者が自分の役割や作業内容を正確に理解し、効率的に進めるための基本資料となります。
適切に作成された設計書は、開発中の仕様変更やトラブル発生時にも迅速かつ正確に対応するための指針となり、開発の効率化と品質向上に大きく貢献します。また、設計書を作成する過程で関係者間の共通理解が深まり、認識のズレを減らすことで、後の開発工程でのミスや手戻りを防ぐことも可能です。
さらに、わかりやすく体系的にまとめられた設計書は、新たに参加するメンバーへの引き継ぎにも役立ち、チーム全体の開発力を底上げします。しっかりとした設計書は内製化プロジェクトの成功に不可欠な土台となるのです。
開発環境を構築する
DXの内製化をスムーズに進めるためには、適切な開発環境の構築が欠かせません。これには単に開発ツールやサーバー、ネットワークの整備だけでなく、テスト環境やバージョン管理システムの導入も含まれます。こうした環境が整備されていることで、開発作業の効率化はもちろん、品質の安定化も実現できます。
また、開発チーム内での情報共有やコミュニケーションを円滑にするための仕組みも重要です。プロジェクト管理ツールやチャットツールを活用することで、進捗状況や課題をリアルタイムに把握し、迅速な意思決定が可能になります。
近年ではノーコード・ローコード開発環境の導入も内製化を後押ししています。これにより、IT専門家以外の現場社員も簡単にシステム開発に参加でき、組織全体のデジタル活用力を向上させることができるでしょう。
段階的に外注を減らす
すべての業務やシステムを一度に内製化しようとすると、大きなリスクや混乱が生じる可能性があります。そのため、まずは影響範囲が小さくリスクの少ないプロジェクトや機能から内製化を始める「スモールスタート」のアプローチが効果的です。
この段階的な取り組みで小さな成功体験を積み重ねることが重要です。初期の成功は組織内の信頼や協力を生み、内製化を広げるモチベーションと基盤となります。成功事例が共有されることで、他部署やプロジェクトへの展開もスムーズになり、内製化の範囲を徐々に拡大できるでしょう。
また、スモールスタートは問題発生時の影響を最小限に抑え、迅速な対応や調整がしやすいメリットもあります。段階的に外注を減らしながら、確実に体制を整えていくことで、リスクをコントロールしつつ内製化を定着させる効果的な方法といえます。
内製化の完了
DXの内製化が最終段階に達した際に重要なのは、自社のDX推進が継続可能な仕組みとして定着していることです。具体的には、技術やノウハウが社内に十分に蓄積され、それを活用して業務改善や新規サービスの開発が自律的に行える状態を指します。
DXの内製化にはゴールはありません。市場環境や技術は常に急速に進化しているため、それに対応できるように定期的な振り返りや改善活動が欠かせないのです。こうした仕組みが整えば、企業は変化に強い組織となり、競合他社に対して優位性を確保しながら持続的な競争力を高めることができるでしょう。
内製化を成功させるためには、ただ技術を内製するだけでなく、組織全体での持続的な取り組みと成長を視野に入れることが重要なのです。
DXを内製化する際の課題を解説!
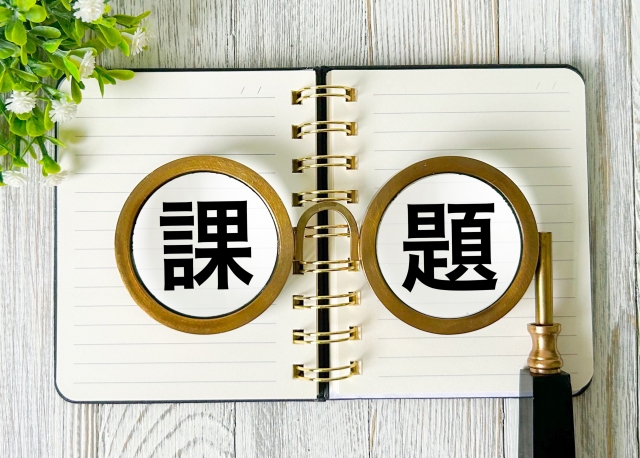
DXの内製化は企業の競争力向上につながる一方で、スムーズに進めるにはいくつかの課題をクリアしなければなりません。中でも最も大きな壁となるのが人材不足とプロジェクトの停滞です。
課題の本質を理解し乗り越えるために、これら2つの問題への対策方法について解説していきます。
人材不足
DX推進に欠かせないITやデジタルスキルを持つ人材の確保は、多くの企業が深刻に直面している課題です。特に、高度な技術力と業務理解を兼ね備えた人材は国内で不足しており、そのため採用競争も激化しています。外部からの採用だけでなく、社内での育成も重要ですが、短期間でスキルを習得することは簡単ではありません。さらに、IT人材は都市部に集中する傾向があり、地方企業にとっては特に確保が難しい現状があります。
こうした背景から、内製化を急ぐ企業はフリーランスや外部専門家を活用しながら、非専門職の社員もローコード・ノーコードツールで業務改善に参加できる環境づくりを進めています。加えて、定期的な研修や勉強会を通じて、社内でのスキル向上を支援し、人材不足を補う体制づくりが求められています。
プロジェクトの停滞
内製化プロジェクトは組織全体を巻き込むため、方向性の共有不足やコミュニケーション不足で停滞しやすいです。現場と経営層の意識差やリソース不足が原因で合意形成が進まず、スケジュールが遅れることも珍しくありません。加えて、複雑な開発やシステム改修には技術的な問題も多く、計画通りに進まないこともあります。
こうした課題を避けるためには、段階的に小さな部分から内製化を進め、成功体験を積み信頼やモチベーションを高めることが重要です。さらに、プロジェクト管理を強化し、定期的な進捗報告や課題を共有する場を設けて情報共有を徹底することも欠かせません。これらを怠ると、プロジェクトは途中で頓挫し、結果的に企業のDX推進が大きく遅れるリスクがあるため、特に気をつけましょう。
DXの内製化に成功した企業を紹介!
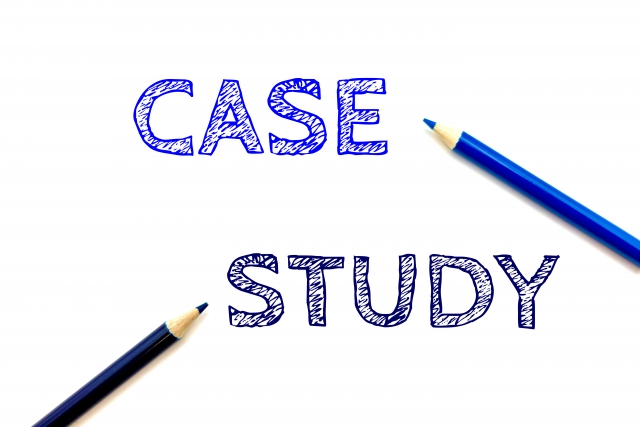
ここまで、DXの内製化について、そのメリットや導入方法、注意点などを詳しく解説しました。ここで気になるのが、ほかの企業の成功事例です。
ここでは、DX内製化に成功している「NTTドコモ」「ダイハツ工業」「竹中工務店」の事例を取り上げます。これらの企業は独自の課題に向き合いながら内製化を推進し、業務改善と競争力強化を実現しています。それぞれの事例を確認することで、自社のDX内製化のイメージもつきやすくなり、成功のためのビジョンも見えてくるはずです。
NTTドコモ
NTTドコモは、全社的にデータドリブン経営を推進するために、内製化のDX体制を強化してきました。顧客データの収集や分析を活かし、意思決定の高度化を目指す専門組織を設置。BIツールを活用し、経営や営業、マーケティングに必要なダッシュボードを自社で開発・運用しています。
内製化により、自社の現場がリアルタイムで効率的にデータを活用できる環境を実現でき、現場担当者が自らデータ分析を行い、意思決定に反映できる仕組みを築きました。
これらの取り組みは単なる技術導入に留まらず、データ分析スキルとマーケティングマインドを兼ね備えた人材育成や組織文化の変革にもつながっています。結果として、変化に迅速に適応しながら継続的な成長を目指す強固なDX基盤の構築に成功しています。
ダイハツ工業
ダイハツ工業は全社的なAI活用を目指し、操作が簡単で専門知識がなくても利用できるAIプラットフォームを導入しました。このシステムによって高精度な予測モデルの作成を自動化することができ、従来半年以上かかっていたモデル生成が短時間で完了できるようになりました。
また、操作性の分かりやすさから、多くの社員がAI活用できるようになったのもポイントです。AI活用へのハードルが大幅に下がったことで、現場からの多様な提案が活発に行われるようになり、ボトムアップでのAI導入が加速しているとしています。
この取り組みは、業務効率の向上と新しい価値創出を促進し、ダイハツ工業のDX推進を大きく後押ししています。
竹中工務店
竹中工務店では、働き方改革や人材不足の課題解決を目指し、パートナー企業と協力して内製化体制を整えました。
特に約30年稼働している会計システムの刷新に取り組み、会計基準の変更や処理担当者の業務効率化を叶えています。実際、竹中工務店では日本の商慣習や建設業向けの要件に特化したERP会計システムを導入し、ワークフローの電子化によって出張先でも承認作業ができるようになり、承認の遅延による業務停滞のリスクを減少させています。
また、内部統制の強化や権限管理の効率化も実現し、業務負荷の軽減とリアルタイムなデータ分析が可能な体制を整えることに成功しています。
これは社内担当者が設計に参画し粘り強く改善につなげた好例で、内製化体制の強化にも繋がり、現在は安定稼働を目指しながら業務効率化を推進しています。
DXの内製化に困ったならオーシャン・アンド・パートナーズへ!

この記事では、DXの内製化について、取り組むメリットや導入方法、注意点について解説し、成功事例もご紹介しました。
DXの内製化は自社の競争力を大きく高めますが、その一方で人材不足やプロジェクト停滞など課題も多く、独力だけで進めるのは難しいことがあります。そんなときにぜひご利用いただきたいのが、「オーシャン・アンド・パートナーズ」です。
同社は多様な業界で培った知見を活かし、組織の課題を全体的に捉えたデジタル変革支援を行っています。単なる開発代行にとどまらず、お客様のITチームと連携しながら技術やノウハウを社内に蓄積していく支援を提供します。
必要なリソースだけを柔軟に外部から補いながら、自社内でスピーディーなシステム対応を可能にする「半内製」体制を採用することで、高コストや納期遅延のリスクを抑えつつ、ノウハウ蓄積や人材育成を推進。アジャイル開発を軸に品質向上とプロジェクトの定着を図っています。
オーシャン・アンド・パートナーズでは、組織や業務の全体最適化を目指した最適なIT戦略も提案しており、現在まで業界を超えて多くの企業様に選ばれています。詳しい事例や実績については公式サイトよりご確認ください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談するこの記事を書いた人について
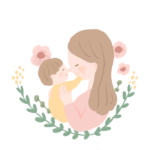
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。