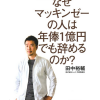基幹システム刷新の失敗原因とは?大企業が陥る5つの落とし穴と成功のポイントを徹底解説!

基幹システムの刷新は、大企業や中堅企業にとって避けて通れない重要な経営課題のひとつです。情報システム部門の責任者や、DX推進を任された管理職にとっては、「刷新の失敗=事業全体への深刻な影響」を意味します。
それでは、なぜ多くの企業が基幹システム刷新で失敗してしまうのでしょうか。失敗の原因を正しく理解し、自社で同じ過ちを繰り返さないための注意点を押さえることが大切です。また、刷新の「最適なタイミング」や「成功に導く進め方」を知ることも欠かせません。
本記事では、企業が陥りやすい基幹システム刷新の5つの失敗要因をわかりやすく解説します。失敗を防ぎ成功へと導くための具体的なポイントや、信頼できるパートナー企業の選び方についても紹介しますので、基幹システム刷新を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
目次
大企業が基幹システムの刷新に失敗する5つの理由とは?

まずは、基幹システム刷新が失敗に終わる原因を詳しく見ていきましょう。要因は多岐にわたりますが、大企業で特に目立つ代表的な5つを以下に挙げます。
これらの問題は単なるシステムの不具合にとどまらず、予算超過や稼働遅延、期待効果の未達といった形でプロジェクト全体の失敗につながるリスクもあります。
システムの理解不足
システム理解の不足は、基幹システム刷新での典型的な失敗要因のひとつです。
大企業の基幹システムは、長年にわたって運用されているケースが多く、改修や機能追加を繰り返すうちに、設計書や仕様書と実際のシステム内容が大きくずれてしまうことがあります。さらに、初期の開発担当者がすでに退職している場合も多く、改修履歴や業務フローの詳細が十分に引き継がれていないことも珍しくありません。
すると、「現行システムがどんな役割を担い、どの機能が業務にとって重要なのか」を正確に把握するのが非常に難しくなります。その結果、必要な機能を新システムに反映できず、運用開始後にトラブルや業務効率の低下を招いてしまのです。
このような基幹システム刷新の失敗を防ぐためには、まず現行システムの構造や機能を丁寧に調査・分析し、ブラックボックス化している部分を明確にすることが不可欠です。業務プロセスとの関係性を整理し、重要機能を正確に洗い出すことが、刷新を成功に導く第一歩となります。
ベンダー選定の失敗
ベンダー選びを誤ることは、基幹システム刷新が失敗に終わる最大の原因のひとつです。コストを重視しすぎて、実績が乏しいベンダーや自社業務との親和性が低いパッケージを選んでしまうと、開発や導入が思うように進まなくなることもあります。
標準機能だけでは必要な要件を満たせず、多数のカスタマイズが発生した結果、予算やスケジュールが大幅に膨らむケースも少なくありません。また、ベンダーの技術力不足や業界知識の欠如は、導入後のトラブル対応やメンテナンスにも悪影響を及ぼします。
さらに、契約内容が不明確なままだと、想定外の追加作業が増え、費用の透明性が失われるなど、プロジェクト全体の管理が難しくなるリスクも高まります。
基幹システム刷新の失敗を防ぐためには、ベンダーの過去実績や顧客評価、技術力、サポート体制を入念に確認し、自社の業務や目的に合ったパートナーを慎重に見極めることが欠かせません。
要件定義が不十分
要件定義が曖昧、または不十分なままプロジェクトを進めてしまうと、基幹システム刷新の失敗リスクが一気に高まります。具体的には、関係者間で業務内容や必要機能に対する認識のズレが生じ、結果として「必要な機能の漏れ」や「不要な機能の追加」が発生します。たとえば、現場担当者との要件共有が不十分な場合、帳票の出力形式や権限管理の仕様が異なり、後工程での修正が頻発することになります。
また、他システムとの連携要件を整理しないまま進めると、データ連携の不備により業務が滞ることもあります。こうした手戻り作業が増えるほど、コストと工期が膨らみ、刷新プロジェクト全体が失敗しかねません。
このような問題を防ぐには、まず刷新の目的を明確に定義し、経営層から現場担当者まで関係者全員が共通認識を持つことが重要です。そのうえで、業務フローや機能要件をできる限り具体的かつ詳細に整理し、合意形成を図ることが基幹システム刷新を成功に導く鍵となります。
担当者不在でプロジェクトが進行する
基幹システム刷新の失敗でよく見られるのが、現場を理解する担当者が不在のままプロジェクトが進んでしまうケースです。刷新プロジェクトでは、日々の業務に精通した担当者が参画し、現場の実態とシステム要件をつなぐ“橋渡し役”を担うことが不可欠です。
しかし、担当者が通常業務に追われて十分に関与できなかったり、途中で異動・退職して離脱したりすると、現場のニーズが正しく反映されなくなります。その結果、完成したシステムが操作しにくい、実際の業務フローに合わないなど、使い勝手の悪い基幹システムが出来上がってしまいます。
さらに、現場間や他システム担当者との連携が不足すると、必要なデータ連携や調整が後回しになり、修正や再設計が頻発することもあります。これは典型的なプロジェクトの遅延やコスト増加を招く基幹システム刷新の失敗パターンです。
こうした事態を防ぐには、業務担当者をプロジェクトの初期段階から継続的に関与させ、定期的にコミュニケーションを取る仕組みを整えることが重要です。現場とシステム部門が一体となって進めることで、現実に即したシステムを構築し、刷新を成功へと導けます。
計画の検討不足
基幹システム刷新は、規模が大きく関係者も多い非常に複雑なプロジェクトです。そのため、綿密で現実的な計画立案が欠かせません。ところが、計画の検討が甘いまま進めてしまい、スケジュールが実態に合わず、進捗管理が難しくなって遅延を招いてしまうケースも少なくありません。
また、移行作業に伴う業務停止期間への配慮が不足していたり、ユーザートレーニングやテスト計画が不十分だったりすると、本稼働後に想定外のトラブルが相次いでしまうこともあります。これは、コスト増加につながるだけでなく、信頼低下など深刻な状況を招いてしまう可能性があり、大変危険です。
こうしたリスクを防ぐためには、段階的かつ現実的なスケジュールを策定し、移行時に発生し得るリスクを事前に洗い出して対策を講じることが重要です。実稼働前のリハーサル(移行テスト)やユーザー教育も丁寧に実施すれば、トラブルを最小限に抑えてスムーズに稼働をスタートさせられるでしょう。
大企業の基幹システムは古くなっている?

上記のように、基幹システムの刷新には多くのリスクがあり、失敗に終わるケースも少なくありません。それでも、多くの企業が刷新に踏み切らざるを得ないのは、現行システムの老朽化が深刻化しているためです。
現在、この基幹システムの老朽化は大企業の多くが直面している課題とされています。これらのシステムは、導入当時の技術やプログラミング言語に依存しており、たとえばCOBOLなど古い言語で構築されたものも少なくありません。その結果、対応できる技術者の不足や、改修履歴が不明瞭なままのブラックボックス化が進行しています。
また、ハードウェアの劣化による処理速度の低下や頻繁なシステムダウンが業務の停滞を引き起こすケースも増えています。さらに、セキュリティリスクの高まりや、最新の業務要件・デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応が難しくなるなどの問題もあり、企業の柔軟な経営判断を妨げる要因にもなっています。
こうした問題を放置すれば、競争力の低下や経済的損失につながるだけでなく、企業の信頼にも関わってくるでしょう。さらに、問題が深刻化すればするほど基幹システム刷新の難易度が上がってしまう点にも注意が必要です。いまや基幹システムの刷新は「いつかやるべきこと」ではなく、「早急に取り組むべき経営課題」となっているのです。
基幹システムを刷新するための最適な時期とは?

基幹システムの刷新の重要性を理解したところで気になるのが、「どのタイミングで刷新すればよいのか」ということです。基幹システムは、ただ古くなったからすぐに更新する、というわけにはいきません。さまざまなリスクを予防し、投資効果を最大限に得るためには、各社に適した刷新タイミングで行うことが重要です。
ここでは、基幹システムの刷新のタイミングの見極めについて詳しく解説します。せっかくの投資を失敗しないためにも、ぜひ参考にしてください。
システムの老朽化
基幹システムは長年使用されれば、どうしても老朽化が進みます。老朽化したシステムは単に動作が遅くなるだけでなく、セキュリティの脆弱性も高まり、新しい業務ニーズや最新技術に対応できなくなってきます。特に、古い技術で構築されたシステムでは、現代のIT環境やクラウドサービスと連携できないケースも少なくありません。その結果、業務担当者の負担が増え、ミスやトラブルが発生しやすくなり、システム全体の信頼性が低下してしまいます。
頻繁な障害や処理速度の低下、手作業・二重入力の増加、操作性への不満が多くなった場合は、老朽化のサインといえるでしょう。
導入当時を知る担当者がいない
基幹システムの導入から長い年月が経過している企業では、当時の担当者がすでに退職しているケースも多く見られます。導入当時の運用ノウハウやシステム仕様を把握している人材がいなくなると、問題発生時の原因特定や改善の方向性が見えづらくなり、対応が後手に回ってしまうおそれがあります。その結果、システムがブラックボックス化し、意思決定の遅れやミスの増加につながることもあります。
担当者不在は、障害発生時の復旧対応が遅れたり、業務停止や信頼失墜を招いたりする大きなリスク要因です。こうした状況を回避するためにも、早期のシステム刷新を検討することが重要です。
業務に合わないシステムを使い続けている
基幹システムが長期間ほとんど改修されずに使われ続けていると、企業の業務変化に追いつけず、システムと実際の業務の間にミスマッチが生じることがあります。
たとえば、市場環境の変化や新規事業の開始、組織再編などによって業務プロセスが変わっても、システム側が対応できていないケースがあります。業務の実態に合わないシステムによって、手作業や二重入力が増え、複数のシステムを使用せざるを得ない状況になることもあります。
業務ニーズに合ったシステム刷新は、業務の標準化と効率化を促進し、社員満足度や生産性の向上にも直結します。業務とシステムの乖離が見られた段階で早期に課題を洗い出し、刷新のタイミングを検討することが重要です。
社員のストレスが溜まっている
社員のストレスや不満が目立ち始めた段階も、基幹システム刷新の重要なサインです。老朽化した基幹システムは操作性が悪く、レスポンスも遅いため、日常業務に大きなストレスをもたらします。使い勝手の悪さから作業時間が長引き、残業の増加やヒューマンエラーの発生につながることも少なくありません。
こういったシステムトラブルが頻発すると、現場の疲弊が進んで社員のモチベーションが低下してしまうことがあります。業務効率の低下が従業員の不満やストレスの蓄積を招き、職場環境が悪化して離職者が増加することも珍しくありません。
こうした悪循環は、生産性の低下だけでなく、企業全体の信頼や競争力にも悪影響を及ぼしてしまいます。社員の負担軽減や働きやすさの向上のためにも、基幹システムの刷新は重要なのです。
サポート終了・終了予告が出たシステムを使っている
基幹システムが古くなったサインとして「サポートが終了している」「終了時期が発表されている」場合というのも注目したいポイントです。
メーカーやベンダーからのサポートが終了すると、問題が発生しても修正やアップデートが受けられず、重大なセキュリティリスクに直面します。セキュリティパッチや脆弱性対策が提供されなくなるため、サイバー攻撃の標的になりやすく、情報漏えいなどの事故リスクが一気に高まります。
サポート終了が予告されている段階でも、移行計画の策定には時間がかかるため、早めの対応が必要です。 対応を後回しにすると、システムダウンや業務停止といった深刻なトラブルを招くおそれがあります。
したがってサポートが完全に終了する前に、余裕をもって刷新・移行を進めることが、リスクを最小限に抑えるための重要です。サポート切れを迎える前に対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、スムーズなシステム移行が実現できるでしょう。
海外への展開を考えている
大企業が海外で事業を展開する際には、基幹システムが多言語・多通貨対応しているだけでなく、各国の法規制や税制にも柔軟に対応できることが欠かせません。こうした要件を満たしていないシステムを使い続けると、現地拠点ごとに独自の業務プロセスや管理方法が生まれ、業務の標準化やデータの一元管理が難しくなります。結果として、情報共有の遅れやミスが発生しやすくなり、全体のガバナンスが弱まるリスクも高まります。
海外展開を計画している企業にとって、各拠点と本社の連携をスムーズにとり、グローバル全体の経営状況をリアルタイムで把握するのは非常に重要な生命線です。特にクラウド基盤の基幹システムであれば、世界各地の拠点へ迅速に展開でき、運用面でも高い柔軟性を確保できます。できるだけ早い段階で基幹システムを刷新し、海外対応機能を備えたシステムに移行するようにしましょう。
DX推進を図りたい
デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する場合も、基幹システムの刷新を行うタイミングです。DXには、既存の基幹システムがクラウド対応やAPI連携など、最新技術に柔軟かつ迅速に対応できることが欠かせないからです。古いシステムのままでは、AI・ビッグデータ分析・RPAなどの先進技術を導入しにくく、業務のデジタル化や自動化が進まないため、DX推進の大きな障壁となってしまいます。
DXの本質は、異なるシステム同士がデータを連携し、リアルタイムで情報を活用できる仕組みを整えることにあります。そのためには、基幹システムの刷新が重要なステップとなるのです。経営層のDX戦略に基づいて、ビジネス環境の変化に柔軟に対応できるIT基盤を構築すれば、スピーディーな意思決定と競争力の強化につなげられるでしょう。
基幹システムの刷新を考えている際の参考になる寿命を紹介!

基幹システムの寿命を正しく把握することは、適切な刷新タイミングを見極めるうえで非常に重要です。
一般的には、基幹システムの寿命はおよそ10年~15年といわれています。この期間を超えると、メーカーサポートの終了や技術的な陳腐化が顕著になり、システム刷新を検討せざるを得ない状況に陥ることが多くなります。
ただし、業務内容や使用状況によって寿命には差があります。頻繁な改修や高度化に対応しているシステムでは想定より早く老朽化するケースも少なくありません。
そのため、寿命を迎える前に計画的に刷新を進めることが重要です。適切なタイミングで基幹システムを更新すれば、業務の変化や企業成長に柔軟に対応でき、刷新の失敗リスクも低減できるでしょう。
基幹システムを刷新する際に失敗しないためのポイントとは?

基幹システム刷新は、規模も費用も大きいプロジェクトであるため、慎重かつ計画的に進めることが求められます。ここでは、基幹システムを刷新する際に失敗しないためのポイントについて解説していきます。
ベンダーに丸投げするのではなく、自社主導で課題を把握・共有しながら進めることが、基幹システム刷新を成功に導く最大のポイントです。詳しく見ていきましょう。
必要な人材体制を整える
基幹システム刷新を成功させるには、専門知識を持つ適切な人材を揃えることが不可欠です。特に、経営層、IT部門、業務部門からバランスよくメンバーを選出し、プロジェクトチームを編成しましょう。
経営層はプロジェクトの方向性や意思決定を示し、IT部門は技術面での計画や開発を担当します。業務部門は業務要件や運用面の視点を提供し、プロジェクトマネジャーが全体の進捗管理と関係者間の調整を円滑に行うことが求められます。
さらに、外部のコンサルタントや技術パートナーを活用することで、社内だけでは補えない専門知識や経験を補強でき、基幹システム刷新の失敗リスクを大幅に低減できます。適切な人材体制の整備は、プロジェクト成功の土台となる重要なポイントです。
刷新理由を明確にする
基幹システム刷新を進める際には、「なぜ刷新が必要なのか」という目的を具体的に設定することが欠かせません。
刷新理由が曖昧だと、プロジェクト全体の方向性がぶれてしまい、関係者間で認識のズレが生じやすくなります。そうすると、必要のない機能追加や要件の変更が増え、スケジュール遅延やコスト超過の原因になることもあります。たとえば、老朽化解消、業務効率化、DX推進、グローバル対応など、刷新の目的によって優先すべき課題や具体的な要件は大きく異なります。
したがって、刷新の目的に合わせて方針や施策を事前に明確化し、経営層から現場スタッフまで関係者全員に共通認識を持たせることが大前提であると言えます。この共通認識が、システム刷新の失敗を回避し、プロジェクトを成功に導くための土台になるのです。
必要な機能と仕様を整理する
基幹システム刷新の成功には、詳細な要件定義と機能・仕様の整理が欠かせません。曖昧な仕様のまま開発を進めると、仕様変更や手戻り作業が増えてスケジュール遅延やコスト増大のリスクが高まります。
詳細な要件定義と機能・仕様の整理には、まず現在の業務プロセスや将来の変化を踏まえ、現場のニーズをしっかり把握することが重要です。具体的には、帳票の出力形式や頻度、アクセス権限の範囲、さらに外部システムとの連携方法など、細部にわたって仕様を明確に定める必要があります。関係部署間で仕様の確認・共有を重ね、すべての関係者が合意することも大事です。
この際、文書だけでなくフローチャートや画面イメージ、プロトタイプなども活用すれば、イメージ共有ができ、プロジェクトの成功率を高めることができるでしょう。また、将来の業務拡張や技術的なアップデートにも対応できる柔軟な設計を心がけましょう。
ベンダーに問い合わせる
システム刷新の成功には、信頼できるベンダー選びが欠かせません。
まず、自社の業務特性や要件にマッチした提案が可能か、過去の導入実績や技術力、サポート体制をしっかりと評価しましょう。これは、過去事例の規模や業種、成功・失敗のポイントを確認し、似た環境での実績があるかで判断することができます。
また、問い合わせ時には疑問点や課題を洗い出し、詳細な要望や質問を伝えることが重要です。これにより提案内容や費用見積もりの適合性が明確となり、トラブル防止につながります。また、契約内容・開発・保守体制の透明性を確保し、不明瞭な部分がないかも確認すべきです。
評価は、コストだけでなくシステムの拡張性やアップデート対応力、セキュリティ、問題発生時の対応力を含め、長期的なパートナーシップの相性も考慮することを推奨します。担当者とのコミュニケーションや企業文化のフィット感も長期的な協力関係構築には欠かせません。複数のベンダーを比較し、丁寧に選定することでシステム導入成功の確率を高めることができるでしょう。
基幹システムの刷新に失敗したくないならオーシャン・アンド・パートナーズへ!

基幹システムの刷新は多くの企業にとって重要かつリスクの高いプロジェクトです。成功には現行システムの正確な理解、明確な刷新目的、適切な人材体制、詳細な要件定義、そして信頼できるベンダー選定が不可欠です。これらを欠かさず実行することで、失敗を回避し、業務効率化やDX推進を実現できます。
オーシャン・アンド・パートナーズは、企業の基幹システム刷新を支援する専門コンサルティングサービスを提供しています。当社は、多数の大企業の基幹システム刷新プロジェクトを成功に導いた豊富な実績と経験を持ち、業務理解に基づいた最適なシステム選定や導入支援を得意としています。
プロジェクト管理のノウハウに加え、ベンダー調整やリスク管理も徹底しているため、トラブル発生を未然に防ぎ、スムーズに刷新を進行できるようサポートします。基幹システムの刷新で失敗したくない企業様は、ぜひオーシャン・アンド・パートナーズへご相談ください。経験豊富な専門家が、最適なパートナーとして成功を力強くご支援いたします。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
この記事を書いた人について
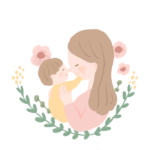
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。