暗黙知を拾い尽くし、根幹だけを残す──基幹システム刷新の成否を分けるもの
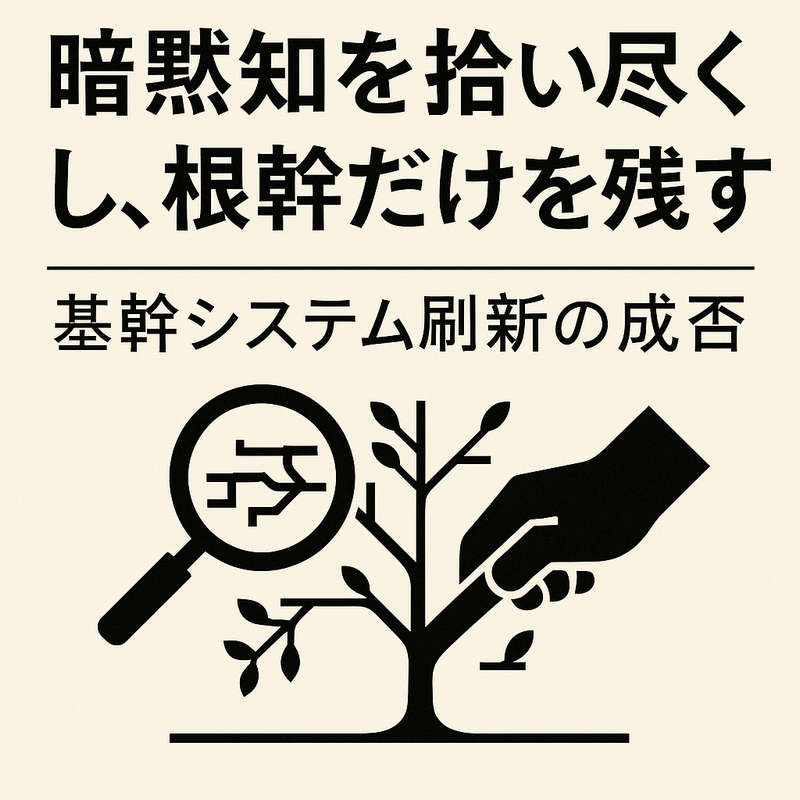
目次
なぜ基幹システム刷新は失敗するのか
基幹システムの再構築は、多くの企業にとって“避けては通れない投資”です。
しかし、うまくいかない事例も少なくありません。
「要件が決まらない」「現場の要望が膨らむ」「コストと期間が青天井」──そんな話を聞いたことがある方も多いでしょう。
さらには完成したのに、現場の士気は上がらない。画面遷移は増え、処理時間は伸び、必要な数字は翌朝にならないと出てこない。さらに保守費は膨らむ一方──。
この繰り返される結末は、偶然ではありません。何を理解し、何を捨てるかという順序を踏まずに設計に飛び込んだ必然の帰結です。
一方で、近年は刷新を成功させた企業も増えてきています。たとえば、ある大手食品メーカーは10年以上使ってきた受発注システムを刷新しました。徹底的に現場を回り、営業担当者や物流スタッフの「ここだけは譲れない」という暗黙知を拾い上げたうえで、システムに組み込む部分とそうでない部分を仕分けしました。その結果、受注から出荷までのリードタイムは平均で20%短縮し、在庫回転率も改善。現場からも「システムが仕事を邪魔しない」という評価を得ています。
ある小売業では、新しいPOSシステムによって在庫管理が飛躍的に効率化し、商品欠品率を大幅に減らすことに成功した事例があります。製造業では、生産工程の情報を整理し直したことで、従来の“属人的な勘”に依存しない仕組みを作り上げ、品質とスピードの両立を実現した例もあります。
失敗が多い領域であっても、正しい順序を踏めば成功できる──それを示す事例が確かに存在しています。
本質的な失敗理由:「掘る前に設計してしまう」
失敗の多くは、現場を理解しないまま設計に進んでしまうことに起因します。
物流業のある典型的な事例では、配送ルート最適化のシステムを導入したものの、ドライバーが使わずに紙の地図へ逆戻りしてしまいました。理由は簡単で、システムが考慮していたのは「最短距離」だけだったからです。実際の現場では「荷下ろし先の混雑具合」や「信号待ちの多さ」といった暗黙知が配送効率を左右しており、それを拾わずに設計してしまった結果、システムが現実に合わなかったのです。
逆に成功した製造業の事例では、半年以上をかけて現場を観察し、ベテラン作業員がどのように異常を検知しているかを徹底的に聞き出しました。その知見を「センサー情報+人の判断ポイント」として設計に組み込み、システムはシンプルながら信頼性が高いものになりました。
つまり、暗黙知を掘らずに設計した企業は失敗し、掘ってから設計した企業は成功するのです。
第一步:「枝葉を拾い尽くす」地道な調査
刷新を成功させた企業は例外なく、まずは「拾い尽くす」ことを徹底しています。
ある地方銀行では、融資審査プロセスの刷新を行いました。プロジェクトメンバーは半年間で延べ50人以上の現場担当者にヒアリングを実施。審査資料の裏に書き込まれていたメモや、担当者だけが知っている「取引先の特徴」を丁寧に拾い上げました。最終的に、それらを「システム化すべき判断」と「人間に残すべき判断」に分けることで、システムはシンプルで使いやすく、かつ現場の安心感も担保されました。
また、ある製薬会社では、研究部門から生産部門までの情報連携をテーマに刷新を実施。現場に眠るExcelファイルや個人フォルダのノートまで調べ上げ、200以上の“非公式プロセス”を洗い出しました。そのうえで、「研究データの承認ルート」など根幹に関わる部分はシステムに組み込み、それ以外は部門間で柔軟に扱える仕組みを残しました。結果として、新薬開発のリードタイム短縮に直結しました。
枝葉を拾う作業は地味ですが、成功企業はここに時間を惜しまなかったのです。
第二歩:「根幹を残し、大胆に削る」決断
ただし、拾ったものをすべてシステムに盛り込むと失敗します。
成功した企業が必ずやっているのは、「根幹を残し、それ以外を削る」判断です。
ある大手小売チェーンは、POSシステム刷新の際に現場から数百項目の要望が集まりました。しかし経営層は、「売上を迅速に把握する」「在庫を正確に管理する」という根幹以外は思い切って削除。顧客アンケートや販促施策などは外部SaaSとAPI連携する方針に切り替えました。その結果、導入からわずか半年で投資回収を実現。しかも周辺機能はSaaSの進化に合わせて柔軟に切り替えられる仕組みができました。
逆に、あるメーカーでは現場の声を「全部入れよう」とした結果、画面は複雑化し、操作マニュアルは数百ページに。現場からは「結局Excelの方が速い」と突き返され、再び大規模改修に追い込まれました。
削る勇気こそ、成功企業を成功企業たらしめている要素なのです。
そして枝葉を徹底的に掘り切らなければ、残すべき根幹の肖像は決して浮かび上がりません。木の枝葉をすべて観察してこそ幹の形が際立つように、業務の細部を拾い尽くすことで初めて、経営として本当に守るべき中核が明確になります。掘り切らずに曖昧なまま判断すれば、残す基準も揺らぎ、結果としてシステムは肥大化してしまうのです。
実行のヒント:経営者にしかできない二つの役割
成功事例から見えてくるのは、経営者が果たすべき役割の明確さです。
-
徹底した調査を支援すること
暗黙知を拾う調査は時間がかかります。経営が「そこに投資する価値がある」とメッセージを出すことが、現場を動かす力になります。 -
削る決断を下すこと
部門の声をすべて取り込むのではなく、「10年後に残すべきものは何か」という視点で要件を仕分けること。この判断は経営者にしかできません。
実際、前述のメーカーの経営者は「10年後にまだ価値を持つか?」という問いを基準に要件を仕分けしました。その結果、余計な機能を削りつつも、成長に耐えられる柔軟な基幹システムを手に入れました。
まとめ
基幹システム刷新は難しい挑戦ですが、成功事例が示す通り、正しい順序を踏めば成果は確実に得られます。
-
枝葉を拾い尽くす調査を徹底すること
-
根幹を残し、大胆に削る決断を下すこと
この二つをやり切った企業は、現場に受け入れられるシステムを手に入れ、変化に対応できる基盤を築いています。
暗黙知を拾い尽くし、根幹だけを残す──この順序を守ることが、刷新を成功に導く唯一の道なのです。
この記事を書いた人について

-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社 代表取締役
協同組合シー・ソフトウェア(全省庁統一資格Aランク)代表理事
富士通、日本オラクル、フューチャーアーキテクト、独立系ベンチャーを経てオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社を設立。2010年中小企業基盤整備機構「創業・ベンチャーフォーラム」にてチャレンジ事例100に選出。
最新記事一覧
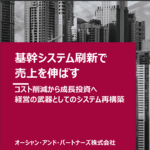 経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか?
経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか? 経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは
経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは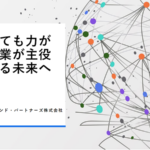 経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録
経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録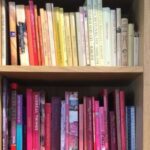 RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―
RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―










