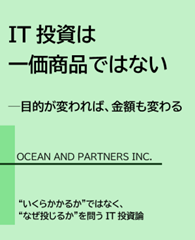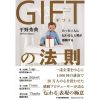そのIT投資は1年で回収可能か?システム投資ROIの目安と6つの判断ポイント

あるミーティングでのこと、営業部門と管理部門の責任者が集まり、業務の課題について議論を重ねていました。
その中で「業務効率を向上させる方法」として、ITシステムの改善が解決策として挙がり、業務を効率化できる余地があること、社内リソースを緩和できる可能性があること、そしてどのような仕組みが適しているのかが検討され、さらにプロジェクトの金額感や実施期間についても考察が示されました。
責任者の方々は、口々に業務の負担軽減や営業活動への好影響を期待する意見を述べ、具体的な業務プロセスの改善に対する期待も高まり、導入を模索する姿勢が見受けられました。
しかし、具体的な予算の確保や、プロジェクトに関わるリソースの割り当てを想像し始めた途端、空気が一変、「決裁を取るのは難しいかもしれない」「経営層に話を持ち込むと、慎重になってしまう可能性がある」と、不安の声が出始めたのです。
結局、経営層に決裁を打診してみるものの、正式な検討は先送りにされ、案件は動かないままとなりました。顧客側の担当者も「この状況をどう打開すればいいのか」と頭を抱えています。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談する目次
- 1 システム投資の際のROIと計算方法とは?目安も解説!
- 2 システム投資のROIに対する一般的な考え方とは?
- 3 1年以内にROIを回収する目安となるケースを解説!
- 4 システム投資で現状の非効率性がROIに与える影響とは?
- 5 システム投資で定量的と定性的なROIのバランスの目安を解説!
- 6 システム投資は1年でのROIを上げるのが難しいケースとその対策とは?
- 7 ROIとROASの違いとその他の指標を解説!
- 8 システム投資の際のROIの具体的な活用パターンとは?
- 9 システム投資の際のROIのメリット・デメリットを解説!
- 10 システム投資の際のROIの目安がわからないならオーシャン・アンド・パートナーズへ!
システム投資の際のROIと計算方法とは?目安も解説!

システム投資を進める際、多くの経営者が気になるのは「投資に見合ったリターンが得られるのか」という点です。そこで登場するのがROIという指標です。
ROIを用いることで総合的な費用対効果を測定でき、経営判断の根拠として活用できるのです。ここではROIの基本的な意味、計算方法、そして目安となる判断基準について詳しく見ていきましょう。
ROI(Return On Investment)
ROIとは「投資利益率」を意味し、投資額に対してどれほどの利益が得られたかを示す指標です。システム投資の場面で用いる場合、例えば業務効率化による人件費削減や、新しい顧客管理システムの導入による売上増加などを数値化して投資効果を測ります。
ROIの大きな特徴は、投資の成否を「金額ベースで比較できる」点です。たとえば、1,000万円をかけてシステムを導入し、年間で1,500万円の利益改善が得られた場合、ROIは50%となります。
ROIが高ければ投資効果が大きく、低ければ改善余地があると判断できるわけですが、万能ではなく、効果がすぐに現れにくい投資では短期的に数値が低く出る場合もあります。そのため、あくまで客観的な目安として活用しつつ、長期的な戦略や非数値的な効果も考慮する必要があるのです。
ROIを求める計算方法
ROIの基本的な計算式は次の通りです。
ROI(%)=(投資による利益 − 投資額)÷ 投資額 × 100
たとえば、システム導入によって得られる利益が2,000万円、投資額が1,000万円の場合、ROIは100%となります。つまり投資した分を上回る利益が得られたことを意味しているのです。
一方で、利益が800万円しか出なければROIはマイナス20%となり、投資に失敗したと判断されます。重要なのは、投資額とリターンを正しく計算することです。リターンには売上増加だけでなく、コスト削減や生産性向上による間接的な利益も含めることができます。
実務でROIを計算する際には、短期・中期・長期のスパンで算出し、持続的な効果を測るのがおすすめです。
目安となる判断基準
ROIを活用する際に気になるのは、「どのくらいの数値であれば良い投資といえるのか」という目安です。一般的にはROIが20%以上であれば投資として妥当とされ、50%を超えると優良な投資と判断されることが多いです。
ただしこれは業種や投資規模によって変動します。例えば、製造業のように初期投資が大きい分野ではROIが低くても長期的にプラスへ転じるケースがあり、ITやマーケティングの分野ではROIが高めに出やすい傾向があります。
ROIの数値だけでなく、投資によって得られる「副次的な効果」にも注目が必要です。顧客満足度の向上や業務効率化による従業員の働きやすさ改善など、数値化しづらい要素が企業の競争力につながることも少なくありません。つまり、ROIは便利な指標ですが、単純に数値だけを基準にするのではなく、投資の目的や事業戦略と照らし合わせて総合的に判断することが求められます。
システム投資のROIに対する一般的な考え方とは?

むしろ、多くの企業がIT投資の必要性を認識しながらも、意思決定の段階で逡巡し、前に進めない状況に陥っています。その背景には、投資効果の不透明さや回収期間の不確実性が大きく影響しています。
本コラムでは、このような課題を解決するため、「1年で回収できるかどうか」という新たな判断基準を提案し、合理的な投資判断を行うためのポイントを解説します。また、以下の6つの視点から考察を深めます。
1.回収期間の短縮が業績の安定に直結する
IT投資の回収期間が短いほど、キャッシュフローが健全化し、企業の経営安定性が向上します。
2.1年回収基準を採用することで、投資の優先順位が明確になる
どのIT投資が本当に価値を生むかを見極めやすくなります。
3.「IT投資はすべて1年で回収できる」と考えるのは誤り
適切な回収期間の設定が重要であり、業態や投資対象によって基準を柔軟に調整すべきです。
4.回収基準を定量的に測るためのフレームワークが必要
数値で効果を見極めるための測定方法が不可欠です。
5.回収期間の短縮と長期的な競争力強化を両立させる視点が必要
短期的な利益と長期的な成長のバランスをとることが重要です。
6.1年以内の回収が難しい場合の代替指標を持つ
投資対効果の判断軸を多面的に設定することで、柔軟な判断が可能になります。
特に中堅企業の経営層や事業部門の責任者にとって、IT投資の判断は極めて重要な経営課題となります。なぜならば、限られた予算の中で最大の成果を得ることが求められ、不要な支出を抑える必要があるからです。そのため、1年という短期間での回収が可能であれば、投資を決断しやすくなります。
IT投資のコンサルティングを考えているならこちら
「オーシャンのコンサルティング」
1年以内にROIを回収する目安となるケースを解説!

1年以内の回収が現実的なケースとして、以下の3つのシナリオが考えられます。
1.直接的なコスト削減
例えば、RPAを導入して年間500時間の業務時間を削減し、時給2,000円と仮定すると、年間100万円のコスト削減が可能です。初期投資が100万円未満であれば、1年以内に回収できます。
2.売上増加
営業部門やマーケティング領域では、適切なツールを導入することで、リード獲得の効率化やクロージング率の向上が期待できます。具体的な例として、以下のようなシステム導入が挙げられます。
-CRM(顧客管理システム)の導入
営業プロセスを一元管理し、顧客情報を最適化することで、営業効率を向上させ、年間売上を1,000万円増加させることができれば、初期投資が1,000万円未満であれば1年以内の回収が可能です。
-デジタルマーケティングの自動化
マーケティングオートメーションを活用することで、適切なタイミングで顧客にアプローチし、成約率を向上させることが可能です。
-ECサイトの強化
オンライン販売チャネルを整備し、デジタルマーケティングと組み合わせることで、売上を大幅に拡大できます。
これらのシステムは、売上増加がダイレクトに見えるため、IT投資としても短期間でのROI(投資回収)が期待できます。
3.維持コスト軽減
クラウド移行により、年間200万円のインフラコストを削減できれば、初期投資が200万円未満であれば1年以内に回収できます。
【財務視点での考察】
特に中堅企業においては、経営リスクの軽減という観点から、1年以内の回収を目指すことが推奨されます。経営資源が限られる中で、長期間にわたって効果が不透明な投資を行うことは、財務上のリスクを高める要因となり得ます。例えば、以下のような点がリスク軽減につながります。
1. キャッシュフローの安定化
短期間で回収できる投資は、資金繰りへの影響を最小限に抑えることができます。
2.リスク回避
不確実性の高いプロジェクトに長期間の資金を投じるのではなく、早期に効果が見える施策を優先することで、失敗のリスクを減らすことが可能です。
このように、短期間での回収が見込めるIT投資は、財務戦略の観点からも有効な選択肢となります。
システム投資で現状の非効率性がROIに与える影響とは?

システム投資を行う際、多くの企業は導入後の効果に注目しがちですが、実は投資前の業務効率の状態がROIに大きく影響します。
ここで、現状の非効率性がどのようにROIに影響するのか、その評価方法や考慮すべきポイントを整理し、投資判断の精度を高めるための視点を解説していきます。
現状が非効率であればあるほど、上昇幅を大きく取れる
現状の業務が非効率であればあるほど、IT投資による改善効果は大きくなります。
例えば、20名の管理部門と10名の営業部門が毎日1時間の業務時間を削減できれば、年間7,200時間の削減が可能です。時給2,000円と仮定すると、年間1,440万円のコスト削減が実現できます。もし1,400万円のIT投資でこれを実現できれば、1年で回収可能です。
ちなみに日本企業において人件費は固定費であるため、業務の効率化によって削減された時間は、直接的なコスト削減にはつながりにくいものの、新たな余剰リソースとして活用できます。この余剰リソースの活用によって、以下のようなシナリオが考えられます。
• 業務リソース増加の視点
業務効率化による時間削減の恩恵が他部門にも波及し、全社的な生産性向上につながる。
• 営業リソース増加の視点
余剰時間を活用することで、新規顧客獲得やクロスセルの機会が増加し、売上が加速度的に伸びる可能性が高まる。
•財務リソース増加の視点
IT投資によって解放されたリソースが、新規プロジェクトや市場開拓に振り向けられ、企業の成長速度を加速させる。
営業リソースの増加が売上に与える影響
特に余剰時間を多く確保できる可能性については、営業部門を例に考えると分かりやすいでしょう。IT投資による業務の効率化によって、本来の営業活動に充てる時間を増やせることが売上増加に直結する重要なポイントになります。
例えば、10名の営業スタッフが1日1時間の余剰時間を営業活動に充てられるとすると、年間で2,400時間分の追加営業リソースが生まれます。仮に営業スタッフが1時間あたり1件のアポイントを取得できるとすれば、年間2,400件の商談機会が増加します。そのうち10%が成約につながると仮定すると、240件の追加成約が見込めます。もし、1件あたりの平均受注単価が50万円だとすれば、1年間で1億2000万円の売上増加につながる計算になります。
このように、IT投資によって間接業務を削減し、営業リソースを本来の業務に集中させることで、投資額をはるかに超える売上増加を実現できる可能性がある ことを考慮すべきです。IT投資は単なるコスト削減手段ではなく、企業全体の生産性向上と収益拡大をもたらす経営戦略の一環であるという視点を持つことが重要です。
システム投資で定量的と定性的なROIのバランスの目安を解説!

定量的ROIは数値で測れるため、投資判断の基準として分かりやすいですが、定性的ROIも無視できません。
例えば、IT投資によって意思決定の迅速化が実現すれば、市場変化への対応力が向上し、長期的な競争力を強化できます。また、従業員の満足度向上は、離職率の低下や生産性の向上につながり、間接的に業績に好影響を与えます。
定性的ROI(数値化が難しいが重要な効果)が向上するケースとして例を示します。
• 意思決定の迅速化:
システム導入によりリアルタイムでデータを把握できるようになれば、経営判断のスピードが向上し、競争力を強化できます。
• 従業員満足度の向上:
業務負担が軽減されることで従業員のストレスが減り、生産性向上につながる可能性があります。
• ブランドイメージの向上:
最新のIT技術を導入することで、サービスの品質や提供速度が向上し、取引先や顧客からの信頼を強化できる場合もあります。
定量的ROIだけでなく、定性的なROIも含めて評価することが、IT投資の成功につながります。
システム投資は1年でのROIを上げるのが難しいケースとその対策とは?

すべてのIT投資が1年で回収できるわけではありません。
例えば、ERPシステムの刷新や新規事業向けのシステム導入は、長期的な視点が必要です。
短期的な費用対効果だけでなく、中長期的な影響も考慮する必要があります。
例えば、業務効率化や人件費削減といった直接的な利益は測定しやすいですが、意思決定の迅速化や組織の柔軟性向上など、間接的な利益については定量的な評価が難しいのが現状です。
これから1年以内の回収を目指すべきケースと、それが難しい場合の判断基準について整理してみます。
長期的なシステム投資が必要な場合
以下のようなケースでは、2〜3年以上の回収期間を見据える必要があります。
• 基幹システムの刷新:
ERPやSCMの導入は、企業全体の業務フローを変革するため、短期での回収は難しい傾向にあります。
• 新規事業向けのシステム導入:
市場が未確定な新規事業にIT投資を行う場合、成果が出るまでに時間を要する可能性があります。
• 組織のITリテラシー向上が必要な場合:
システム導入だけでなく、社内教育を並行して行う必要がある場合は、定着するまでの期間が長くなります。
IT投資の平均相場についてはこちら
ホワイトペーパー「統計からひもとくシステム投資額の平均相場観」
長期回収のシステム投資を成功させるための対策
• フェーズ導入
一度に大規模なシステムを導入するのではなく段階的に導入し、各フェーズでROIを評価しながら投資を進めることで、リスクを分散します。
• 短期回収プロジェクトとの組み合わせ
基幹システムの刷新と並行して短期間で効果を出せる小規模なIT導入を実施し、短期間で効果を出すことで、全体の投資効果を高めます。
ROIとROASの違いとその他の指標を解説!
システム投資の効果を測る際、ROI以外にもさまざまな指標が存在します。その中でも混同されやすいのが「ROAS」です。ROIとROASはどちらも投資効果を数値で表すものですが、計算の対象や意味合いに違いがあるのです。
企業活動においてはROIやROAS以外にも役立つ指標があるため、それぞれを正しく理解しておくことが的確な投資判断につながるでしょう。ここでは、ROIとROASの違い、そしてその他の代表的な指標について詳しく解説します。
ROIとROASの違い
ROIとROASはどちらも投資の成果を測定するための数値ですが、焦点を当てているポイントが異なります。
ROIは「投資全体に対する利益率」を示す指標で、売上増加だけでなくコスト削減や生産性向上による効果も含めて計算できます。つまり、企業活動全般を通して投資がどれだけ利益を生み出したのかを総合的に評価するためのものです。
一方で、ROAS(Return On Advertising Spend)は「広告費に対する売上額」を測る指標です。計算式は「売上 ÷ 広告費 × 100」で表され、広告活動がどれだけ効率的に売上を生み出したかを判断します。
例を挙げると、広告費100万円に対して売上500万円が生まれればROASは500%です。しかしその広告によって得られた利益が実際には200万円しかなく、運営コストを引くと利益がほとんど残らない場合もあります。
ROASは広告活動の成果を短期的に確認するための指標、ROIは投資全体の収益性を判断するための包括的な指標という点が大きな違いです。両方を併用することで、システム投資やマーケティング戦略の精度をより高めることができるでしょう。
その他指標との違い
ROIやROASのほかにも、投資効果を測るための指標はいくつか存在します。代表的なものとして以下が挙げられます。
- CPA(Cost Per Acquisition)
新規顧客を獲得するためにかかった費用を示す指標。広告やキャンペーンの効率性を測る際に利用され、獲得単価が低いほど効率的とされる。 - LTV(Life Time Value)
顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益の総額を示すもの。LTVが高い顧客を多く抱える企業は、長期的に安定した利益を得られる傾向。 - CPC(Cost Per Click) 広告が1クリックされるごとに発生するコストを表す指標。クリック数が増えてもコンバージョンにつながらなければ意味がないため、CPAやROIと組み合わせて評価することが重要。
これらの指標はそれぞれ特定の目的に特化しています。ROIは全体的な投資判断に有効ですが、広告やマーケティング活動のように特定の施策を評価する場合はROASやCPAが適していると言えます。
システム投資や広告戦略を評価する際には、ひとつの指標に頼るのではなく、ROIを基軸にROASやLTVなどを組み合わせることが、実態を正確に把握するための鍵となるのです。
システム投資の際のROIの具体的な活用パターンとは?

ROIはシステム投資の効果を測る際に欠かせない指標ですが、実際の活用場面は一つではありません。導入を検討している段階、運用を始めて効果を測定する段階、あるいは事業全体を評価する段階など、さまざまなシーンで役立ちます。
システム投資は金額規模が大きく、費用対効果を誤ると経営に大きな影響を与えるため、ROIを正しく読み解くことが重要です。ここでは具体的に、ROIが活用される代表的なパターンを4つ取り上げて詳しく解説します。
マーケティングの効果の確認
システム投資におけるROIは、マーケティング施策の効果検証でよく使われます。例えば、顧客管理システム(CRM)を導入することでリード獲得数が増え、営業効率が改善した場合、どれほど売上につながったかをROIで算出できるのです。
マーケティングオートメーションツールの導入により、顧客へのアプローチが自動化され、成約率が上がったとき、その効果を金額に換算することで投資の妥当性も測定できます。単に売上増加を確認するだけでなく、「投資額に対してどのくらい効率的に成果が出ているのか」を把握できるのがROIの強みです。
ROIを活用すれば、複数の施策を比較する際の判断材料にもなります。たとえば、AシステムとBシステムのどちらを導入すべきか迷ったとき、それぞれのROIを計算することで、費用対効果の高い選択が可能となります。
投資判断の決断の時
システム導入の検討段階では、ROIは投資判断の後押しとなります。新しいシステムの導入は多額の初期投資を必要とするため、経営層にとっては慎重な決断が求められるのです。
その際にROIを算出することで、数値的な裏付けを持ったプレゼンテーションが可能になり、社内合意を得やすくなります。たとえば、営業支援システムを導入した場合、どのくらい人件費が削減できるのか、どの程度売上が増加するのかをROIで明示することで、投資の妥当性を客観的に示せます。
「感覚的に良さそうだから導入する」という曖昧な判断ではなく、「確実に費用対効果が見込める」という裏付けのある判断が可能となるのです。
事業の評価
ROIは事業そのものの評価指標としても活用できます。特にシステム投資は単体の施策にとどまらず、部門全体の業務プロセスを改善するケースが多いため、投資効果を総合的に評価することが重要です。
例えば、在庫管理システムを導入することで在庫回転率が改善し、キャッシュフローが健全化したとします。その結果、仕入れコスト削減や廃棄ロスの減少につながり、最終的にROIが向上します。
こうした定量的な評価を行うことで、経営層は事業全体の効率性を把握でき、次の戦略立案に役立てることができますし、部門ごとにROIを比較することで、どの部署の投資が効果的だったかを判断でき、リソース配分の最適化にもつながるでしょう。
大規模な投資判断
ERP(統合基幹業務システム)や大規模な基盤システムの刷新といった投資は、数億円規模になることも少なくありません。このような大規模投資では、ROIが極めて重要な判断基準となります。
大規模投資は効果が出るまでに時間がかかるため、短期的なROIだけでなく、長期的な視点でのROI算出が必要です。例えば、初年度はROIが低くても、5年後にプラスへ転じる見込みがあれば、将来的に大きなリターンが期待できると判断できます。
さらにROIを用いれば、複数の大規模投資案件を比較し、優先順位を付けることも可能です。リスクを最小限に抑えながら、企業の成長につながる投資を選び取るために、ROIは欠かせない指標だといえるでしょう。
システム投資の際のROIのメリット・デメリットを解説!

ROIはシステム投資の効果を客観的に把握できる便利な指標ですが、もちろん万能ではありません。ROIの強みを理解しつつ、同時に注意すべき限界やデメリットも踏まえて活用することが大切です。
ここでは、ROIをシステム投資に用いる際のメリットとデメリットを整理し、効果的に使うための考え方を解説していきます。
メリット
ROIを用いる最大のメリットは、投資効果を「数値」で明確に示せる点です。システム投資は導入時に多額のコストがかかるため、その際にROIを算出することで、経営層や関係部門に対して客観的な裏付けを持った説明が可能になります。
続いて、異なる投資案件を比較する際にも役立ちます。例えば、顧客管理システムと在庫管理システムのどちらを優先すべきか迷った場合、それぞれのROIを算出することで、費用対効果の高い投資を選びやすくなるのです。
さらに、ROIは短期的な施策の検証にも有効です。システム導入後にどれほど売上が改善したか、業務効率化によってどれだけコストが削減できたかを可視化することで、次の投資判断や改善策につなげることができるでしょう。
このようにROIは「導入の判断材料」「投資効果の検証」「案件の比較基準」として、多面的に活用できるのが大きなメリットです。
デメリット
一方で、ROIにはいくつかのデメリットも存在します。まず挙げられるのは、数値化できる範囲が限られるという点です。
システム投資による効果には、売上増加やコスト削減のように明確に金額換算できるものだけでなく、顧客満足度の向上や従業員の働きやすさ改善といった定性的な効果もあります。
次に、「短期的な効果」に偏りがちだという点も問題です。特に大規模なシステム投資は効果が出るまで数年かかるケースも多く、初年度のROIが低くても、長期的には大きなリターンが見込める場合があります。
また、算出方法によっては数値が大きく変動する点も注意が必要です。利益をどこまで含めるか、投資額にどの範囲を計上するかによって結果が大きく異なるため、算出基準を明確にしておかなければ、比較の信頼性が損なわれてしまいます。
以上のように、ROIは非常に有用な指標ではあるものの、その数値だけで投資を判断するのは危険です。定性的な効果や長期的な視点を加味し、他の指標と組み合わせて総合的に評価することが欠かせません。
こんな資料はいかがですか?(無料ダウンロード提供中)
ホワイトペーパー「IT投資は一価商品ではない」
- 経営が握る“予算の作法”- PDF形式
─「IT投資を「コスト」ではなく
「戦略」として捉えるための新しい視座を提示します。
🚀読後に得られる視点
-
IT投資の「適正価格」を、
金額ではなく目的から逆算できるようになります。 -
ベンダー見積の“高い・安い”に惑わされず、
判断軸を自社の経営目的に置けるようになります。 -
「IT=コスト」ではなく、「IT=戦略投資」として意思決定できるようになります。
システム投資の際のROIの目安がわからないならオーシャン・アンド・パートナーズへ!

IT投資の判断基準として「1年で回収できるかどうか」は重要な視点ですが、それだけにとらわれず、定性的な効果や長期的な競争力の向上も考慮する必要があります。具体的には、以下のステップで判断を行うことをお勧めします。
1. 投資目的を明確にする
特に直接的なコスト削減や売上向上につながるものは、積極的に検討すべきです。
2.定量的・定性的な評価基準を設定する
ROIを単なる数字で測るのではなく、企業の成長や競争力強化の観点からも評価することが求められます。
3.短期回収が可能な投資と長期投資をバランスよく組み合わせる
これらのポイントを踏まえ、柔軟にIT投資を評価することで、企業の成長を加速させることが可能となります。
専門的な知見を持つパートナーに相談すれば、解決への近道になります。オーシャン・アンド・パートナーズは、企業の資金調達や事業戦略に関する豊富な実績を持ち、システム投資におけるROIの算出や判断基準の策定についてもサポートします。
ROIの目安に悩んでいるなら、一度プロに相談してみてはいかがでしょうか。専門家のアドバイスを得ることで、自社にとって最適な投資判断ができ、将来的な成長への道筋を明確に描けるでしょう。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談するこの記事を書いた人について
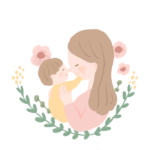
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。