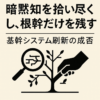基幹システム再構築の失敗事例について徹底解説!失敗を避けるための5つのポイントとは?

基幹システムの再構築は、企業が競争力を維持し、業務を効率化していくために欠かせない取り組みです。とはいえ、実際には多くの企業が思わぬ壁にぶつかり、残念ながら失敗に終わってしまうケースも少なくありません。失敗してしまうと、予算の大幅な超過や納期の遅延が発生するだけでなく、業務そのものが滞るといった深刻な事態につながってしまいます。
こうした事態を防ぐためには、過去の失敗例から学び、事前に適切な対策を取っておくことが非常に重要です。実際の現場の意見が一致しないまま進めてしまったり、システム導入の目的があいまいだったり、ベンダー選びを誤ったりと、基幹システム再構築には数多くの落とし穴があります。
本記事では、よくある失敗パターンを分かりやすく整理し、それらを回避するための具体的なポイントをご紹介します。再構築プロジェクトを成功に導くヒントとして、ぜひ参考にしてください。
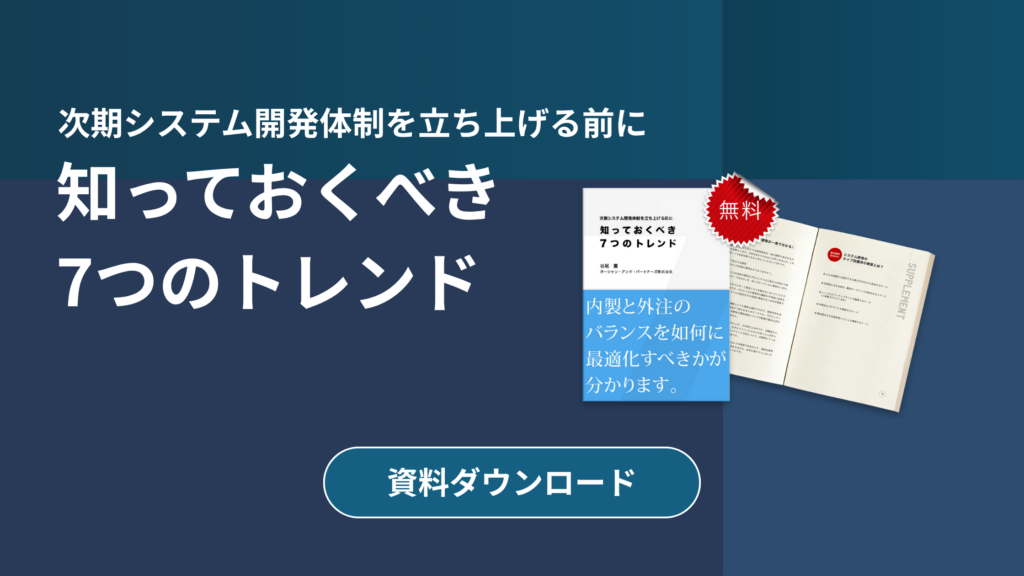
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
目次
基幹システムとは?

基幹システムは、企業のビジネス活動において根幹となる業務を支える要となるITシステムのことを指します。基幹システムが止まるとビジネスが継続しがたい状況に陥り、企業経営にとって大きな打撃となりかねません。そのため、基幹システムには高い安定性と堅牢性が求められます。
一般的に基幹システムには、販売管理システム、生産管理システム、在庫管理システム、物流システム、財務会計システム、人事給与システムなどが含まれます。基幹システムは、企業がビジネス活動をする上で欠かせないシステムであるため、その再構築は慎重に行う必要があります。
基幹システムの再構築はなぜ必要?

そもそも、基幹システムの再構築が必要となる背景には、さまざまな理由が存在します。基幹システムでは、長年の改修が重ねられた結果、いわゆるスパゲッティーコードと呼ばれる複雑で難解なソースコードになることが多く、保守業務の難易度が年々高まっている問題を多くの企業が抱えています。システムのレガシー化により、メンテナンスやランニングコストが増大し、DX推進の足かせとなっているのが現実といえるでしょう。
つまり現代において、企業にとって基幹システムの刷新は避けて通れない課題となっています。また、業務の変化に対し、現行の基幹システムが対応できなくなっている状況や、従業員からの不満が高まっている場合も、再構築を検討すべきタイミングとなります。
新しい技術への対応やデータの一元管理、セキュリティ強化といった現代的な要求に応えるためにも、基幹システムの再構築は重要な経営課題なのです。
基幹システム再構築の失敗事例

基幹システムにおける再構築プロジェクトでは、多くの企業で失敗が発生しています。すでに起きてしまった失敗事例を理解することで、自社のプロジェクトでリスクを回避することができるでしょう。
実は失敗の多くは、プロジェクト初期段階での準備不足や関係者間の認識のズレに起因しており、適切な対策を講じることで防ぐことができるものがほとんどです。本章では、具体的な基幹システム再構築の失敗事例をご紹介します。
現場の声が一致せず方向性が定まらない
基幹システム再構築における最も典型的な失敗パターンの一つが、現場の声を無視しての導入は難しい一方で、現場の意見を聞きすぎると本来の方針から外れてしまい、結果的に失敗を招くというものです。
現場の声が一致しないと各部門がそれぞれ異なる要求を持ち出し、統一された方向性を見いだせないまま混乱が拡大してしまいます。営業部門は顧客管理機能の強化を求め、製造部門は生産管理の効率化を重視し、経理部門は財務機能の精密さを要求するなど、利害が対立する場面が頻発してしまうのです。
このような状況では、プロジェクトの進行が滞り、開発期間が大幅に延長される結果となります。すべての要望に応えようとすることで、システムが複雑化し、使いにくいものになってしまうリスクも高まります。さらに、現場の意見がまとまらないことで、最終的な意思決定が遅れ、プロジェクト全体のスケジュールに深刻な影響を与える可能性もあるでしょう。
このような失敗を回避するためには、プロジェクト開始前に責任者を明確に定め、各部門の要求を整理・調整する仕組みを構築することが不可欠です。各部門の代表者による定期的な会議を開催し、全社的な視点から優先順位を決定する体制を整える必要があります。現場の意見を尊重しつつも、最終的な決定権を持つ責任者を設けることで、方向性のブレを防ぐことができます。
ある製造業の企業では、部門間の調整が不十分なまま開発を進めた結果、完成したシステムは「誰もが中途半端に満足しない機能」が詰め込まれた複雑な仕組みとなり、結局ほとんど利用されなくなってしまいました。
このような状況では、プロジェクトの進行が滞り、開発期間が大幅に延長される結果となります。
新システム導入の狙いが不明確
基幹システム再構築プロジェクトで発生する深刻な問題として、目標が曖昧な状態で基幹システムを導入すると、システムが十分に機能せずにコストだけがかかってしまうため、失敗という結果を招く要因となりかねない課題があります。
導入目的が明確でない場合、プロジェクトメンバーが共通の目標を持てず、開発作業に一貫性が欠ける結果となってしまいます。例えば、「現行システムの問題解決」という抽象的な目標しか設定されていない場合、具体的にどの業務をどの程度改善すべきかが不明確になり、適切なシステム設計ができません。
このような状況では、開発途中で仕様変更が頻発し、プロジェクトの予算とスケジュールが大幅に悪化する可能性が高くなります。また、システムが完成しても期待していた効果が得られず、投資対効果の低いシステムとなってしまうリスクもあります。つまり、導入目的が不明確だと、システムの評価基準も曖昧になり、プロジェクトの成功・失敗を適切に判断することも困難になってしまうのです。
このような問題を防ぐためには、プロジェクト開始前に具体的で測定可能な目標を設定することが求められます。業務効率を何パーセント向上させるのか、処理時間をどの程度短縮するのか、コストをいくら削減するのかといった定量的な目標を明確に定義しましょう。これらの目標を関係者全員で共有し、プロジェクト期間中も定期的に進捗を確認する仕組みを構築することも併せて必要となります。
小売業の企業が「現行システムを刷新したい」という曖昧な理由だけで導入を進めたところ、完成後に「在庫管理の精度が改善されない」「売上分析に必要な機能が不足している」といった不満が噴出。結果的に高額な投資に対して効果が得られず、再び追加開発を余儀なくされました。
導入目的が明確でない場合、プロジェクトメンバーが共通の目標を持てず、開発作業に一貫性が欠ける結果となってしまいます。
選定したシステムやベンダーが自社と合致していない
基幹システム再構築における重大な失敗要因として、システムの内容やベンダーが自社に合っていない場合、失敗を招く恐れがあるということも挙げられます。
業界特有の業務フローを理解していないベンダーを選定したり、自社の規模や要件に適していないシステムを導入したりすることで、期待した効果を得られないケースが多発してしまうのです。例えば、製造業特有の複雑な生産管理プロセスを理解していないベンダーが提案するシステムでは、現場の実務に適合しない可能性があります。
その上、ベンダーの技術力不足や対応体制の不備により、開発が遅延したり、品質の低いシステムが納品されたりするリスクもあります。さらには、導入後のサポート体制が不十分な場合、システムトラブル時の対応が遅れ、業務に深刻な影響を与える可能性があります。
このような問題を避けるためには、ベンダー選定時に十分な調査と評価を行うことが重要です。候補となるベンダーの過去の実績、特に自社と類似した業界・規模での導入事例を細かく確認しましょう。ベンダーのサポート体制や技術者のスキルレベル、プロジェクト管理能力なども総合的に評価し、長期的なパートナーシップを築けるベンダーを選定することが成功の鍵となるのです。
ある中小製造業では、金融業向けに実績のあるベンダーに依頼したところ、製造現場特有の生産計画や在庫管理のノウハウが不足しており、現場では「使えないシステム」と評価されました。導入後に追加カスタマイズを繰り返すことになり、コストも納期も大幅に膨らんでしまいました。
現行システムの改修が基準で原因の根本的な解決にならない
既存の基幹システムと比較してしまい、その改善が目標となってしまっているケースも見受けられます。現行システムの問題点を部分的に改善することに焦点が当てられ、抜本的なシステム刷新の機会を逃してしまう結果となりかねません。結局は既存システムの制約や設計思想から完全に脱却できず、新しい技術やビジネス要件に対応できないシステムが構築されてしまうでしょう。
本来システム入れ替えを検討するに至るのは、使用していたシステムの仕様やサポートなどへの限界に起因しているため、既存基幹システムの改善では原因の根本的な解決にはなりません。表面的な改善にとどまってしまうことで、数年後に再び同様の問題が発生し、追加的なシステム改修が必要になる可能性が高くなるのです。
この問題を解決するためには、現行システムの改善ではなく、将来のビジネス戦略に基づいたシステム再構築の必要性を明確に定義することがポイントです。なかなか理解を得られない経営層に対しては、抜本的なシステム刷新の価値と必要性を適切に説明し、根本的な解決策への理解を得る必要があります。また、ベンダーに対しても、既存システムの延長線上ではない、革新的なソリューションを求めることが重要となります。
ある商社では、古い在庫管理システムを「既存の仕組みに少し機能追加」する形で再構築したところ、結果的に古い仕組みの制約に縛られ続け、新しいEC連携やデータ分析基盤を取り入れられませんでした。数年後に再び全面刷新が必要となり、二重の投資を余儀なくされました。
現行システムの問題点を部分的に改善することに焦点が当てられ、抜本的なシステム刷新の機会を逃してしまう結果となりかねません。
基幹システム再構築の失敗を避けるための5つのポイント

基幹システム再構築プロジェクトを成功に導くためには、失敗を避けるためのポイントを考慮し、体系的な戦略を練ることが不可欠です。
ここからご説明する5つのポイントは、多くの成功事例で共通して見られる重要な要素であり、これらを適切に実行することで基幹システム再構築プロジェクトの成功確率を大幅に向上させることができます。なお各ポイントは相互に関連しており、総合的な取り組みが推奨されます。
①導入を推進する組織体制を確立する
基幹システム再構築プロジェクトの成功には、要件定義や複数のベンダーとの打ち合わせ、業務内容の整備などで多くの手間がかかるため、適切な組織体制の構築が不可欠です。プロジェクト責任者を明確に設定し、経営層からの十分な権限委譲を受けることで、迅速な意思決定と関係部門間の調整を可能にする必要があります。また、各業務部門から代表者を選出し、プロジェクトチームに参画させることで、現場の実情を反映したシステム設計を実現できるでしょう。
プロジェクトマネージャーには、ITに関する専門知識だけでなく、業務プロセスへの深い理解と調整能力を持つ人材を配置することが求められます。変更管理やリスク管理の専門家も体制に含めることで、プロジェクト期間中に発生する様々な課題に適切に対応できるようになります。
また、定期的なステアリングコミッティを開催し、プロジェクトの進捗状況や重要な意思決定事項について経営層と共有する仕組みも構築する必要もあります。組織体制の確立により、プロジェクト全体の統制が効き、効率的な推進が可能になるのです。
②導入の目的やゴールをはっきりさせる
基幹システム再構築プロジェクトにおいては、具体的で測定可能な目標設定が必要となります。単に「業務効率化」や「コスト削減」といった抽象的な目標ではなく、「受注処理時間を50%短縮する」「在庫管理精度を95%以上に向上させる」といった定量的な目標を設定することが重要です。これらの目標は、現状分析に基づいて設定され、達成可能性と挑戦的な水準のバランスを考慮する必要があります。
目標設定においては、短期的な効果だけでなく、中長期的なビジネス戦略との整合性も確保することが重要です。例えば、将来の事業拡大に対応できる拡張性や、新しいビジネスモデルへの対応力なども目標に含めると良いでしょう。
また、定量的な目標と併せて、従業員満足度の向上や顧客サービスの質的改善といった定性的な目標も設定し、総合的な成功指標を構築することが推奨されます。自社の現状を踏まえて新システム導入の目的を明確にし、方針がブレないように社内で共有することにより、全員が共通の理解を持ち、一貫した方向性でプロジェクトを推進することが可能になります。目的とゴールの明確化は、その後の要件定義やベンダー選定の指針となるのです。
③システムに必要な要件を整理・定義する
成功する基幹システム再構築プロジェクトでは、システムに求める要件を洗い出しておくことも必須です。機能要件だけでなく、性能要件、セキュリティ要件、運用要件、保守要件など、システムのあらゆる側面について明確に定義しましょう。また、現在の業務要件だけでなく、将来的な事業成長や環境変化に対応できる柔軟性も要件に含めることが大切です。
要件定義は、その後の導入プロセスで手戻りが発生しないように時間をかけて丁寧に行うことがポイントで、十分な期間と人的リソースを投入し、詳細な要件定義書を作成しましょう。適切な要件定義により、開発段階での仕様変更や認識違いを最小限に抑えることで、効率的なプロジェクト推進が可能となります。
④ベンダーとの問い合わせや打ち合わせを重ねる
基幹システム再構築の成功には、ベンダーとの密接なコミュニケーションが不可欠となります。ベンダーに自社の導入目的や要件を示し、導入によって実現したいことを正しく伝え、定期的かつ体系的な情報共有の仕組みを構築する必要があります。単発的な打ち合わせではなく、プロジェクトの各段階において継続的なコミュニケーションを維持することで、認識のズレや仕様の誤解を防ぐことができます。
ベンダー選定段階では、複数の候補業者との詳細な技術的討議を通じて、自社の要件に対する理解度と提案力を評価すると良いでしょう。加えて、過去の類似プロジェクトでの実績や、開発チームのスキルレベルについても詳細に確認する必要があります。契約後は、定期的なプロジェクト会議、進捗レビュー、課題解決セッションなどを通じて、プロジェクトの健全な進行を確保しましょう。
忘れてはいけないのが、技術的な課題や仕様変更の必要性が発生した際の迅速な対応体制を構築することです。要求がうまく伝わらないと、思うように導入が進まないことがあるため、明確なコミュニケーションプロトコルを確立し、文書による確認と承認プロセスを徹底しましょう。ベンダーとの良好な協力関係は、プロジェクト成功に直結します。
⑤システムの構築・稼働を実施する
システム構築・稼働段階では、計画的で段階的なアプローチが成功の鍵となります。実装からリリースまでは、システムの規模にもよりますが一般的に3〜9ヶ月ほどの期間を要します。
特に重要なのは、現行システムからのデータ移行プロセスです。これまで蓄積してきたデータをシステム入れ替え後もそのまま使えるかどうか、必ず確認しましょう。
テスト段階では、単体テスト、結合テスト、システムテスト、ユーザー受入テストの各段階を体系的に実施し、品質を確保しましょう。テスト期間中は従来の基幹システムとの併用運用となり、新基幹システムに問題がなく安定して動作できることが確認でき次第、移行となります。
稼働開始後の運用支援体制も重要で、システム管理者の育成、ユーザー研修の実施、トラブル対応手順の整備などを通じて、安定的な運用基盤を構築することも大切です。継続的な改善活動を通じて、システムの価値を最大化し、投資対効果の向上を図ることが、真の意味でのプロジェクト成功につながるのです。
基幹システムならオーシャン・アンド・パートナーズにご相談を
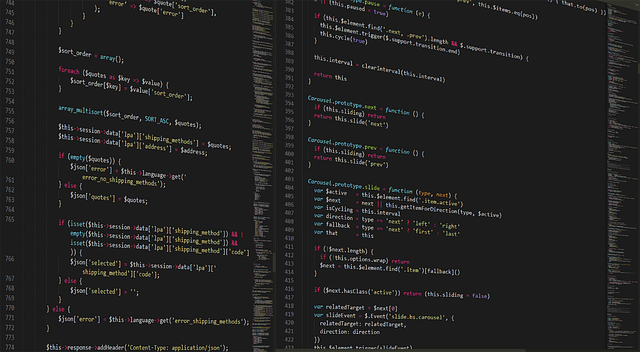
基幹システムの再構築をご検討の企業様には、オーシャン・アンド・パートナーズが最適なソリューションを提供いたします。特定のメーカーや分野に偏らず、進化する技術を幅広くキャッチアップし、お客様にとって本当に必要な選択肢をご提案することで、最適なシステム構築を実現しているのが特徴です。
さらに、お客様の「やりたいこと」から、逆算して考えるアプローチにより、技術ありきではなく真のビジネス価値創出を目指します。組織・業務・仕組み・テクノロジーを横断的に捉え、全体最適を見据えた支援により、複雑な課題を解決し、事業全体にとって意味のある変化を実現します。基幹システム再構築の成功に向けて、ぜひオーシャン・アンド・パートナーズまでお気軽にご相談ください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
この記事を書いた人について
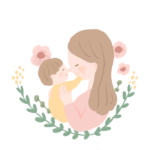
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。