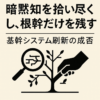ベンダー選定基準を設けることが重要な理由とは?選定の流れや選定基準のポイントを解説

新しいシステムの導入や既存システムの刷新を検討する際、多数のベンダー候補から最適な1社を選ぶことは企業の将来を左右する重要な決断となります。しかし、明確な基準を設けずに感覚的にベンダーを選定してしまうと、プロジェクトの失敗につながるリスクは避けられません。
しかし実際には、提案内容やシステムの良し悪しをどのように評価して良いか分からず、評価基準が曖昧な状態のまま選定を進めてしまうケースが非常に多くなっているのが現状です。そこで、適切なベンダー選定基準を設けることで、客観的な評価が可能となり、プロジェクトの成功確率を大幅に向上させることができるのです。
本記事では、ベンダー選定の基本概念から具体的な選定プロセス、そして評価基準のポイントまでを詳しく解説していきます。ベンダー選定でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談する目次
ベンダー選定とは?

ベンダー選定とは、システム開発やIT導入において、自社の要求に最も適したシステム開発会社やソリューション提供会社を選び出すプロセスのことです。候補となる複数のベンダーから提案を募り、それらを比較・評価して最終的な発注先を決定する一連の活動を指します。
新しいシステムの導入や古いシステムの刷新、システム統合等を検討する際は、候補となるベンダー各社から提案を募り、その提案内容を比較・評価して発注先を決定する「ベンダー選定」のプロセスが欠かせません。このプロセスでは、技術的な能力だけでなく、コスト面、サポート体制、納期対応力など多角的な観点から評価を行います。適切なベンダー選定は、プロジェクトの成否を左右する極めて重要な要素となっているのです。
ベンダー選定基準を設けることが重要な理由

明確なベンダー選定基準を設けることは、プロジェクト成功のための必須条件です。基準がない状態でのベンダー選定は、感情的な判断や偏った評価につながりやすく、結果として大きなリスクを抱えることになります。
基準を明確にすることで、特定事業者への肩入れを防いで適切なベンダーを選定できるようになるため、プロジェクトの成功可能性が高くなります。一方で、基準を設けずにベンダーを選んだ場合、想定していたシステムと異なる仕上がりになったり、大幅な予算オーバーが発生したりするなど、様々なトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
明確な基準があることで社内での合意形成もスムーズになり、選定プロセスの透明性と説明責任を確保することができるのです。
ベンダー選定について詳しくはこちら
ホワイトペーパー「RFPが鍵!!ベンダ選定でプロジェクトの成否は8割決まる」
ベンダー選定の流れ

ベンダー選定は段階的なプロセスを経て進められます。各段階で適切な準備と評価を行うことで、より精度の高い選定結果を得ることが可能となります。ベンダー選定・評価は一般的に「事前調査」「RFI(情報提供依頼)」「RFP(提案依頼)」「評価・交渉・契約』といった複数の工程に分けられます。
ここからは便宜上、大きく「事前調査フェーズ」「検討準備フェーズ」「評価・選定フェーズ」の3工程として解説します。各フェーズでは異なる目的と作業内容があり、順序立てて実行することで効果的な選定が実現できるでしょう。
①事前調査
事前調査フェーズでは、市場にどのようなベンダーが存在するかの全体像を把握することから始めましょう。まず、自社の要件に合致する可能性のあるベンダーをリストアップし、各社の基本情報、事業規模、技術領域、実績などを収集します。この段階では、ベンダーの公開情報やWebサイト、業界レポートなどから情報を集め、候補を絞り込んでいきます。
また、業界内での評判や他社での導入事例なども調査し、各ベンダーの強みや特徴を把握することも大切です。RFI(情報提供依頼書)を活用して、より詳細な情報を収集することも有効です。さらに、自社の予算規模や要求水準に見合わないベンダーを早期に除外することで、後続の選定作業を効率化することができます。
この事前調査により、目安として5~10社程度の候補ベンダーに絞り込み、次の選定準備フェーズへと進みます。調査の精度が高いほど、最終的な選定結果の質も向上するため、十分な時間をかけて実施することが重要です。
②選定準備
選定準備フェーズでは、ベンダーからの提案を適切に評価するための基盤を構築します。まず、RFP(提案依頼書)を作成し、自社の要件や期待する成果物を明確に定義します。RFPには、システムの機能要件、非機能要件、予算範囲、納期、評価基準などを詳細に記載し、全候補ベンダーに同じ条件で提案を求めることがポイントです。
同時に、ベンダー評価のための評価項目と配点を設定します。技術力、コスト、納期、サポート体制、プロジェクト推進力など、自社が重視する観点を明確にし、それぞれに適切な重み付けを行います。評価を実施する社内メンバーの役割分担も決定し、評価プロセス全体のスケジュールを策定しましょう。
さらに、候補ベンダーからの質問に対応するための体制を整え、必要に応じて説明会や現地調査の機会を設けます。この準備が充実しているほど、ベンダーからより質の高い提案を引き出せる可能性が高まります。
③評価・選定
評価・選定フェーズでは、収集した提案書やプレゼンテーションを基に、事前に設定した評価基準に従って各ベンダーを点数化していきます。書面評価だけでなく、プレゼンテーション評価、デモンストレーション、場合によってはPoC(概念実証)なども実施し、多面的な評価を行います。評価結果は客観的な数値として算出し、評価者間での認識の違いを最小限に抑えましょう。
最終選考では、上位候補との詳細な条件交渉を行い、コストや契約条件の最適化を図ることが重要です。また技術的な詳細確認や、実際の開発体制、プロジェクト管理手法などについても深掘りして確認します。選定理由を明文化し、社内の意思決定者への報告と承認を得て、最終的な契約候補の決定に至ります。
選定結果については、選ばれなかったベンダーに対しても適切なフィードバックを提供し、今後の関係性を考慮した丁寧な対応を心がけましょう。契約交渉を経て最終合意に至れば、プロジェクト開始へと進んでいきます。
ベンダー選定基準のポイント

ここまででも少し触れてきましたが、効果的なベンダー選定を実現するためには、評価すべき観点を体系的に整理し、自社の状況に応じた適切な基準を設定することが不可欠です。
評価観点は大きく「企業側の観点」と「提案内容の観点」に分けて考えることができ、それぞれに重要な評価項目が存在します。各評価項目に対して明確な判定基準と配点を設定し、評価者による主観的なばらつきを最小限に抑えることが目的となります。詳しく見ていきましょう。
企業側の観点
企業側の観点では、ベンダー自体の安定性や信頼性、そして技術的な実力を評価しましょう。これらは、長期的なプロジェクト推進や将来的なシステム保守・運用において極めて重要な判断材料となります。
なお、単発的な開発能力だけでなく、継続的なパートナーシップを築けるかどうかの視点で評価することが求められます。
経営の安定性・継続可能性
ベンダーの経営状況は、プロジェクトの継続性と品質保証に直結する重要な要素です。財務諸表による売上高、利益率、自己資本比率などの財務指標を確認し、事業の安定性を評価します。
事業継続性の観点から、主力事業の収益構造や顧客基盤の多様性も判断材料となります。経営陣の安定性や事業戦略の一貫性についても、可能な範囲で確認しておくと良いでしょう。
さらに、コンプライアンス体制や情報セキュリティ対策の整備状況も、現代のビジネス環境においては不可欠な評価項目です。ISO27001などの認証取得状況や、過去のセキュリティインシデントの有無なども含めて総合的に判断することが必須といえます。
技術力・導入実績
ベンダーの技術的能力は、プロジェクトの成否に直接影響する最も重要な評価項目の一つです。保有技術の範囲と深さ、最新技術への対応力、類似プロジェクトでの実績などを多角的に評価しましょう。
技術者のスキルレベルについては、保有資格、経験年数、過去のプロジェクト実績などから総合的に判断します。プロジェクトに実際にアサインされる予定のメンバーの経歴やスキルセットを具体的に確認し、要求される技術レベルとの適合性を評価することも必要です。
また、技術的な課題解決能力や提案力も重要な評価ポイントとなります。RFP回答やプレゼンテーションにおいて、自社の課題を正しく理解し、適切な技術的解決策を提示できているかを確認しましょう。加えて、将来的な技術進歩への対応力や、継続的な技術習得への取り組み姿勢も長期的なパートナーシップを考える上で考慮したいところです。
提案内容の観点
提案内容の観点では、実際にベンダーから提示された提案の質と実現可能性を評価します。コストや納期といった定量的な要素から、提案の創意工夫や実現性といった定性的な要素まで、幅広い視点での評価が必要となります。
提案内容の評価では、単純な比較だけでなく、自社の要件との適合度や将来的な拡張性なども視野に入れましょう。
初期費用・運用コスト
コスト面では、単純な価格比較ではなく、総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)の観点から行うことをおすすめします。初期開発費用だけでなく、導入後の運用・保守費用、将来的な機能拡張費用、そして隠れたコストまで含めて総合的に評価することが求められます。
コストの妥当性については、市場相場との比較や、提供される価値との対比で判断しましょう。極端に安い提案については、品質面でのリスクや後から追加費用が発生する可能性について十分に検証する必要があるので注意が必要です。
また、支払い条件や変更時の追加費用の算定方法についても事前に明確化しておきましょう。プロジェクトの途中で仕様変更が発生した場合の対応方針や、追加工数の単価設定などについても確認し、予算管理の観点から適切な契約条件を検討しておくと安心です。
要件の現実性
ベンダーからの提案が、自社の要件を正しく理解し、現実的な解決策を提示しているかを評価することも欠かせません。機能要件への対応度合いはもちろん、非機能要件(性能、セキュリティ、可用性など)についても具体的な実現方法が示されているかを確認しましょう。
技術的に困難な要件について、実現可能な代替案や段階的な実現方法が提案されているかどうかは特に評価すべきポイントといえます。要件の理解度については、RFPに記載された内容だけでなく、その背景にあるビジネス課題や目的を理解しているかどうかも判断材料となります。表面的な機能実装だけでなく、根本的な課題解決につながる提案がなされているかを評価することが必要です。
さらに、将来的な事業成長や変化に対応できる拡張性や柔軟性が考慮されているかもチェックしておきたいところです。現在の要件を満たすだけでなく、将来的なニーズの変化に対応できるアーキテクチャや実装方法が提案されているかを確認し、長期的な視点での適合性を評価すると良いでしょう。
納期計画と現実性
提示された納期計画の実現可能性と合理性も評価すべき点です。プロジェクト全体のスケジュールが適切かどうかや、各工程の作業量と期間が現実的に設定されているかを確認します。特に、要件定義、設計、開発、テスト、導入といった各フェーズの期間配分は重要な判断材料となります。
リスク管理の観点から、スケジュール遅延要因の識別とその対策が適切に計画されているかも評価項目となりえます。バッファ期間の設定、並行作業の可能性、クリティカルパスの管理など、プロジェクト管理手法の妥当性についても確認が必要です。
また、自社側の作業や意思決定のタイミングが適切に考慮されているかも忘れてはいけません。ユーザーレビューや承認プロセス、テストデータの準備など、発注者側の対応が必要な作業についても現実的なスケジュールが組まれているかを評価し、双方の協力体制での実現可能性を判断することが求められます。
開発体制の妥当性
プロジェクトに割り当てられる開発チームの構成と体制が、プロジェクトの規模と複雑さに適しているかも必須事項です。プロジェクトマネージャーの経験値、システムエンジニアやプログラマーのスキルレベル、各専門分野の技術者の配置など、チーム編成の妥当性を確認します。類似プロジェクトでの経験を持つメンバーがどの程度含まれているかも確認しましょう。
品質管理体制についても詳細な確認が必要です。コードレビューの実施方法、テスト体制の整備、品質保証プロセスの確立など、品質を担保するための仕組みが適切に構築されているかという点はもちろん、プロジェクト管理ツールや開発環境の整備状況も、効率的な開発推進の観点から必須要素となります。
さらに、コミュニケーション体制や報告体系についても確認が必要です。定期的な進捗報告の方法、課題やリスクの共有方法、意思決定プロセスなどが明確に定義されているかを評価し、円滑なプロジェクト推進が期待できるかを判断しましょう。
保守・サポート体制の信頼性
システム稼働後の保守・サポート体制は、長期的なシステム運用の品質と安定性の要となる要素です。障害対応体制、定期メンテナンスの実施方法、システム監視体制など、運用フェーズでの対応力を詳細に評価すべきです。特に、24時間365日対応が必要なシステムの場合、サポートデスクの体制や緊急時の対応手順が適切に整備されているかが重要な判断基準となるでしょう。
技術的なサポート能力についても確認が必要です。システムの深い理解を持つエンジニアが保守チームに含まれているか、新技術への対応やシステム拡張時のサポート能力があるかなどを評価します。また、保守作業の品質を担保するためのプロセスや、継続的な改善活動への取り組みについても確認しましょう。
さらに、ユーザーサポートの充実度も評価ポイントとなります。操作マニュアルの提供、ユーザー研修の実施、問い合わせ対応の迅速性など、エンドユーザーの満足度向上に向けた取り組みが適切に計画されているかを確認し、システム導入後の円滑な運用開始を支援する体制が整っているかを判断する必要があります。
提案・説明スキル
ベンダーの提案書作成能力やプレゼンテーション能力は、プロジェクト期間中のコミュニケーション品質を予測する指標です。提案書の構成や内容の論理性、図表の活用による分かりやすさ、専門用語の適切な使用など、文書作成スキルの高さを評価しましょう。また、自社の課題や要件を正確に理解し、それに対する適切な解決策を明確に示しているかも重要な判断材料となります。
プレゼンテーション能力については、聞き手に応じた適切な説明レベル、質問への的確な回答、時間管理能力などを総合的に評価します。特に、技術的な内容を非技術者にも理解しやすく説明できる能力は、プロジェクト関係者との円滑なコミュニケーションに直結する可能性が高く重要度が高いです。
提案内容の独創性や付加価値の高さも評価対象です。単純に要求仕様を満たすだけでなく、自社のビジネス価値向上につながる創意工夫された提案がなされているかを確認することがポイントです。業界知識の深さや他社事例の活用など、豊富な経験に基づく価値ある提案が期待できるかを判断しましょう。
プロジェクトへの取り組み姿勢
ベンダーのプロジェクトに対する姿勢と意欲は、プロジェクト成功に大きく影響する要素です。提案書や面談を通じて、プロジェクトに対する熱意や責任感、困難な課題に対する積極的な取り組み姿勢などを評価しましょう。特に、単なる受託開発ではなく、パートナーとしてプロジェクト成功にコミットする意識があるかは大きな判断基準となります。
リスク管理に対する姿勢も評価ポイントです。プロジェクトで想定されるリスクを適切に識別し、その対策を事前に検討しているか、問題発生時の迅速な対応体制が整備されているかなどを確認しましょう。変更要求への柔軟性や、予期せぬ課題に対する解決提案力などが、プロジェクトの成否に関わると言っても過言ではありません。
さらに、継続的な改善への取り組み姿勢や、新しい技術や手法への学習意欲なども長期的なパートナーシップを考える上で不可欠です。プロジェクト期間中だけでなく、システム稼働後も含めた長期的な関係構築への意欲があるかを評価し、持続可能なパートナーシップが期待できるかを判断しましょう。
基幹システムならオーシャン・アンド・パートナーズにご相談を
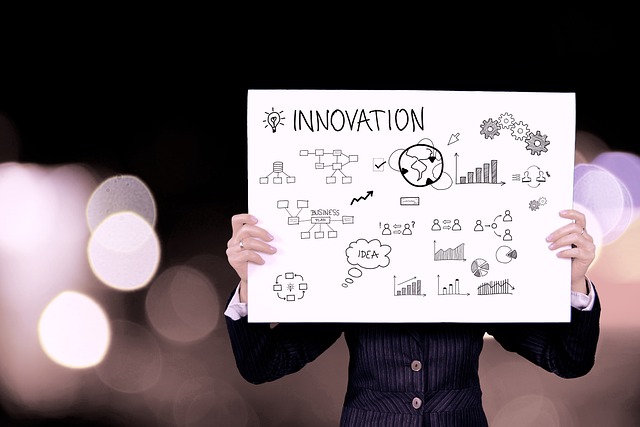
本記事では、ベンダー選定にかかわる流れや選定基準ポイントを詳しくお伝えしてきました。ベンダー選定でお悩みであれば、製造・流通・医療・金融など、幅広い業界で得た成功事例をもとにオーシャン・アンド・パートナーズが最適なソリューションを提供いたします。
固定観念にとらわれず、外部の視点で本質的な改善を提案することを念頭におきながら、戦略的なRFP策定から候補比較や最終交渉まで一貫して伴走し、最適なベンダー選定を支援します。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談するこの記事を書いた人について
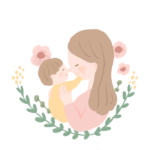
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。