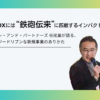RFP(提案書)の書き方をサンプル付で徹底解説!作成の目的やメリットデメリットとは?

企業のシステム開発などの際によく出てくる「RFP」とは、日本語では「提案依頼書」と訳されます。
「システム開発を外注する予定だから、RFPの作成をお願い。」と言われても、「何を書けばよいのか?」と悩んだことがある企業の担当者はいるのではないでしょうか。
ここでは、RFPの必要性をはじめ、サンプル付でRFPの書き方を解説します。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談する
目次
RFP(提案書)とは?目的やRFIとの違いを解説

RFP(提案依頼書)とは、企業が自社システムなどを開発またはリプレイスする際に、外部のSIerやITベンダーに委託する際に、活用する資料です。
RFPは外部発注したい内容についてまとめられており、これを元にSIerなどが出した提案書を比較検討します。
ここでは、RFPの目的や必要性などについて見ていきましょう。
RFP(提案書)とは?
RFPとは「Request for Proposal」の略で、日本語では「提案依頼書」と記されます。
主に企業が自社のシステムなどの開発やリプレイスをSIerやITベンダーに委託する際に、発注側の企業が依頼内容や要件を正しく伝えるための資料です。
RFPは委託企業がどのような要件や求めるアウトプットについての情報が詳しく記載されています。このRFPに沿ってSIerやITベンダーは委託企業に見積りや納期などを含めた提案内容を提示します。
特に、企業が大規模なシステム開発などをする際は、発注側が自社の要件や予算に合った最適な提案をするITベンダーを選定するために重要なツールと言えます。
RFP(提案書)の目的
RFPの目的は、主に次の3つです。
1つ目は、依頼内容や要件を正確に伝えることです。口頭だけでは、それぞれの思い込みや解釈により情報が正しく伝わるとは限りません。文書に書き出すことで、要件を漏れなく伝えられます。
2つ目は、発注側と受注側の間での認識のズレを防ぐためです。1つ目の目的と共通する部分がありますが、文書に残さず口頭だけでのやり取りになると発注側と受注側での認識のズレや要件の抜け漏れが発生してしまいます。
3つ目は、発注候補のSIerやITベンダーに対して平等に情報提供することです。同じ量と質の情報提供ができなければ、発注先を検討する際に、情報の差異が発生してしまうため、平等に検討することは難しいでしょう。
RFP(提案書)とRFIの違い
RFPと似た用語でRFI(Request for Information:情報提供依頼書)というものがあります。これは、発注側の企業がSIerやITベンダーに対して、会社情報の他に開発実績や持っている技術、製品情報の提示を求める文書のことです。
この文書で発注側の企業が求めるものは、ウェブサイトやパンフレットなどには掲載されてないことが多い内容が中心です。
これをSIerやITベンダーに出すことにより、表面的な情報以外のものが得られます。各社がどのような業種業界に強いのか、どの技術分野が得意で技術者をどのぐらいかかえているのか、などを知ることができ、自社のニーズに合った委託先を探すのに役立ちます。
RFP(提案書)を作成するメリットデメリット

前述のとおり、RFPの作成はシステム開発やリプレイスの成功に欠かせないものの1つと言っても過言ではありません。
ここでは、RFPを作成することのメリットとデメリットについて見ていきましょう。
RFP(提案書)を作成する3つのメリット
RFPを作成することのメリットは主に3つあります。それぞれのメリットについて、ポイントをご紹介します。
①自社の要望を正確に伝達できる
RFPを作成することで最も得られるものは、相手に「正確な情報を伝達できる」ことです。
用語とは個人や企業ごとに定義や解釈が異なる場合があります。お互いが1つの用語に対して定義や解釈が違う状態で話を進めてしまうと必ず認識のズレが生じるでしょう。RFPを作成することで、共通認識のベースが出来上がります。
②自社の現状や課題を見直せる
RFPを作成する時には、プロジェクトの目的やアウトプット、システムの仕様、予算や納期、その他要望をまとめます。
相手に正確に情報を伝達するだけでなく、作成プロセスの中で自社の現状を改めて確認したり、課題を見直したりも可能です。作成プロセスの段階で、社内でよく議論して作成することで、SIerやITベンダーからの提案内容の質も上がるでしょう。
③複数のベンダーを効率良く評価できる
RFPの内容は発注側と受注側の共通言語となります。また、SIerやITベンダーに同じ量と質の情報を提供することで、提案される範囲にズレがなく、比較検討しやすい提案書が揃います。
発注側の企業はRFPを元にそれぞれの項目について検討すればよいため、提案書を効率良く比較検討することが可能です。
「基幹システム再構築の成功法則大全(10ページ目参照)」では、ベンダー選定のポイントについて紹介しています。
RFP(提案書)を作成するデメリット
一方で、RFPを作成することで受けるデメリットは主に次のようなものです。
(1)作成に時間と手間がかかる
(2)RFPに記載がない追加要件の発生は工数の増加につながる
1つ目はRFPの作成に時間と手間がかかる点です。RFPの作成には関連する部署や担当者からもヒアリングし、要件をまとめなければなりません。内容の重複や漏れがないように記載しなければならないため、相当の時間と手間を要します。しかしRFPの作成はシステム構築に不可欠なプロセスであり、この段階に時間がかかったとしても、結果的には全体の進行をスムーズにし、むしろ効率を高める効果もあります。
2つ目はRFPに記載されていない追加要件の発生は工数の増加につながります。RFPをSIerやITベンダーに提出した後、各社は相当の時間をかけてRFPの内容に沿う提案書を作成します。そのため、RFP作成段階で漏れてしまった要件の追加要求は提案書の練り直しにつながるため、想定していたスケジュールから逸れてしまう可能性が高くなるでしょう。しかしRFPの作成はシステム構築に不可欠なプロセスであり、この段階に時間がかかったとしても、結果的には全体の進行をスムーズにし、むしろ効率を高める効果もあります。
RFP(提案書)の作成の流れ

RFP(提案依頼書)の作成には、いくつかの重要なステップがあります。
まずは、社内でプロジェクトチームを発足することから始めます。システム開発などの大規模なプロジェクトでは、関係部門が多岐にわたるため、チーム体制で進行することが一般的です。チーム内では、現在抱えている課題を丁寧に洗い出し、それをもとにプロジェクトの目的を明確化します。
目的の共有が不十分なままプロジェクトを進めてしまうと、後々の仕様のブレや委託先との認識齟齬につながるため、初期段階での丁寧な整理が非常に重要です。
次の段階では、委託先候補となる企業の情報収集を行います。各社の実績や専門性、対応領域などを調べながら、プロジェクトに適したパートナーを絞り込んでいきます。また、どのような観点で委託先を評価するかといった基準もこの段階で設定しておくと、選定時の判断がブレにくくなります。
こうした下準備が整ったら、いよいよRFPの作成に取りかかります。プロジェクトの概要、求める成果物、スケジュール、予算、評価基準などを具体的に記載し、委託先候補企業へ提示します。RFPは、企業のニーズを正確に伝え、最適なパートナーと出会うための重要な文書です。
RFP(提案書)概要の書き方【サンプル付】

ここからは、RFPの「概要」の書き方について解説します。
概要に記載することは、自社の情報やRFPの目的にはじまり、プロジェクトの背景、自社の課題やゴールが何か、ということです。ひとつひとつ見ていきましょう。
表紙
表紙にはプロジェクトの中身が分かりやすいように表題を書きましょう。その他は会社名を書いておけば、表紙として問題ありません。
| [プロジェクト名]提案依頼書(RFP) 本書は、[株式会社ABCソリューション]が実施する[プロジェクト名]に関して、システム・サービス選定にあたって提案を依頼するための資料です。 発行日:2025年04月30日 |
RFPの目的
次に書くことはRFPの目的についてです。委託先候補企業がRFPに目を通した時に全体像が分かりやすいようにRFPの位置づけを明確にしておきましょう。
| 現在、[株式会社ABCソリューション]では[目的:例「営業活動の効率化」「社内業務のDX推進」など]を目的として、[対象システム・サービス]の導入を計画しています。 本書(以下、RFP)は、ベンダー各社様に対し、当社の背景や要件を開示し、貴社にてご提案いただく際の指針となるものです。 当社は、本書をもとに貴社のご提案を受け、本プロジェクトの委託先選定を行う予定です。 |
プロジェクトの背景
なぜプロジェクトが発足されたのかを書きましょう。自社が何を解決したいのか、何を実現させたいのかを相手に伝えるためにも背景は重要な情報です。
|
[現状の業務状況や課題の兆候を簡潔に記載:例「エクセルによる情報管理の限界」「属人化した業務運用」「対応ミスやクレームの増加」など] こうした状況を踏まえ、業務全体の見直しと効率化を目的に、[システム名やプロジェクト名]の導入を検討しています。 |
現状の課題
自社が解決したいこと、実現したいことに向けてのハードルが何なのか、RFP作成段階で関係者へヒアリングしたことや要件を漏れなく書いておきましょう。
つらつらと書いてしまうとまとまりがなく要点が分からないため、箇条書きにしたり、図表を用いたりして情報を整理して書くことがポイントです。
(例)
|
システム導入の目的
今抱えている課題を解決するため、また、得たい効果について具体的に記しましょう。
この実現させたいこと、解決したいことが明確に言語化できるかがプロジェクト成功のカギの1つです。
※各目的の背景や期待する効果も任意で補足してください。 |
プロジェクトのゴール
プロジェクトのゴールは、品質(Quality)と費用(Cost)、納期(Delivery)の観点から定量的な指標を使って設定しましょう。
プロジェクト後に成果を見たり、評価したりする際に、定量的な指標を設定しておくことで評価しやすくなります。
また、企業のビジネスのデジタル化が進む現在、ITシステムは「業務効率化」から「ビジネスへの貢献」が求められるようになりました。前述のホワイトペーパーでは、IT投資の中身の変化についても紹介しています。(16ページ目参照)
|
プロジェクトの範囲
RFPではプロジェクト範囲を明確に記しましょう。プロジェクト範囲は予算やスケジュールにも関わる項目です。
また、自社でやる範囲があるのか、すべてを委託先に依頼したいのか、範囲を明確にしなければ、SIerやITベンダーから提示される提案内容にばらつきが生じてしまいます。
提案内容の精度を高めるためにもプロジェクト範囲はしっかりと記しましょう。
|
自社の会社概要
自社の売上高や資本金、代表者や従業員数、組織構成などについて明記します。会社のウェブサイトのURLを記載しておくのも良いでしょう。
開発対象のシステムを実際に運用する際にシステム管理者や利用者の権限設定が必要な場合は、組織図は必ず添付しましょう。
|
現行のシステム構成
現行のシステム構成を図表やシステムフロー図を用いて書きましょう。新システムに切り替える際、現行システムにどこに影響が及ぶのかなどを把握するためにもシステム構成は欠かせません。
開発対象システムが複数にわたる場合、システム間のデータ連携をスクラッチで開発しているのか、ツールを用いているのかなどの情報もあると良いでしょう。
| [現状の業務を支えているシステムやツールを簡単に説明] |
機器情報
現行のシステムで利用しているサーバやPCの数やスペックについても重要な情報です。ハードウェアの調達までを依頼する場合は必ず必要になるため、漏れなく書きましょう。
|
RFP(提案書)提案依頼内容の書き方【サンプル付】

ここまではRFP(提案書)の概要の書き方について説明しました。ここからは、より具体的な内容に踏み込む「提案依頼内容」の書き方について、解説します。
受注側の会社情報
委託先となるSIerやITベンダーの会社情報の情報開示を依頼しましょう。
ここでポイントになるのは、委託先の規模や得意とする業種・業界、どのような技術力を有しているかでしょう。また、欠かせないのは、自社と同じ業種・業界顧客に対しての実績があるかです。自社が属する業界知識などに乏しい場合、依頼した後も認識のズレが生じる可能性もあります。
事前にRFIで委託先企業の情報を取得している場合は、この項目はRFPから外しても問題ありません。
|
本提案に関わる全ての法人・団体名を記載してください。 ※RFIを実施済みの場合は本項目の記載を省略可能です。RFPのみで選定を行う場合は、貴社の業種・実績・強みがわかる資料の添付もお願いいたします。 |
提案システム概要と構成
この項目では、委託先企業からどのように情報を提示してもらいたいか記しましょう。
例えば、提案システムの主要機能の明示や主要機能画面のキャプチャ、その他、ハードウェアの調達まで依頼する場合は必要なスペックの機器情報なども明示してもらいましょう。
| 【概要】 以下の情報をご提示ください。 提案対象システムの主要機能一覧 操作画面の構成イメージ 今後予定されている機能追加の有無と概要 当社の要件との適合性、及び競合他社との比較優位性 【構成】 ネットワーク構成図、およびインフラ構成 オンプレミス/クラウドの別、および提供方式 |
機能要件
機能要件では、開発するシステムにどのような機能を実装してほしいかを具体的に記しましょう。
業務フローに沿いながら、各システムでどのようなことができなければならないかを漏れなく書き込みましょう。
| 以下の機能を含むソリューション提案を求めます。詳細は別紙にて記載しますが、以下の要件を満たす機能概要を記載してください。
例:営業支援システムにおける主な要件 タスクのテンプレート化と通知機能 売上予測の可視化とレポート作成機能 モバイル環境からの入力・閲覧機能 |
プロジェストのスケジュール
プロジェクトのスケジュールは週単位または月単位で、プロジェクトの全体像が分かるように提示してもらいましょう。
また、スケジュールを提示してもらう際は、自社が担当するタスクも明確化して、組み込んでもらうことがポイントです。
| 週/月単位でのプロジェクト全体スケジュールをご提出ください。 各フェーズでの担当(自社/弊社/外注先等)を明示し、役割分担が明確になるようご配慮ください。 |
プロジェクトの体制
プロジェクトの体制は、SIerやITベンダーがどのような体制でプロジェクトを進めるかを確認するために提示してもらいます。
特に、ここでしっかり確認したいのが、プロジェクトマネージャーについてです。プロジェクト全体の管理を担う責任者であり、プロジェクト成功のカギを握る存在の一人です。どのような経歴の人が担当するのか、提示してもらえるようにRFP(提案書)に記しておきましょう。
※PMの実績と適性は重視しています。過去の類似プロジェクトの経験等を記載してください。 |
成果物
プロジェクト内で納めてもらいたい成果物をこの段階で明示しましょう。すでにアウトプットとしてほしいドキュメントなどが決まっていれば、箇条書きでも良いので書き出すことをおすすめします。
また、RFP(提案書)に書いておきたいのが、ドキュメントのサンプル提示です。納品されるドキュメントの品質を事前に確認できるよう、サンプルを提示してもらえるよう記しましょう。
| 本プロジェクトにおいて納品予定の成果物をリスト化してください。 また、可能であれば類似プロジェクトで作成された成果物の一部サンプルをご提示ください。 |
サポート体制
サポート体制とはシステムの稼働後にトラブルなどがあった際、どのような対応がされるかを確認するために必要です。
受付時間やどのような受付方法があるのかなどを明示してもらいましょう。
以下の情報をご記載ください。
|
概算費用はシステム開発時のイニシャルコストと稼働後のシステム運用のサポートなどが含まれるランニングコストに分けて明示してもらうのがポイントです。
また、必ず内訳を記してもらうよう求めましょう。内訳がなく合計額のみの表示だと何にどれくらいかかっているか分かりません。他社と比較検討する際のポイントになったり、金額交渉の要素になったりするため、RFP(提案書)で明示してもらいしょう。
| 初期費用・月額費用をそれぞれ下記のように明示してください。 初期費用:開発費・インフラ費・教育費などの内訳と総額 月額費用:保守・ネットワーク・運用費の内訳と単価 ※合計金額のみの提示ではなく、詳細な内訳を明示してください。 |
制約事項やリスク
制約事項とは システム利用時の同時にアクセスできるユーザー数や発行可能アカウント数、登録データ件数などについてです。これらに制約がある場合、事前に判明していることは明示してもらいましょう。
システムのリリース直前に制約事項があると判明した場合、利用可能枠やアカウント数を増やすために追加費用がかかる可能性もあります。また、スケジュールの遅延にもつながりかねないため、制約事項や考えられるリスクについては、必ず確認しましょう。
本プロジェクトに関して、現在判明している制限事項(例:同時アクセス数制限、拡張不可領域など)がある場合は、必ずご提示ください。 |
契約内容
契約内容は、契約の対応範囲や契約期間、支払い方法や支払いサイクル、瑕疵担保期間など、明示してもらいましょう。
なお、規模の小さい委託先企業との契約は下請法が適用される可能性があります。「60日以内の支払い」など制約もあるため注意しましょう。
|
RFP(提案書)選考の進め方の書き方【サンプル付】

ここからは、RFP(提案書)の「選考の進め方」についての書き方を解説します。
選考の進め方で書くことに難しいことはありませんが、評価基準や方法は事前に社内でじっくり検討することが重要です。
選考スケジュール
選考スケジュールは、自社が期待する回答スケジュールを記載しましょう。一般的なシステム開発提案であれば、2週間程度が目安です。
ただし、一方的な自社都合だけを考えたスケジュールの提示はNGです。多数のSIerやITベンダー側から期間変更を求められた場合は、スケジュールを見直し再提示しましょう。
| 選考は、以下のスケジュールに基づいて進行する予定です。各日程においてご都合がつかない場合は、事前にご相談ください。
※スケジュールは調整の可能性があります。 |
提案書提出先
提案書提出先に記載するのは、「いつまでに」「誰に」「どのような送付方法」で提出すればよいかを記しましょう。
「いつまでに」については時間まで指定することをおすすめします。また、回答期限を過ぎた場合の対応についても記載しておくのが良いでしょう。
| 提案書は以下の宛先へ電子ファイル形式(PDF推奨)でご提出ください。
※期限を過ぎた場合は、選考対象外とさせていただくことがあります。 |
評価基準と方針
SIerやITベンダーからの提案に対して、自社が何を重視して提案内容を評価するのかを記しましょう。明示することで、提案内容が自社の意図に沿った内容が提示される可能性が高まります。
下記のホワイトペーパー(10ページ目参照)では、ベンダーの評価ポイントとして押さえておきたい点について紹介しています。
ホワイトペーパー「基幹システム再構築の成功法則大全」
|
ご提出いただいた提案は、以下の観点から総合的に評価いたします。 1.ソリューション評価
2.マネジメント評価
3.価格評価
4.ベンダー評価
※上記評価項目を基に、選定委員会にて総合判断の上、発注先を決定いたします。 |
RFP(提案書)を作成するうえでの3つのポイント

RFP(提案書)を作成するうえで重要なポイントは、次の3つです。
これらのポイントを押さえてRFPを作成することで、作成したRFPの品質は各段に上がるでしょう。
目的を明確にする
RFP(提案書)の概要に記載するプロジェクトの背景で記載しますが、開発したシステムで自社が何を解決したいのか、何を実現させたいのか、を明確にしましょう。
目的がブレてしまっては、プロジェクトを進めていく中で認識のズレが生じたり、本来のゴールにたどり着かなくなってしまったりする恐れがあります。
システム開発は社内のリソースや時間、お金を使う投資です。リソースや費用をかけたのに使えないシステムになってしまっては開発元とのトラブルに発展してしまうため、RFP作成段階で目的を明確にしましょう。
経営層や管理職・ユーザーなど多くの人から意見を聞く
投資して開発やリプレイスするシステムは、自社の事業を成長させていくために必要なものの1つでしょう。
経営層の話だけでは、実務担当者の課題は解決できません。一方で実務担当者の話だけでは、経営層が目指すものの実現のためのシステムを作り上げることは難しいでしょう。
そのため、社内のさまざまな立場や部門の人からの意見を聞き、RFPに情報として加えましょう。
専門家に相談する
RFP(提案書)の作成経験が少ない企業の担当者は、RFP作成支援などを展開する専門家にアドバイスを求めるのも良いでしょう。
本ホワイトペーパーでは、プロジェクトを成功させるために事前に知っておくべき見えないリスクやシステム開発を委託するベンダーを選定する時の評価ポイントについて紹介しています。
ホワイトペーパー「基幹システム再構築の成功法則大全」
RFPについてのご相談はオーシャン・アンド・パートナーズまで
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社は、企業向けにシステム開発をはじめとしてさまざまなITソリューションを提供しています。多くの企業の基幹システムの刷新やシステム開発の実績を有しています。
当社の特徴は、技術力のあるプロフェッショナル人材とパートナーシップを組み、プロジェクトごとに精鋭チームをつくり、お客様へ価値を提供するという点です。
企業の解決したい課題や実現したいことに合わせて、プロフェッショナル人材での精鋭体制を構築し、お客様を支援します。
RFP(提案書)の作成で悩まれている企業の担当者は、オーシャン・アンド・パートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
まずは気軽に相談するこの記事を書いた人について
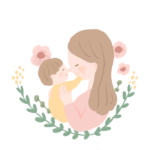
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。