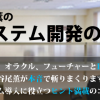10分で分かるIT業界の変遷
こんにちは!オーシャンの谷尾です。
本日のコラムではIT業界の発展史から「情報システムとは何ぞや?」を探っていきます。
10分で読める文量にまとめてみましたので、お気軽にどうぞ。

▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
コンピュータの黎明期
-パンチカード装置の普及がきっかけだった
人類歴史の最初のコンピュータは、1920年代の初頭に産声を上げました。
1920年代から40年代にかけてIBM社の電子機械式のパンチカード装置がベストセラーとなったのがその発祥です。店舗で発生する売上げの数字や仕入れの数字を計算するという仕事は、コンピュータが無いときは、一日の営業活動の集計をそろばんで弾いていました。それをもっと効率的に計算できるということでパンチカード装置が出てきたのです。
IBM社のパンチカードに使う消耗品の用紙は、IBM社から買わないといけないということになり、本体と消耗品を同じ会社が提供するというモデルがスタンダードになりました。
売上げの集計という仕事はどこか本部でやっていたわけでなく、発生したのは店舗でした。そこに目を付けたIBM社の戦略が功を奏し、パンチカード装置がベストセラーになったのです。
メインフレームの台頭
-用途毎に互換性の無い製品ライン
IBM社による世界制覇から業界の歴史が動き始めました。
まずIBM社は最初に電子機械式のパンチカードを装置を出して市場を支配しました。そして、それを集計するためのS/360という大きいコンピュータが出てきます。これが世界のベストセラーになります。
1964年、IBMによるS/360の衝撃発表後、1980年台に至るまで業界はメインフレーム全盛時代を向かえました。従来のコンピュータは、事務処理用と科学技術計算用という異なる製品ラインに分かれており、これらは互換性がありませんでした。ハードやOSだけではなくプログラミング言語も事務処理系ではCOBOL、科学技術計算系ではFORTRANと別のスキルが要求されました。 用途毎に互換性の無い製品があることは、メーカーにもユーザにも大きな負担となっていました。
-単一のプラットフォームで全方位、360度のアプリケーションをカバー
この状況を打破すべく開発されたのがS/360でした。
単一のプラットフォームで全方位、360度のアプリケーションをカバーするという意味合いで「360」を背負って登場したシステムで、メインフレームが「汎用機」と呼ばれるようになった所以です。 また、あまり知られていないのですがが、初めてOSという概念を取り入れたコンピュータでもありました。
-日本も国家的にIBMモデルを追いかけた
この衝撃発表の後、日本も国家的にこのビジネスモデルを追いかけてコンピュータメーカーの戦国時代が始まりました。日本では富士通、日立、NECなどの国産メーカーが出てきましたが、あくまでもIBMが業界のトップリーダーであり、富士通をはじめとする国産メーカーはその他大勢でした。
後を追いかける富士通は、すでに浸透したIBMアーキテクチャーを人類の共通資産とすべく、日立とともにIBM互換路線を選択しました。しかしIBMは設計思想をオープンにすることはなく、あくまでも自社独自路線を走りました。
これらコンピュータメーカーは、マーケティング上どういう戦略をとったかといいますと、すべての部品、製品、消耗品など目に見える品物から、サービスに至るまでの全てを、顧客に販売し続ける権利に執着しました。一度あるコンピュータを売ったら、それ以降そのシステムの中で使われるH/W製品、あるいはS/W製品など全て、自分のカタログから選んで頂く仕掛けを作ったのです。
-メーカーによる支配戦略の終焉
しかしこのコンピューターメーカーによる支配戦略は1990年頃に終焉しました。
これは他の業界や他の製品で考えてみたらごくシンプルなことで、ハードウェアでお客様を支配できるビジネスは存在しません。ハードウェアでお客様を支配するというのはどういうことかというと、例えば、東芝のテレビを買ったら、東芝のビデオデッキとしかつながらない、ビデオテープは東芝製でないとだめだということです。ハードで支配できるビジネスが存在するというのはむしろその業界が未成熟ということです。
IT業界は、一見常に先端技術で競争してきたように見えて、実は業態の存在と考え方は非常に古かったのです。
【メインフレームの予備知識】
高価なプロセッサと200本以上の入出力チャネルの実装により、非常に高コストです。 導入サイドでは、初期費用だけでなく維持費用も高負担となります。 ただし、入出力まわりが充実しているので信頼性は抜群です。逆にオープン系では、入出力まわりが弱点となり、特に、Windows系では他社製品との相性によりシステムがハングアップすることが非常に多い傾向がありました。 加えて単一メーカーによって、導入・開発・運用のトータルライフサイクルのサービスが提供されるので、障害時の対応はピカいちです。電話一本でメーカーの技術者がすぐ駆け付けてくれます。
オープン系ではシステムが複数メーカーの組み合わせで構成されることが多く、ソフトウェア障害の場合問題点の切り分けに時間がかかります。ちなみにソフトウェア製品による障害の場合、ベンダーの技術者が飛んでくるこはまずありません。
また、単一メーカーのハードとソフトで構成されます。マシンが高価なため、メーカー以外のソフトウェア会社がアプリケーションを開発するというオープン系では当たり前のビジネス構造が実現できません。従って、選択できるアプリケーションが非常に少ないです。一方、アッパーコンパチブルが保証されており、上位互換が至上のミッションとされています。 既存のアプリケーションが動かなくなるのは「悪」として認識され、マイクロソフト製品のように、バージョンアップすると動かなくなるということはとんでもないこととして認識されています。
このメインフレームは90年代よりオープン系に駆逐されるようになりますが、高信頼性による根強い需要がいまだに残っています。しかし、既存メインフレームユーザが継続使用するケースがほとんどで、これから新規にITを導入する場合では、ほとんどメインフレームを採用することはありません。 最近では低価格化とアプリケーション(ERPなど)の充実化が進んでおり、独自のマーケットを形勢しています。
ダウンサイジングの波
-集中処理によって浮かび上がった問題点
1980年代半ばまでは大型汎用機が大きく栄えた一方で、集中処理システムの問題点が取り沙汰されるようになってきました。そもそもコストパフォーマンスを高めるために、ホストコンピュータのパワーでさまざまな処理をさせていたのですが、この考え方が仇となって次のような問題点が生じてきたのです。
・ホストコンピュータ負荷の増大
・ソフトウェアの巨大化
・多様化する端末ユーザーの要求に応えきれない
そして、システムの増強に費用がかかる点や、またオープン系のように開発ツールや管理ツールが充実してないことにより、巨大化したソフトウェアはもはや手の付けられないことになっていることが多く、このような問題が非常にインパクト大きく浮かび上がってきたのです。
-同じコストでも性能は前年の2倍以上
そこで問題点の解決として
・安価で機能向上の著しいパソコンやワークステーションなどを利用する。
・資源を適材適所に使い分けてコストパフォーマンスを高める。
という考え方が浸透してきました。 この結果をふまえて、性能が向上した小型コンピュータによる経済面の効率が向上してきました。つまり初期投資が少なく、台数を増やすことが容易である点や拡張性と柔軟性に優れたシステムを構築できる点、システムの変更に対する対応の柔軟性のメリットが市場に認識されることで、ダウンサイジングの浸透が加速し、やがて同じコストで性能は年の2倍の伸びを示すようになりました。
UNIX機の浸透
-自ら手に入れられる部品で構成した最初のマシン
自ら手に入れられる部品で構成した最初のマシン、それがUNIXです。
UNIXが企業システムで大きな話題になったのは90年代前半です。導入コストが高いメインフレームから低価格なUNIX機へ移行するダウンサイジングが華々しくマスメディアを飾りました。
-市場で流通しているハードとソフトの組み合わせが、オープンシステムを生み出した
これを象徴しているのはUNIX機のリーダー的存在、米サンマイクロシステムズの最初の商用機「Sun-1」です。Sun1は、サンマイクロシステムズの創始者が米スタンフォード大学に在籍時、自ら作ったマシンに源流をたどります。当時、大学ではメインフレームやミニコンを複数のユーザがタイム・シェアリングの機能で使っていました。このため重い処理を走らせるには制限がありました。そこで同氏は自分が占有できるマシンがあればと考え、自ら部品を調達しコンピュータを作り上げたのです。ネットワークへの接続機能を標準装備したこのマシンが学生の間で評判となり、「Stanford University Network」(SUN)と名付けられ、何台ものマシンのコピーが作られていきました。そもそもは自ら手に入る部品という制約が、市場で流通しているハードとソフトの組み合わせ、すなわちオープンシステムを生み出したのです。
-メインフレームの代替機として価格が1桁安いUNIX機を提供
その後、低価格化及び高性能化をたどりつつ、90年初頭にはほとんどのコンピュータメーカーが独自のUNIX機を製品化します。このころのUNIX機の典型は、CPUには米モトローラ社の680X0を搭載したものでした。ただし同じCPUでOSがUNIXといっても現在のPCのように異種メーカー間で互換があるわけではありませんでした。そしてその後、CPUもメーカー独自のものを搭載するようになるのです。
90年代に主要なUNIX機メーカーはCPUをモトローラのCISCチップから独自開発のRISCチップへと移行していきます。RISCに移行したことでUNIX機の性能は飛躍的に向上します。
そして、UNIX機の性能がメインフレームの中・小型機のレンジに届くころになると、UNIXメーカー、とりわけメインフレームを製品化していないSunや米HPがメインフレームの代替機として価格が1桁安いUNIX機を提供するようになり、メインフレームの代替機としての訴求が強まっていきます。
Wiondowsの浸透
-WindowsNTは当初ファイル・プリンタサーバとして普及
UNIXを使ったシステムは、企業のシステムを構築する際の選択枝として中心的な役割になろうとしていました。このような状況で登場したのが米マイクロソフト社のWindowsNT(以下、Windowsと記載)でした。企業システムでWindowsが広く使われはじめたのは、1994年からですが、当初はファイル・プリンタサーバとして、UNIXを超えて爆発的に普及していきました。
-ユーザー企業がWindowsの導入に走った理由
ユーザー企業がWindowsの導入に走った理由は、 クライアントOSのWindows3.1と同じGUIを全面採用していたため、LANの運用管理が容易になるようなイメージをユーザにもたせた点が大きいでしょう。またRDBMSやメールなどのサーバソフトウェアを同梱したBackOfficeを提供したことで、業務アプリケーションのプラットフォームとしての将来性を訴求したことも大きいです。
ではなぜ、UNIXよりWIndowsが受け入れられたのでしょうか?
大まかにいうとUNIXよりWindowsのほうがよりオープンなプラットフォームであったからです。身もふたもない言い方をすれば、Windowsのほうが初期導入コストが安く付いたというのが最大の理由です。
商用UNIXと異なり、Windowsの場合はOSとハードを異種メーカの組み合わせで使うことになります。このため複数のハード・メーカーの間で価格競争があり、UNIX機より低価格になります。加えてハードの仕様がクライアントと同じアーキテクチャ(IBM PC AT互換機)であるため量産効果から部品の低コスト化が図れるのです。
-Windowsが示した新たな課題
Windowsの課題は、頻繁なバージョンアップと、それに伴う非互換性や新しいバグの発生が挙げられます。Windowsに限らずオープンシステム全体の課題ではありますが、バグフィックスと機能強化が一体となったサービス・パックを頻繁に提供したことが非互換や新機能におけるバグの問題を大きくしています。
【IBMが委託した相手とは】
オープン系と呼ばれるものが出てきたきっかけは、1981年にIBM社が出したパソコンです。パソコンがオープンという考え方を持ち込みました。IBM社はその当時は、大きなコンピュータが主体の会社でしたので、小さなパソコンを作るということは、エンジニアのプライドもあったため外注化しました。外注化した相手は、3人でできたインテルと当時20歳台だったビルゲイツとポールアレンの2人でできたマイクロソフト社です。
Linuxの出現
-新しいプラットフォームが浸透していく条件とは
Linuxが注目を浴びたのは、オープン・ソースであったことは事の本質ですが、苦労しながらWinsowsを使っている管理者や開発者にとっては問題や課題を解決するように見えたからだと言えます。
メインフレームからUNIX,Windowsにかけての変遷からも分かるように開発者や管理者が多いプラットフォームに対する救世主に見えることが、新しいプラットフォームが浸透していく大きな条件です。
-情報の囲い込みで楽をできる時代が終わる
そして、Linux浸透のもうひとつの意味は、情報の囲い込みで楽をできる時代は終わる、ということです。Linuxを含めたオープン・ソース・ソフトウェアが普及すれば、ソフトハウスが主体性を持って真の意味でのインテグレーションができるようになります。情報は完全にオープンなのでベンダに囲い込まれることなく、会社の枠も超えて本当に力のある技術者と組んで仕事ができるのです。またバグフィックスも早く、長期的にはトータルコストを大きく下げることができるでしょう。
-ソフトベンダの功罪
一方で、マイクロソフト社やオラクル社の最大の功罪は、「メーカーのせいにしていれば責任を取らなくていい」という風潮を作り上げたことです。 それに対してソースさえあれば、いざという時なんとかなるというメリットは計り知れません。
そして完成よりスピード重視のステージへ
私たちは基本的に「完成されていること」に慣れてます。
完成度で競うならば、日本の製造業は圧倒的に世界の一位であり続けるでしょう。たとえば、家電なども極めて完成度が高く、一生のうち自分がお金を払って買った商品がいきなり壊れて動かなくなるという現象にでくわすことはめったにありません。
一方で、IT(とりわけオープン系)の技術は「未完成」です。
例えばマイクロソフト社は「創業以来、自分の売っている製品で完成したものはない」と言ってはばかりません。完成されてない部分は堂々とインターネット上のホームページに開示されてます。感心するのはそれが発見されたとき、極力リアルタイムに近い形で公開されていることです。未完成であることが当たり前の時代になってきています。
ところが、私たちは未完成に対する耐性については発展途上です。しかし実際は、アメリカに先進的なユーザがいて、そこからどんどん日本に入ってきました。新しいものにチャレンジするというのはアメリカのほうが得意で、WindowsというパソコンのO/Sをビジネスで浸透させたのもアメリカです。Windowsが出だしの頃は一日に何度も止まってウンともスンともいわなくなるのに、それをいとわず、新しいものに積極果敢にチャレンジしていったのです。
新しい技術は、常に完成を待たず次の技術を先追いする性格があるため、何らかの欠陥が残された状態で、提供され続ける傾向があります。
その一方、新しい技術は、常にこれまでの技術への反省を元につくられていますし、システムを開発する効率がより良くなるように改良されてもいます。開発の効率が良くなれば、生産性も高くなりますので、同じものをつくるにしても開発期間はどんどん短くなるはずです。ということは、ユーザにとっては最先端の技術を使えば使うほど無駄なコストを使わずにすむというわけです。
「未完成」と「最先端」、この2つのトレードオフをバランスさせて、業務に当てはめていく、このようなセンスと技が、ユーザのIT投資の成否の大きなポイントではないでしょうか。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
この記事を書いた人について

-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社 代表取締役
協同組合シー・ソフトウェア(全省庁統一資格Aランク)代表理事
富士通、日本オラクル、フューチャーアーキテクト、独立系ベンチャーを経てオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社を設立。2010年中小企業基盤整備機構「創業・ベンチャーフォーラム」にてチャレンジ事例100に選出。
最新記事一覧
 経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか?
経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか? 経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは
経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは 経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録
経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録 RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―
RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―