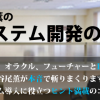このRFPでは誰も提案しない:ベンダーが嫌がるNGパターン

RFP(提案依頼書)は、発注者とベンダーを結ぶ重要なコミュニケーションツールです。
しかし、書き方ひとつで、優れたベンダーからの提案を得られなくなることもあります。
「誰も提案しない」RFPには共通するNGパターンがあります。本コラムではその具体例を挙げ、改善のヒントをお伝えします。
これを参考にすれば、ベンダーにとって魅力的なRFPを作成できるようになるでしょう。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
目次
第1章:目的不明確なRFP
「何をしたいのか」「なぜ必要なのか」が曖昧なRFPほど、ベンダーを困惑させるものはありません。
たとえば、こんな依頼を受け取ったとしましょう。
「DX推進のためのシステム構築をお願いしたい」
一見、具体的な依頼に思えますが、DX(デジタルトランスフォーメーション)というキーワードは非常に広範です。この記述だけでは、何を目指しているのか、どのような課題を解決したいのかがまったく分かりません。
背景にある問題
発注者側がプロジェクトの目的を曖昧にしている理由として、以下が考えられます。
-
プロジェクトの背景や課題が社内で共有されていない
-
経営層と現場の間で目指すゴールに齟齬がある
-
RFPを作成する人が、目的設定に慣れていない
ベンダー視点のリアル
ベンダーは、プロジェクトの「目的」によって提案内容をデザインします。
目的が明確でない場合、どのような解決策を提示すれば良いのか分からず、結果として「参加しない」判断を下すことがあります。
改善のヒント
-
プロジェクトの背景や課題を詳細に記載する
-
定量的なゴールを設定する(例:「売上を5%増加させる」)
-
経営層がプロジェクトの必要性を明確に伝える
具体例として、「競合他社が短納期を実現している中、自社のリードタイムが10%遅れており、これを改善するために受発注システムを刷新する」と書くだけで、提案を大幅に具体化できます。
第2章:過度に細かい仕様指示
細かすぎる仕様記述も、ベンダーを敬遠させる原因となります。たとえば、こんなRFPを想像してください。
「管理画面のボタンは右上に配置し、赤色にしてください」
「日報はPDF形式で、自動生成時間は毎日21時です」
一見、明確な指示に思えますが、これではベンダーが持つ専門知識や創造性を発揮する余地がありません。
また、現実的に最適ではない方法で仕様が固定されている場合、結果として非効率なシステムが構築されるリスクもあります。
なぜ問題なのか?
仕様が細かすぎるRFPでは、以下の弊害が生じます:
-
ベンダーが創造性を発揮できない
-
提案が「発注者の指示通り」に終始し、価値が生まれない
-
発注者が抱える課題の本質が見えにくくなる
改善のヒント
-
「何を解決したいか」を中心に記載する
-
実装方法はベンダーに任せる余地を残す
たとえば、「日報作成の作業負担を削減したい」という課題を記載するだけで、ベンダーはPDF以外の効率的な方法(例:自動メール配信やクラウド上での共有)を提案できるようになります。
第3章:予算未提示のRFP
多くの発注者が陥りがちなのが、予算を明示しないことです。
「まず見積を出してほしい。その後に考える」
こういった依頼では、ベンダーは提案をためらいます。
理由は明白で、どれだけの規模やリソースを投入すれば良いのかが分からないためです。
また、仮に提案を受け入れられたとしても、「こんなに高いの?」という反応を引き出しやすく、無駄な時間を費やす結果になります。
改善のヒント
-
仮の予算範囲を提示する(例:9,000万~12,000万円)
-
予算と期待する成果物のバランスについて具体的に言及する
これにより、ベンダーは現実的で実行可能な提案を作成でき、双方の意思疎通がスムーズになります。
第4章:曖昧なスコープと成果物
「スコープが曖昧」「何でもやってほしい」というRFPも、ベンダーが嫌がる典型例です。
NG例
-
「事業全体のデジタル化を支援してください」
-
「効率化できるところをすべて見直してください」
改善のヒント
-
プロジェクトの対象範囲を具体的に定める(例:在庫管理プロセスのみ)
-
成果物のイメージや期待する効果を明記する
これにより、プロジェクトの進行中にスコープの迷走が発生するリスクを大幅に軽減できます。
第5章:相見積もりを過度に強調する依頼
相見積もりの目的は、複数の提案を比較することで最適な選択を行うことですが、「価格重視」の姿勢が強すぎると、結果的にプロジェクトの成功を損なうことがあります。
NG例
-
「内容と価格のバランスで評価します」
一見、合理的な評価基準に見えますが、内容の評価基準が曖昧な場合、最終的には価格が優先されるケースが少なくありません。
価格重視の空気が暗黙の了解となると、提案内容の質が低下します。 -
「価格は一番重要な決定要素です」
明確に価格を重視すると示されると、ベンダーはコスト削減を最優先に考えるため、プロジェクトに付加価値を生む提案が期待できなくなります。
なぜ問題なのか?
こうした発注方法では、ベンダーは利益確保のため、最低限の提案やリスクを排除した内容を提示する傾向があります。結果として、納期や品質のトラブルが発生するリスクが高まります。
-
「価格ありき」の提案では、長期的な価値創出が期待できない
-
ベンダーが質よりもコストに重点を置くため、プロジェクトの成果が限定的になる
なぜベンダーは嫌がるのか?
-
「安さ競争」に巻き込まれると、リソースを適切に割けなくなる
-
プロジェクトに必要な付加価値を提案しにくくなる
改善のヒント
-
提案評価の基準を「価格」だけでなく、「提案内容の質」「価値創出の可能性」にも重みを置く
-
発注者が価格以上に重視する要素(例:運用のしやすさ、柔軟性など)をRFPに明記する
たとえば、評価項目に「5年間の運用総コスト削減を見込める提案かどうか」を加えることで、ベンダーは短期的な価格だけでなく、長期的な効果を考慮した提案を行いやすくなります。
あるいは、「業務プロセスを効率化し、年間100時間の工数削減を目指す」という目標があれば、単なる価格競争ではなく、達成可能性や効果の大きさを評価基準に加えるべきです。
第6章:一方的で不合理な契約条件
契約条件は、発注者とベンダー双方にとって納得感があることが重要です。しかし、これが一方的で不合理な場合、ベンダーの信頼を損ね、結果として優れた提案が集まりにくくなります。あるいはベンダーは参加をためらうか、提案内容を大幅に制限せざるを得なくなります。
NG例
-
「全リスクはベンダー負担とします」
たとえば、発注者の提供するデータが不十分だった場合や、外部要因(災害や規制変更)による遅延であっても、全てベンダーが責任を負うという条件です。こうした条件では、ベンダーは提案内容を保守的にするか、提案を断念する可能性が高くなります。 -
「納期遅延の場合は1日あたり罰則金を課します」
厳しいペナルティ条件があると、ベンダーはスケジュールの安全マージンを確保するために高額な見積もりを提示したり、納期を優先するあまり、質の低い成果物を納品するリスクがあります。
なぜ問題なのか?
これらの条件は一見、発注者の利益を最大化するように思えますが、実際にはベンダーが提案をためらう原因となります。特に「リスクのすべてをベンダー負担にする」という条件は、優れたベンダーほど避ける傾向があります。
-
ベンダーが過剰なリスクを避けるため、提案内容が限定的になる
-
リスク負担が偏ると、プロジェクトの実行フェーズでトラブルが頻発する
-
ベンダーが保守的な提案を行い、プロジェクトの価値が低下する
-
過剰なリスク負担が、提案の参加そのものをためらわせる
改善のヒント
-
リスクを双方で分担する条件を設定する
-
納期遅延やトラブル時の対応を協議の上で決定する柔軟性を持たせる
たとえば、「予期せぬ事態による遅延については、双方で状況を確認し、妥当な対策を協議する」といった条件を明記することで、ベンダーが安心して提案できる環境を整えられます。
第7章:実績重視主義
RFPにおいて「実績重視」の姿勢は、一見するとリスクを最小化し、確実性の高いベンダーを選定するための合理的なアプローチに思えます。しかし、この方針が過度になると、ベンダー選定の幅を狭め、本来適切な提案を受けられないリスクを高めてしまいます。特に新しい挑戦を伴うプロジェクトでは、「実績重視」が致命的な妨げになる場合があります。
NG例
-
「過去に同じ業界で成功した実績があることを条件とします」
特定の業界や分野での実績を重視すると、既存の手法に依存した提案が多く集まり、新しい視点を持つベンダーの参入が阻害されます。 -
「本件と同様のプロジェクト事例があることを必須条件とします」
新規性のある試みであればあるほど、必須条件としての「実績」を満たせるベンダーは存在しません。これにより、革新的な提案を行う意欲的なベンダーを排除してしまうことになります。
なぜ問題なのか?
-
新規性のあるプロジェクトで真の価値が得られなくなる
新しい試みには、既存の事例では対応できない課題が含まれることが多いです。実績重視の姿勢では、このような課題に対応する柔軟性を持つベンダーを選びにくくなります。 -
革新性を阻害し、従来型の解決策に終始する
実績が豊富なベンダーは安心感を与える一方で、過去の成功体験に基づいた提案を行う傾向があります。これが新しい挑戦における柔軟な発想を妨げることがあります。 -
革新的な解決策を得られない新しい挑戦には、新しい視点や技術が必要です。実績に固執すると、過去の成功体験に頼った提案しか得られず、真に革新的な解決策を見逃す可能性があります。
-
市場の変化に対応できない
競争が激化する市場では、既存の手法だけでは生き残れません。新しいアプローチを提案できるベンダーを排除すると、競合他社に後れを取るリスクが高まります。 -
ベンダーのモチベーションを低下させる
「実績がないと提案できない」という条件は、新規参入やスタートアップ企業のモチベーションを大きく下げます。これにより、市場に存在する優秀なリソースを活用できなくなります。 -
先進的なベンダーを排除してしまう
特に新しい挑戦を伴うプロジェクトでは、以下のようなベンダーが最も適している可能性があります:
「本件は新しい挑戦のため、事例はありません。もし今回の試みが実現したら、それが最初の事例になります」と語るベンダー
こうしたベンダーは既存の枠組みにとらわれず、柔軟で創造的なアプローチを提供する可能性があります。
しかし、実績重視のRFPでは、こうしたベンダーは選定対象外となり、結果としてプロジェクトが陳腐な方向に進む危険性があります。
具体例
ある企業が、AIを活用した新規サービスの開発を計画していました。RFPには「同様のAIサービス開発の実績があること」を必須条件として記載。しかし、AI分野は急速に進化しており、過去の実績が最新の技術力を保証するものではありません。結果として、最新の技術を持つスタートアップ企業からの提案を受けられず、旧態依然とした解決策しか得られませんでした。
改善のヒント
-
「実績」ではなく「課題解決能力」に目を向ける
「業界での事例があること」を必須条件とするのではなく、「課題に対する理解と解決策の妥当性」を重視する評価基準を設けるべきです。 -
条件を柔軟にする
RFPには次のような表現を使うことで、革新性を持つ提案を歓迎する姿勢を示します:
- 「今回のプロジェクトは新しい試みであり、従来の事例にこだわりません」
- 「新しいアイデアやアプローチを歓迎します」 -
提案内容の評価基準を多角的にする
提案内容の独自性、実現可能性、問題解決のアプローチなどの多様な観点から評価を行い、実績に偏らない評価基準を設定します。 -
過去の実績を必須条件にしない
「実績があれば望ましい」という程度にとどめ、必須条件としないことで、幅広いベンダーからの提案を促します。
実践例
RFPで以下のように記載する。
-
「過去の事例があることは加点要素としますが、必須条件ではありません。」
-
「新しい挑戦に対応できる柔軟性や創造性を重視します。」
-
「今回の試みが実現すれば、それが最初の事例となります。過去の実績にとらわれず、我々と共に新しい価値を創造していただけるパートナーを求めています。」
これにより、先進的なベンダーも参加しやすくなり、プロジェクトの成功可能性を高めることができます。
結論:提案を引き出すRFPの作り方
RFPは単なる発注書ではなく、プロジェクトの未来を切り開く第一歩です。
優れたRFPを作成するためには、プロジェクトの目的や背景を明確にし、ベンダーが最適な提案を行える環境を整えることが不可欠です。
-
目的を明確にし、発注者がプロジェクトの全体像をしっかり把握すること
-
ベンダーが提案しやすい環境を整えること
-
価格だけに偏らない、長期的な価値を重視する視点を持つこと
本コラムで紹介したNGパターンを避け、ベンダーにとって魅力的なRFPを作成することで、プロジェクトの成功確率を高めることができます。発注者としての責任を果たし、ベンダーとの良好なパートナーシップを築くためにも、RFP作成時にはこれらのポイントをぜひ参考にしてください。
▼オンライン相談会も実施中!詳しくは下記からお問い合わせください▼
この記事を書いた人について

-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社 代表取締役
協同組合シー・ソフトウェア(全省庁統一資格Aランク)代表理事
富士通、日本オラクル、フューチャーアーキテクト、独立系ベンチャーを経てオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社を設立。2010年中小企業基盤整備機構「創業・ベンチャーフォーラム」にてチャレンジ事例100に選出。
最新記事一覧
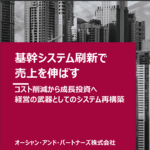 経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか?
経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか? 経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは
経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは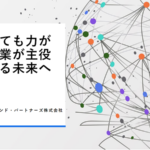 経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録
経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録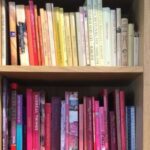 RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―
RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―